
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
オフィス業務に欠かせないものの1つが、適切な文書管理だ。企画や契約、請求などの業務はすべて文書という形態をとることで情報共有や評価が行われる。こうした書類をどのように保管し、利用していくのかは、業務効率化を考える上で避けて通れない。リモートワーク・テレワーク環境の浸透など、各種業務のデジタル化が進展していくことで今後どのように書類を保管していくべきなのかを考えてみよう。
前回、業務の効率化を考えるに当たって、まず多くの書類をデジタル化することの重要性について述べた。紙文書をデジタル化するスキャニングの機器は高度化と高速化が進み、以前よりはるかに手軽に紙の書類をデジタルデータに変えることできる、といったものだ。さらに現在では「AI-OCR」というAIとOCRを組み合わせた高精度のOCRサービスを活用して、手書き文字を認識してテキストデータに変換することで、手書きの申込書や発注書などを容易にデジタルデータ化することができるようになっている。
こうした一連の業務は、RPAの活用でさらに効率化することができる。例えば、FAXで送られてくる手書き発注書の情報をAI-OCRによってテキストデータに変え、それをRPAによって販売システムに自動で入力するようにすれば、人手を一切介在させることなく、正確に業務処理を完了できる。
そして、文書をデジタル化して紙書類の廃棄ができれば、保管スペースは劇的に削減され、デジタルデータになった文書の共有や再利用もスムーズに行えるようになる。これはオフィスにとって革命とも言える大きな変化だ。
しかし、一方で別の課題も浮上してくる。デジタル化された文書データをどこに保管するのが最適なのかという点だ。ここまでを視野に入れたうえでデジタル化を進めることが、業務の効率化から成果を引き出すことにつながる。
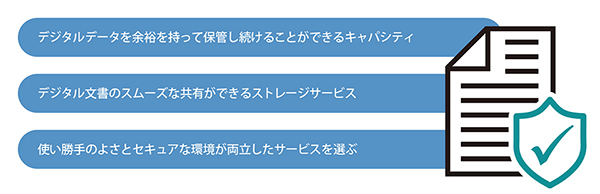
デジタル化された文書データの保管方法を考える上で欠かせない視点が3つある。第一にキャパシティーだ。デジタルデータは紙文書のような保管場所は必要がない。しかし、保管するメディアによって容量制限が発生する。単純に1テラバイトのハードディスクであれば、1メガバイトの文書データを100万件格納することができる。
第二に使い勝手だ。デジタル化のメリットを引き出すためにはデジタル化された文書データがスムーズに共有できることなどが求められる。個人作業用のパソコンのハードディスクではなく、ネットワーク上にある共有可能なストレージが必要になる。
そして、第三がセキュリティ。いくら使い勝手がよくてもセキュリティレベルが低ければ、情報漏えいなどのセキュリティリスクが高まる。使い勝手とセキュリティが両立してこそ、安心してデータが活用できる。
これらの3つの視点から考えると、おのずと最適解が見えてくる。データ容量の増加に柔軟に対応できて、ネットワークを通して必要な人が必要な時にデータにアクセスできるような仕組みを持っていて、強固なセキュリティ対策が講じられているクラウドストレージを活用することだ。
物理的な制約があるハードディスクでは、容量を増やすたびに手間がかかる。社内ネットワークに接続されたストレージはデータ共有ができても、容量に制限があることは変わらない。暗号化されたUSBメモリーであればセキュリティレベルは高いが、紛失のリスクがあるうえ、情報共有の手段として使い勝手がよいとは言えない。
これまでさまざまなデータ共有の方法に挑戦してきた企業は、上記のような使いづらさを経験してきた。その結果、現在ではセキュアなクラウドストレージが選ばれるケースが多い。これからデジタル活用を本格化させる場合には、ぜひこうした視点から自社にとっての最適解を導いてほしい。
執筆=高橋 秀典
【MT】
強い会社の着眼点