
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
「せっかくオンライン商談を設定したのに、相手にこちらの声が届かず、何度も『聞こえますか?』と繰り返すことになった。これでは先方の信頼を失いかねない」。こんな経験をしたビジネスパーソンも少なくないだろう。原因はもしかすると、不安定なWi-Fi通信かもしれない。Wi-Fi、すなわち無線LANは、ビジネスでも日常生活でも、すでになくてはならないインフラになっている。
オフィスでは場所を問わずに業務ができるように、ノートパソコンをWi-Fiに接続して利用している。パソコンに加えて業務用のスマホやタブレットもオフィス内ではWi-Fiでつながり、さまざまな業務システムやクラウドサービス、プリンターなどの周辺機器を利用している。家庭でもスマホやパソコンはもちろん、動画配信を見る大型テレビから、AIスピーカー、エアコンなどの白物家電まで、Wi-Fi接続の機器はあふれている。それだけに、通信が集中し、電波環境に問題が発生すれば冒頭のように通信が不安定になる恐れもある。
そんなWi-Fiに、新しい規格の「Wi-Fi 7」が登場し、対応製品が着々と増加していることをご存知だろうか。Wi-Fi 7は、Wi-Fi Allianceの7番目のWi-Fi規格ということで、この名前が付いている。技術的な国際規格としてはIEEE 802.11beとして標準化されている。「Wi-Fiはいろいろな規格があるようだけれど、新しい規格はなぜ必要だったの?」という疑問もあるだろう。Wi-Fi 7は、通信の速度向上と同時に通信の安定に向けた多様な技術を採用している。単に通信の最高速度が速いだけでなく、環境の変化に対して安定して通信を継続可能というわけだ。
Wi-Fiは、世代ごとに性能を向上させて、通信インフラの1種類としての地位を盤石なものにしてきた。Wi-Fi 7が登場する前は、Wi-Fi 6とWi-Fi 6Eが最新規格として、ビジネスやパーソナルな通信の要望に応えてきた。例えば、Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)は、「直交周波数分割多元接続(OFDMA)」という技術を採用して同時接続に強くなり、テレワークやクラウド利用を支えてきた。Wi-Fi 6E(規格名は同じく11ax)では6GHz帯という新しい周波数帯が利用可能になり、通信の混雑解消に寄与してきた。ちなみに、Wi-Fi 7は、Wi-Fi 6や6Eをベースに、さらに技術的な改良が加えられている。
最もインパクトがあるのは、理論上の最大速度がWi-Fi 6/6Eの9.6Gbpsから、46Gbpsへと大幅に引き上げられたことだろう。変調方式の高度化による効率アップと、最大の帯域幅が倍増したことによる効果が現れている。
さらに、安定した通信が可能な点がWi-Fi 7の特徴になる。1つのデバイスの通信が複数の周波数の電波を同時並行で使えるMLO(Multi-Link Operation)の採用で、ある周波数帯に干渉があっても他の周波数帯で通信を継続できるようになった。また、通信する信号を複数のユニット(RU:Resource Unit)に分け、同時に1つのデバイスに複数のRUを割り当てられるMulti-RU(Multi-Resource Unit)に対応した。これらにより、安定性と低遅延を実現している。
つまり、データのやり取りが途切れにくく、ビジネスシーンならばオンライン会議での音声遅延やクラウドアプリの動作遅れが大幅に改善される。日々の業務にある通信の小さなストレスを解消することにWi-Fi 7が貢献できるのだ。オンライン会議が当たり前になり、メールやストレージ、業務システムまでがSaaSとしてクラウドサービスで提供される時代だからこそ、パソコンやスマホとシステムを結ぶWi-Fiの安定性や低遅延性が一層求められるようになっている。
そんなWi-Fi 7だが、総務省が国内での利用を解禁したのが2023年12月とまだ最近のことで、対応製品が広く提供されているとまでは言えない。Wi-Fiルーター側では、主要メーカーの上位機種からWi-Fi 7対応が進んでいるが、上位機種が中心ということから価格帯も高めになってしまう。通信するデバイス側も、パソコン、スマホともに最近の機種ではWi-Fi 7で通信可能とはいえ、市場に出回っている機種全体からするとまだまだ対応機種は限定的だ。Wi-Fi 7の効果を得るには、Wi-Fiルーター側とデバイス側の両側で対応機器を揃える必要がある。Wi-Fi 7の効果を存分に得たくても、多くの機器が混在するオフィスなどですぐに全面対応するのは難しい。
それでも、手をこまねいていては今後のWi-Fi環境の改善が足踏みしてしまう。まずは、自社について、現状の通信環境を棚卸しすることから始めよう。具体的には、(1)Wi-Fiルーターに接続しているインターネット回線は十分な速度が得られているか、(2)Wi-Fiルーターの性能や稼働の状況はどうか、(3)オフィスや職場内のWi-Fiの電波状況はどうなっているか――などだ。同時に、(4)パソコンや社用のスマホ、タブレットなどのWi-Fi 7への対応状況も確認しておきたいところだ。
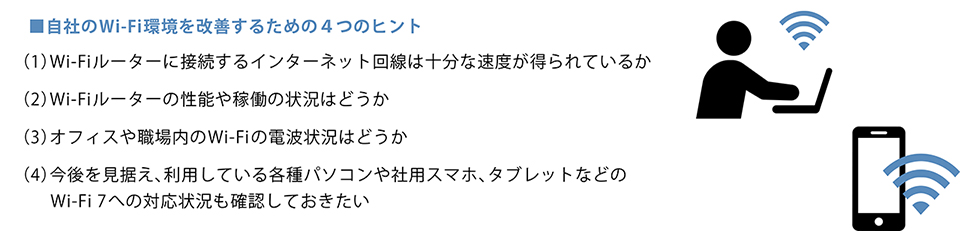
こうした棚卸しができれば、Wi-Fi環境改善に向けた戦略の立案ができる。例えば、通信速度が低く通信が不安定なフロアや部門からWi-Fi 7ルーターを段階的に導入していき、対応する従業員にWi-Fi 7対応デバイスを割り当てれば、Wi-Fi 7が部分的にであっても効果を発揮するだろう。
また、棚卸しの結果、「すぐにWi-Fi 7までは必要がない」状況であっても、オフィスの従業員や来店者などに快適なWi-Fi環境を提供するため、業務用Wi-Fiをレンタルで採用して現状を改善するなどの対策も可能だ。さらに、Wi-Fiルーターの性能やトラブルが業務に支障を与えている可能性があるようならば、ルーターの運用保守サービスを導入して修理などに対応していくことも考えられる。
Wi-Fi 7は、これから数年かけて社会に広がる「未来の標準Wi-Fi」だ。プライベートの家庭内利用ならば、スマホの新機種購入に合わせてWi-Fiルーターを最新機種にすれば快適なWi-Fi環境が手に入る。しかし、オフィスなどのビジネスシーンでは機器の数も多く、話は家庭ほど簡単ではない。それでも理想としてのWi-Fi 7環境を見据えながら、今ある通信環境を少しずつ理想に近づけられるように、Wi-Fi環境やインターネット回線の棚卸しを始めていくところから改善に着手していきたい。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=岩元 直久
【MT】

強い会社の着眼点