
脱IT初心者「社長の疑問・用語解説」(第98回)
"トンネル"を抜けてデータを安全にやり取り
生産年齢人口の減少と人手不足の影響が深刻化する中、多くの企業では、限られた人員でいかに業務を効率的に行うかが問われ始めている。例えば、これまでの業務の進め方やプロセスの見直しを行い、不要な業務や重複している業務があれば改善を行う。また、特定の社員に依存する業務があれば標準化やマニュアル化を実施し、社内の誰でもその業務に柔軟に対応できるようにする。これらの取り組みが奏功することで、社員全体の負担軽減とともに、余剰時間が生まれ「定時の退社」が可能になる余地が生まれてくるだろう。今回は、そこから一歩踏み込み、取り組みの土台となる会社のネットワーク設計も考えていきたい。
「定時の退社なんて、絵に描いた餅。できっこない」という声も聞こえてきそうだが、定時はともかくとして、時間外労働時間を減らし、社員が働きやすい環境づくりは多くの企業にとって急務だ。子育てや介護などのプライベートと仕事の両立はもちろん、人々の生き方、価値観も多様化する今日、「仕事漬け」の職場では人材の定着も、優秀な人材の確保も難しいからだ。
働きやすい環境づくりや組織の活性化、業務の効率化に欠かせないのがIT環境の整備だ。すでに各種のITツールを十分に駆使しているという企業や、ITを活用した業務改革、DXを積極的に進めている企業もあるだろう。プラスアルファの視点として、業務のさらなる見直しや効率化を図るためには、個々の社員の勤務状況を把握することもポイントになる。
この点、AIを活用して社員の勤務実態を見える化するクラウドサービスもある。社員が利用するパソコンのログを集め、勤務時間、時間外労働時間を把握する。特定の社員に業務が偏っているのであれば、他の社員にその業務の一部を任せることで負担を軽減することも可能だ。また、パソコンのログで定型業務ごとの作業時間も把握でき、作業の見直しや定型業務をRPAで自動化して業務を効率化するといった経営判断に役立てられる。
ITを活用した業務の効率化というと、効果が見えやすい業務システムや業務アプリに目が行きがちだが、ビジネス活動のインフラとなるネットワークも重要になる。いくら業務を効率化するためのシステムやアプリを導入しても、その基盤となるネットワークの信頼性や安定性、安全性に問題があれば十分な性能を発揮することができない。例えば、本社に業務システムのサーバーを設置して各拠点からアクセスする場合、本社と各拠点を結ぶネットワークに問題があれば迅速なレスポンスにも影響を与えかねない。業務効率化のために導入したシステムが、ネットワークの問題で業務効率の低下を招く恐れもあるのだ。
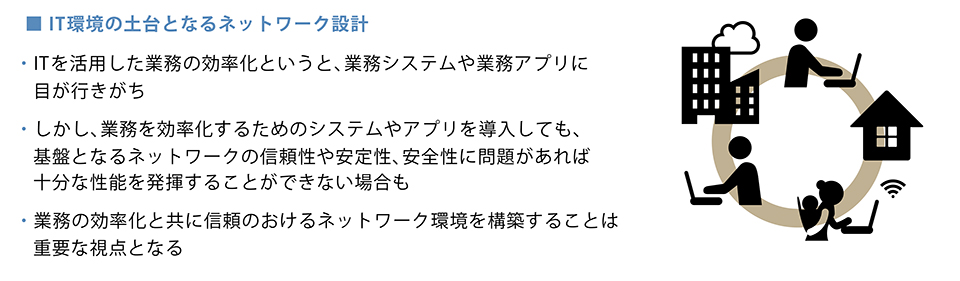
ネットワークとITを活用して働き方改革や業務の効率化を図り、「定時の退社」を可能にしている企業もある。介護サービス事業を展開するA社では、訪問看護などを担う職員の多くが子育て世代のため、ITを活用したワークライフバランスに注力してきた。訪問看護など事業所外で仕事をする職員にスマートフォンを支給する他、デイサービスなど通所介護を担当する職員にはタブレット端末を支給し、クラウドサービスのビジネスチャットやメールを用いて情報共有・交換を行える職場環境を整備している。一例としては、職員が「訪問看護先の●●さんが風邪をひいたので、明日のデイサービスはお休みします」といった情報をチャットでやり取りすることで、報告のために事業所へ戻ることなく利用者宅から定時での直帰を可能にしている。クラウドサービスへの接続はインターネットを利用しているが、介護サービス利用者の個人情報を扱うことからインターネットVPNの利用を検討しているところだ。
先ほど触れた、インターネットVPNはインターネット上にセキュアな閉域網を設け、通信内容の暗号化が可能なことから、企業の広域ネットワーク(WAN)の手段の1つとして利用する企業は多い。この一方で、社外で利用するユーザーの増大とともに、ネットワーク設計の課題も浮かび上がっている。
製造業のB社ではインターネットと社内ネットワークの出入り口となるゲートウェイにVPNやファイアウォールなどのセキュリティ機能を備えたUTM(統合脅威管理)を設置した。しかし、働き方の多様化とともにリモートワークなど社外からのアクセスが増え、想定以上のトラフィックがVPNに集中し、ネットワークのボトルネックが発生した。
リモートワークや各拠点からWeb会議や業務アプリなどのクラウドサービスに頻繁にアクセスすることで本社と各拠点を結ぶネットワークにも遅延が発生し、業務に影響を与えかねない事態となった。解決策として大量の同時セッションに対応するVPN装置の導入も検討したが、増え続けるトラフィックに対して抜本的な対策にはならないと判断した。
そして、本社を経由せずに各拠点からインターネットへのトラフィックを振り向けるインターネットブレークアウト(SD-WAN)対応のVPN装置の導入を決め、新たなネットワーク設計を行った。ネットワークのボトルネックが解消されたことでクラウドサービスの業務アプリなども快適に利用できるようになり、業務効率の向上にも効果があるという。
企業の各拠点を閉域網で結ぶネットワークとして、インターネットVPNの他に通信事業者が提供するIP-VPNサービスがある。その特徴の1つとしては、当該事業者の提供サービスを軸としてアクセス回線に企業ごとのプライベートネットワークを構築できる。各拠点から本社やデータセンターに設置した基幹系システムや業務システムなどへ安全にアクセスするなど拠点間の通信に適している。また、映像など大容量・リアルタイムのアプリケーションに適したIP-VPNサービスもある。こちらは企業の各拠点にIPv6に対応したルーターを設置し、事業者のNGN網とダイレクトにつなぐことで低遅延かつ安定したネットワークの構築が可能だ。
「定時で帰れる」かどうかは、各企業の取り組みによる部分も大きいと考えられるがネットワークの安定稼働が実現すれば、社員のスムーズな業務が可能になり、IT部門の担当者は帰宅後の呼び出しに悩まされる不安は軽減されるはずだ。今後、生成AIなどの活用とともに新たな業務アプリの導入も進み、クラウドサービスへ接続するトラフィックが増えていくことが予想される。ネットワークの再設計はビジネスの再設計にもつながる。自社にとってどんなネットワークが必要か、専門家に相談しながら検討したい。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=山崎 俊明
【MT】
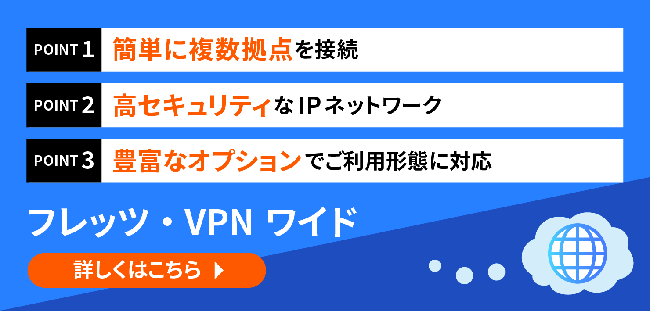
強い会社の着眼点