
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
政府からの修学時間確保の要請を受けて策定された、日本経済団体連合会の「採用選考に関する指針」。法的拘束力はないが、2016年3月卒の学生への広報活動は今年3月、選考活動は今年8月開始となった。採用活動の“後ろ倒し”に加え、大手の業績回復、人手不足もあり、中小企業の人材獲得は厳しさを増している。
「来年卒業を予定している大学生の就職説明会への参加応募者数が、昨年の1161人から約4分の1の281人に激減した」。屋上・壁面緑化事業を手掛ける東邦レオ(大阪市中央区)の橘俊夫社長はこう話す。
幸い実際の説明会参加者数は昨年の297人に対し、今年は203人と大差はなかったので、5月中旬現在、採用活動に大きな支障は出ていない。とはいえ、「短期決戦で時間が限られるので、学生が就職説明会に参加する企業を厳選している」と橘社長は見る。
短期決戦とは、今年から採用活動の開始時期が“後ろ倒し”になったことを指す。政府からの修学時間確保の要請を受け、日本経済団体連合会は「採用選考に関する指針」を策定。加盟企業に今年度から就職説明会などの広報活動は3月、面接などの選考活動は8月に始めるように促した。
指針に法的拘束力はないが、大手企業を中心に多くの企業はこのスケジュールを守っている。昨年までは大学生の場合、3年生の冬頃から就職説明会を始め、4年生の4月頃から面接に移り、夏頃までに学生に実質的な内定を出す大企業が多かった。中小企業は、その後に採用活動を本格化する流れが一般的だった。
だが、大企業の採用活動の期間が後にズレたことで、中小企業の採用活動の期間は短くなる見込みだ。この流れを無視して早めに内定を出したとしても、「大手が後に内定を出すと、辞退されかねないとの不安から、対応に苦慮する中小企業が多い」と新卒採用の実情に詳しいジェイック(東京・千代田)執行役員の内野久氏は話す。
加えて、業績回復もあって大企業は積極的に採用活動を進めているものの、国内若年人口の減少で、各企業とも慢性的な人手不足。限られたパイを奪い合う状況が続く。リクルートキャリアが、昨年12月~今年1月に従業員5人以上の企業に、採用スケジュール変更に伴う新卒大学生(大学院生を含む)の採用人数の見通しを聞いたところ、「減ると思う」が40%を超え、「増えると思う」の4・1%を大きく上回った(図1参照)。
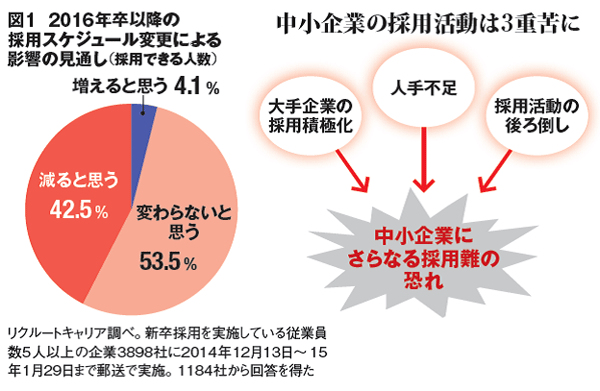
帝国データバンクは今年2月、2万3365社に採用時期の後ろ倒しに伴う影響を尋ねた。「中小は『分からない』が37%と大手より多く、現状では影響を見極められない様子がうかがえる」(図2、顧客サービス統括部情報企画課)。
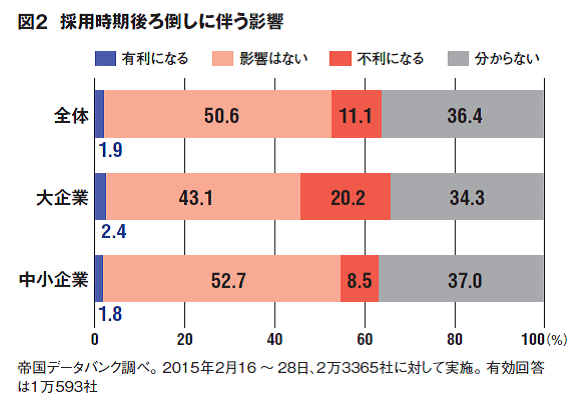
では、厳しさを増す採用戦線の中で中小企業はどのような手を打てばいいのか。ポイントを5つに整理した。
まず自社の特徴を明確にし、どんな仕事ができるのかトップ自らが訴えること。短期決戦である以上、中小企業は社長が説明会などで事業内容や働き方の魅力を語らなければ、存在さえ学生に認知されずに採用期間が終わる恐れがある。
2つ目は、規模の小ささをプラスと捉え、社員の間に一体感がある点を前面に出してアピールすること。「人事担当者が採用後にそのまま責任を持って人材育成も手がけるなど、距離感の近さを訴えれば、魅力を感じる学生はいる」と、リクルートキャリア(東京・千代田)の就職みらい研究所の岡崎仁美所長は話す。
3つ目は若いうちから幅広い仕事を任せる点を強調すること。人数が少ない分、1人で手掛ける業務範囲が広い点を前面に打ち出したい。
4つ目は親や家族とのコミュニケーションを密にすること。事業内容や社風を紹介する動画や冊子をつくるなど、「中小=ブラック企業」との誤解をなくす。本人が入社を望んでも、親や家族の反対で断念するリスクを減らしたい。
最後がインターンシップ(就業体験)によるミスマッチの解消。今年の新卒採用活動には手遅れかもしれない。だが、来年以降の新卒採用活動、または今年の中途採用活動を検討しているなら有効だ。業務内容や社員の働きぶりなどを事前に理解してから採用試験を受ける人は、本気で働きたいと考えていることが多い。
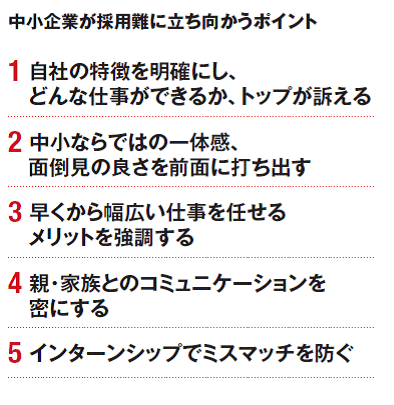
東京・墨田の板金加工会社、浜野製作所では、大学生や高校生のインターンシップをここ数年毎年4~5人受け入れている。「インターンシップ経験者が採用試験を受けて入社するケースが続いており、ほとんどの人が辞めていない。来年もインターンシップ経験者1人の採用が既に決まっている」(浜野慶一社長)という。厳しい環境は続くものの、諦めずに手を打ち続ける努力が欠かせない。
日経トップリーダー/久保俊介
【T】
中小企業のトレンド