
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
冬の冷え込みが厳しい八ヶ岳山麓の生活で、重要な働きをしてくれるのが暖房だ。私たちは新居に、憧れのまきストーブを取り付けることにした。でも、問題は燃料となるまきをどうやって集めるかで……。
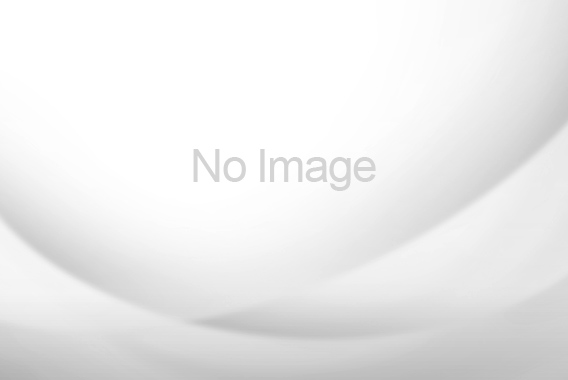
家族が自然に集まる場所にしたいと、リビングに小さなまきストーブを入れることにした(写真はイメージです)
暖かにゆらぐ炎、どこか懐かしい木の燃える香り、そしてまきがパチパチとはじける音。たき火をボーッと眺めているだけで、不思議と心が落ち着いていく。キャンプなどで火の暖かさや癒やし効果を実感していたこともあって、新しい家ではまきストーブを囲む生活をしたいと設置することに決めた。
でもまきストーブには大量のまきが必要となる。それをどうやって調達するかが問題だ。知人に聞いたところ、業者からまきを購入すると、一冬分で数万円かかり、石油ストーブの燃料代よりも割高になるという。太陽熱を暖房として利用するシステムを採用した新しい家では(本記事第7回『私たちらしい家づくり』参照)、太陽が出ない日の補助としてまきストーブを使うことを想定しているためまきの消費量は多くないと見込んでいるけれど、それでもなるべく出費は抑えたい。
購入する以外に、どこかで手に入らないだろうか……と考えていたある日、偶然に山梨県のホームページで「伐採した木を無料で差し上げます」という告知を見つけた。飛びつくように案内を読むと、山梨県中北建設事務所(https://www.pref.yamanashi.jp/ch-kensetsu/)では、河川の管理をするうえで支障となる木を伐採しているそう。それをまきの原木として自由に持って行ってよいらしい。木は2mほどの長さに切りそろえて河川敷に集めてあるという。こんなにありがたいことはないと、早速丸太を運ぶ作戦を考えた。
木の配布は11月のある平日の朝に開始された。複数ある配布場所のうち、新しい家から近い河川敷へ行く。夫はどうしても仕事を休めなかったので、私の両親を呼んで木の運搬を手伝ってもらうことにした。わが家の車は中型のSUV。親の車はミニバンである。たくさんは運べないが、2台とも後部座席を倒せば、10本ぐらいは持って帰れるだろうと考えた。
当日、開始時間に両親と待ち合わせをし、配布場所へ行ってみて驚いた。どうやら原木の無料配布は毎年恒例のようで、勝手知ったる地元の人たちが、軽トラで列をなして河川敷に入っていく。会場にはすでに数十台の軽トラックが止まっていて、積み込みの作業をしていた。プロかと思うほど手際よく丸太を運び、早くも荷台がいっぱいになっている車もある。
乗用車で来ているのは私たちぐらいだ。雰囲気に圧倒され、様子をうかがいながら車を奥へと進めた。なんだか軽トラの人たちに「素人がやってきたぞ~」と思われているようで気恥ずかしく(実際は誰もそんなこと気にしていないだろうが)、配布場所の一番奥、邪魔にならない場所に控えめに車を止めた。
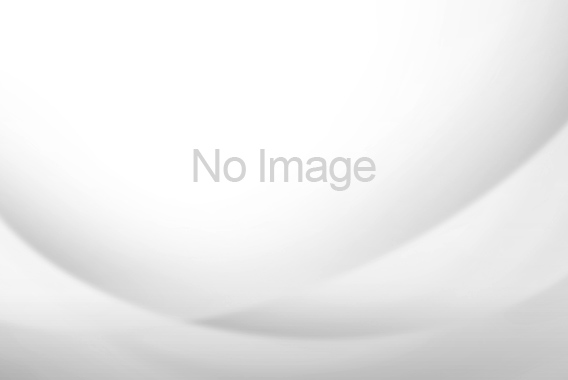
配布場所には軽トラがズラリ。乗用車で乗り込んだ私たちは明らかに浮いていた
広い配布場所には、軽トラが入れ替わり立ち替わりやってきても、1日では運び出せないほどの丸太が積まれていた。その端で、私たちも丸太をもらう。長さ2mの丸太を2人で抱えて、車に載せる。ところが、木は5㎝ほど長くて、そのままではドアを閉められない。事前に調べたところでは、ギリギリ入ると思ったんだけど……。
「そんなこともあろうか」と、父は小型の電動ノコギリを用意してくれていて、それで車に積める長さに木をカットすることにした。「さすがお父さん!」。これならば、結構の量を持って帰れると、いい調子で木をカットしては積み始めた。でも、何本か切ったところで、悲しいことに電動ノコギリは充電切れ。頼りの武器が使えなくなってしまった。
こうなったら手動で切るしかない。電動ノコギリを手のこに持ち替え、3人が交代でしゃがみ込んでシャカシャカと木を切る。地元の人たちが使うチェーンソーの爆音があちこちで響く中、私たちは手のこでの作業で、いかにも地味だ。そんな姿に自分でも笑ってしまうのだから、周りから見たら、かなり滑稽だっただろう。
3人とも腕がパンパンになるまで木を切って、2時間ほどで車がいっぱいになった。10本もらえれば十分だと思っていたけれど、2台で20本ぐらいは積んだだろうか。重くなった車を運転して新居へ移動し、敷地の傍らに木を運んで下ろした。
木の無料配布は、ローカルなお祭りに、よそ者が飛び入りで参加したような違和感だったけれど、体を使った労働が心地よく、未知の体験が楽しかった。そして、タダで手に入れたまきの原木に、ニンマリ。山梨県に感謝した。
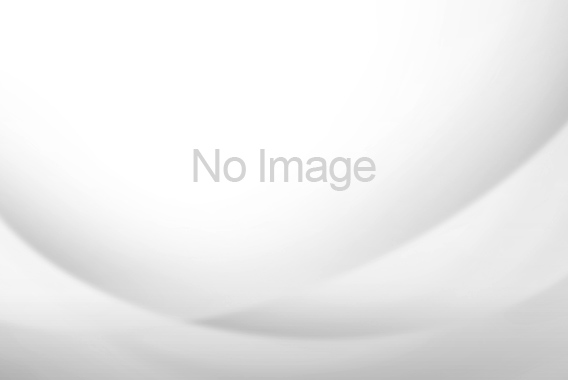
無料配布でもらった木を仮積み。これでまきストーブ何日分になるだろうか?
木は後日、やはり父が新しく持ってきたチェーンソーでストーブに入る長さにカットし、今は仮積みしてある。さて、この大量の丸太を、今度はいくつかに割って、使用するまでにしっかりと乾かさなければならない。想像しただけでも重労働だ。それに、まきを保管するための小屋も作らなければ。山麓で暮らすためには、畑が一段落した冬も、いろいろな作業がある。そうやって、あれこれ考えるだけでも、楽しいのだけれど。
山野を彩る季節の植物たち ~ロウバイ~
ロウバイ(蝋梅)は彩りが少ない冬に、明るい黄色でツヤがある花と、梅の花のような甘い香りで、やがて春が来ることを教えてくれる。花期は最も寒さが厳しい1~2月。名の由来は、「花がろう細工のようだから」とか「朧月(おぼろづき)(旧暦12月)に咲くから」など諸説ある。青空を透かして眺めるのもきれいだが、私は雪がやんだ直後、白い綿帽子をかぶった花を見るのがとっても好き。

執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
ココロ踊る!山麓生活のススメ