
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
土地を入手してから、家づくりに先行して始めた家庭菜園。夏には面積も広がり、オクラのほか、ピーマン、トマトなどの夏野菜、さらに、ジャガ芋、サツマ芋、里芋、カボチャ、大豆など種類もだいぶ増えた。今回は盛夏から収穫までを振り返ってみたいと思う。

大豆の成長を観察する夫とガク
落花生の代わりに植えたオクラ(本記事第6回「家庭菜園1年生 〜落花生の事件簿〜」参照)をはじめ、夏になると野菜たちはぐんぐん成長した。でも、大きくなるのは野菜だけでなく、雑草たちも負けていない。根こそぎ抜いたつもりでも、1週間もするとまた生えてくる。そのうちに引き抜くのが間に合わなくなり、鎌で刈るようにした。今年は長雨で作業ができない日もあって、そんな時には野菜よりも大きく育ち、雑草を栽培しているのか、野菜を作っているのか分からない状態になってしまう。
ガクの離乳食に使おうと6本も植えたカボチャはツルを伸ばして雑草と入り交じり、区別するのも難しくなってしまった。困っていると、ある時、実家の父がエンジン式の刈払機を購入した。「これで、雑草を全部刈ってあげるよ」とパワー全開で、畑周辺の草を生え際からきれいにしてくれた。
見違えるようにスッキリして、夕方、草を片付けていると、カボチャの葉が全部しおれている。朝は元気だったので、水切れではないと思うけれど……とツルをたどっていくと、なんと根元からスッパリと切られていた。父が勢いに任せて雑草を刈るときに、カボチャもいっしょに切ってしまったらしい。コブシぐらいの大きさの実をいくつも付けていたけれど、それでカボチャも全滅……。初めての畑作業では、思いもよらないハプニングが起こるものだ。

作物の間の細かい所は、ひたすら手作業で雑草を引き抜く
それでも他の野菜たちは育ち、7月にジャガ芋を初収穫した。無農薬で栽培しているので虫の食害がひどく期待はしていなかったが、それでも、ソフトボールサイズのジャガ芋をダンボール1箱も採ることができた。8月・9月にはオクラを一生分ぐらい食べたし、数は少なかったものの、新鮮なトマトやピーマンも味わった。
10月になってやっと実を付けた大豆は緑色のうちに採って、エダマメとして楽しんだ。11月には待ちに待ったサツマ芋掘り。手を入れて土の中をまさぐると、1つで2kgほどありそうな巨大なサツマ芋がゴロンと出てきた。そして今は白菜、大根、春菊、ホウレンソウなどの冬野菜が大きくなるのを待っている。
落花生やカボチャのように大失敗したものもあったけれど、初めてにしては十分過ぎる成果である。野菜作りの技術もなく、肥料もそんなにやっていないのによく実ったのは、土がたくさんの栄養をためていたからではないかと思う。そして、改めて日照や降雨など、植物を育む自然の力はすごいものだなと思い知らされた(さすが、日照時間・日本一をうたう北杜市※である)。
※北杜市の紹介(山梨県北杜市移住・定住ポータルサイト「いいじゃん、北杜市。」)
食卓は畑で取れたものが中心になり、夫も「ジャガ芋のホクホク感が違う」とか「エダマメがとっても甘いね」といって、うれしそうに食べていた。焼いただけ、ゆでただけでも特別においしく感じるのは、成長過程を見ながら手をかけてきたからだろう。
おいしい野菜を食べられるのが家庭菜園の醍醐味だけれど、その収穫以上に得られたものがある気がする。それは、週末を菜園で過ごす時間が、私のよい気分転換になったこと。平日は仕事と育児、家事に必死で、気持ちに余裕を持てないときもあった。でも、週末は朝から畑へ行って、外でお弁当を食べ、夕方までたっぷり日差しを浴びて過ごす。そんなシンプルなことが私の気持ちを癒やしてくれた。畑作業が、私にとってこんなにもリフレッシュになるなんて、やってみるまで分からなかったことだ。
ガクも収穫の楽しさを覚えたようで、毎回、畑に着くとトマトやピーマンの所へ一目散に向かい、実に手を伸ばして取ろうとする(青いトマトや親指ほどのピーマンなど、未熟なものもすべて取ってしまったけれど……)。そして、秋には大きな大根やサツマ芋を掘り、運ぶのを手伝おうとしてくれるようになった。そんな様子は公園で遊ぶときよりも楽しそうで、生き生きとした笑顔を見られたことも、思わぬ「収穫」だった。
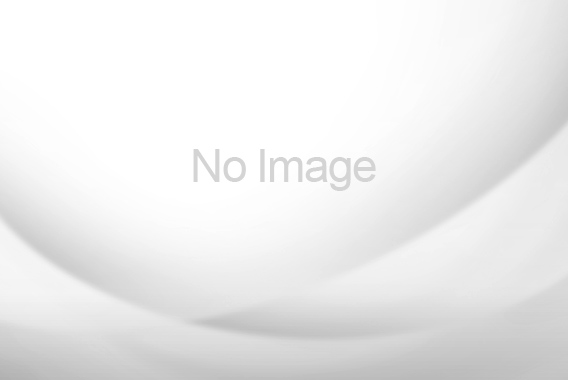
大きな野菜を運んで遊ぶガク
今年、十数種類の野菜を育ててみて、育つスピードや収穫時期など、だいたいの様子がつかめたので、来年はもう少し計画的に栽培してみようと思う。そして除草と防虫・防鳥対策をしっかりして、落花生、カボチャに再チャレンジするのが楽しみだ。
山野を彩る季節の植物たち ~ヒイラギ~
ツンツンと鋭いトゲを持つ葉のヒイラギは、魔よけや厄よけとして庭木に使われる縁起のいい木。漢字では「柊」と書き、10〜12月、冬の訪れを感じる頃に白い花を咲かせる。モクセイ科モクセイ属で、よい香りで知られるキンモクセイの仲間。ヒイラギの花も甘い香りを漂わせる。節分にはヒイラギの枝にイワシの頭を刺した「柊鰯(ひいらぎいわし)」に使われる。クリスマスの飾りにする赤い実がなる植物は「セイヨウヒイラギ」で、名前も、見た目も似ているけれど、モチノキ科モチノキ属のまったく違う木。ヒイラギは黒くて地味な実を付ける。

執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
ココロ踊る!山麓生活のススメ