
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
比較的自然災害が少ないといわれる山梨だけれど、私たちが住む地域は過去に大雨や大雪災害の歴史があり、地震を起こすといわれる活断層も確認されている。また、県の地震被害想定では、南海トラフの東側を震源域とするマグニチュード9クラスの大地震が発生した際、全壊する建物が6万棟以上、避難者14万人以上と見込まれていて、決して安全とはいえない(※)。大きな被害を引き起こした能登半島地震をきっかけに、改めて身の回りの災害対策を考えた。
※参照:山梨県地震被害想定調査結果(2023年5月26日発表)
登山を仕事にしている私の家には山の道具がたくさんあり、その中には災害時に役立つものが多い。例えばテントは、家が使えなくなったときの避難生活場所として使える。登山用テントは立てるのが簡単で、強風・降雪など悪天候にも強いのが利点。オートキャンプ用の大型テントは設営に時間がかかり悪天候には弱いが、居住性に優れる。どちらも足を伸ばして寝られるし、防寒・換気の面でも車中泊より良さそうだ。
また、本格登山で使う大容量のザックは足元が悪い状況でも避難先へ荷物を運ぶのに便利だろう。厚手のビニール袋をザックの内側にセットすれば、給水用ポリタンクの代わりに水を運べる。クッキング用のバーナーやガス、ヘッドランプ、レインウエア、防寒着など、山で使う道具は軽くコンパクトなうえに高機能なので、いざというとき強い味方になるに違いない。実際、私は古くて使わなくなったザックに衛生用品や非常食、飲用水などを入れ、非常時の持ち出し用として玄関に置いている。
自分の家にある他の山道具がいざというとき、本当に使えるのか、改めて考えてみた。まず、ここに引っ越す前のアパートでは、山の道具を玄関近くの部屋にまとめて置いて、普段から運びやすいように工夫していた。でも、今の家は収納の問題から、2階または屋根裏に置いている。これでは災害時に運び出すのが困難だ。
そもそも火災が発生したら、家といっしょに山道具も燃えてしまい、持っていたにもかかわらず使えないことを後悔するだろう。そこで、今は屋外の物置にその一部を移して、家が被災してもある程度使えるようにしようと考えている。また、飲用水、非常食は物置を含めた家の内外の複数箇所に保管することも大事かもしれない。
私の家は、古くからの集落の外れにある。近所は、数世代にわたってこの地に暮らしている人が多いけれど、移住者である私たち家族を寛容に受け入れてくれている。そんな温かな地域に少しでも貢献しようと、草刈りや用水路の手入れ、清掃活動など、春から秋にかけて、ほぼ毎月ある地区の奉仕作業にはできるだけ参加している。最初はそれこそ「奉仕」だと思っていたのだが、地区の人に交じって作業をするうちに、家族の安全につながるメリットがあることに気づいた。
例えば、用水路の手入れ。この作業に参加したことで、用水路がどんな造りになっていて、どこに危険が潜んでいるかを考えるきっかけとなった。そして、子どもにも、そうした危険な場所には近づかないように言い聞かせている。
また、昨年秋に家族で参加した地域の消火訓練。消防車が到着するまでの間、住民による初期消火として、実際に消火栓にホースをセットし、放水するまでの流れを消防団員から教えてもらったのだが、そのときに初めて気づいたことがある。それは、集落内の他の家に比べて、私の家が消火栓から離れた場所にあること。消火栓から水を引く場合は何本もホースをつなぐ必要があり、初期消火が困難ということが分かった。それが、自前で消火器を用意して、火が大きくなる前に消火しようという防災の発想につながった。
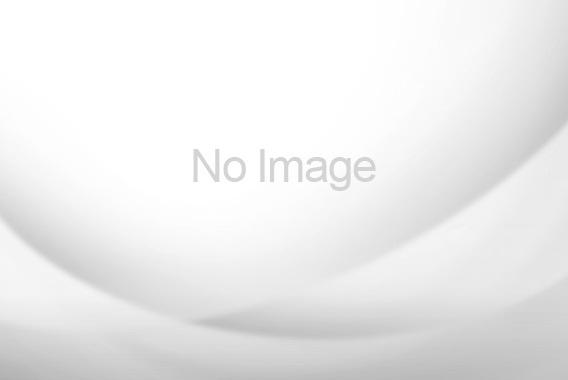
年に一度、地域で行われる初期消火訓練
能登半島地震の報道を見て重要だと感じたのが、地域の人たちとの助け合いだ。情報や交通が遮断される災害発生直後は特に被災者同士の協力が欠かせない。私たち家族は、近所の人たちとの関係は良好だけれど、周りはすべて親戚という人たちに比べると、つながりが強いとまでは言えない。災害で厳しい状況に陥ったときでも孤立しないように、日ごろから周囲の人たちとのコミュニケーションを深めておくことが大事だと感じている。
コロナ禍以降、住民が集まる例会はなくなり、地域の運動会やお祭りはかなり縮小された今ではあるけれど、地域の行事にはなるべく積極的に参加して、防災・減災の面でも地域に溶け込んでいこうと考えている。
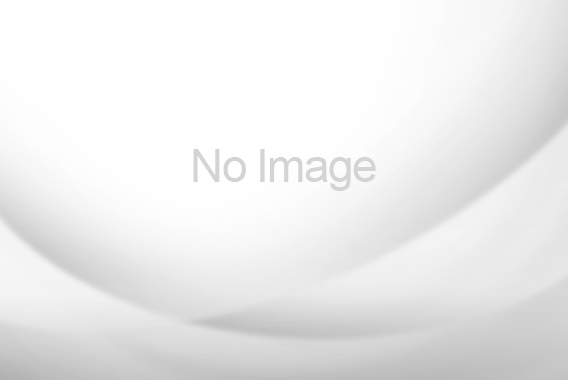
私が住む地域は山麓に集落が点在している
山野を彩る季節の植物たち ~マンサク~
まだ寒さが残り、木の芽も硬い2月下旬、先駆けて春の訪れを知らせてくれるのがマンサクの花。黄色の紙を細くちぎって付けたような花びらが面白くて、地味ながらも興味を引く。山梨では他の木に交じって生えているのをちらほらと見かける程度だけれど、九州の山では群生しているところもあって、咲きそろうと山が黄色く染まって見えるほど。「まず咲く」が転じたという名前は覚えやすい。

明るい黄色の細長い花びらがユニーク
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
ココロ踊る!山麓生活のススメ