
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
家庭菜園を始めたら、育ててみたかったのが落花生。花が咲いた後に子房が土に潜って実ができるという生態がちょっと変わっている。秋にはいっぱい収穫して、香ばしく、食感もいい落花生をビールのおつまみにするのが楽しみだけれど、栽培はそんなに甘くはないようで……。

秋にたくさん収穫しようと心待ちに落花生を育てる(写真はイメージです)
畑の一区画すべてを落花生にしようと、少し欲張って種の小袋2つ分(約40粒)の種を育苗ポットに植える。畑に直接まけるのだが、発芽の様子も毎日観察したかったので、苗をベランダで育てることにした。落花生の種として売られているのは、ピーナツとして食べる部分。薄皮が付き、乾燥して少しシワシワしている種に土が2〜3㎝かかるように植え、水をたっぷりやって発芽を待つ。
植えてからは毎朝、芽が出るのは今日かな、明日かなと見守るのが楽しい。水が切れないように、土の表面が乾いたら水やりをしながら10日ほど過ぎた。でも、芽が出る気配はまったくない。
2週間たっても変化がないので、芽が出る前に水のやり過ぎで腐ってしまったのでは?と心配になり、割り箸の先で種を植えた辺りをそっと掘り返してみた。すると土の中から、白くて太い根が出始めた種がコロンと出てきた。これは発芽の邪魔をしてしまった!と、慌てて埋め戻す。それから数日して、あちこちのポットから芽が顔を出し始めた。水を吸って一回り大きくなったピーナツ自体がそのまま双葉になり、その間から緑色の本葉が顔をのぞかせていてかわいい。
芽が出てから1週間もすると、丸い本葉がしっかりと開き始めた。いくつかの種は不発だったけれど、それでも30数本の元気な苗が育った。
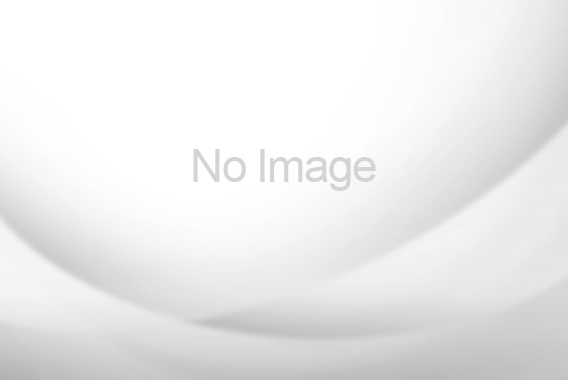
種をまいてから20日ほどかかってやっと芽を出した
種を植えてから約1カ月半、本葉が3、4枚になった頃、いよいよ畑に定植する。よく耕して、土をフカフカにした畑の1列に約10本、それを3列植えた。見渡してみると、家庭菜園というよりは、ちょっとした農園のようでうれしい。
定植した翌週に行ってみると、苗はしっかりと根付いて、どれも一回り大きくなっている。ここまで育てばひと安心。秋には1株から30個ぐらいの落花生が収穫できるらしく、30株あればかなりの量が収穫できそうだ。掘ったばかりの落花生を塩ゆでにして、ビールのおつまみにしたらどんなにおいしいだろう。よく乾燥させて保存し、冬はストーブに当たりながら、ポリポリと香ばしい煎り落花生を食べるのもいい。バターピーナッツにしたり、ハチミツ漬けで保存したりするのもいいかもと、想像するだけで楽しくなる。
ところがその次の週末、畑へ行ってあぜんとした。さらに成長しているに違いないと思っていた落花生だが、植えたはずの区画に苗が1本もないのだ。
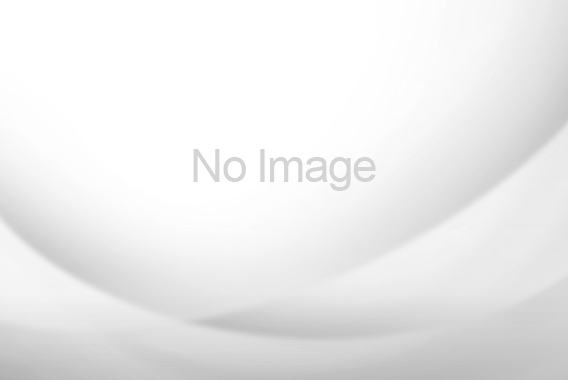
ロープを張って列が真っすぐになるよう、ていねいに苗を植えた
あまりに予想外で信じられず、目をこすって、もう一度辺りを見回してみる。やっぱりない。雨は降ったから水切れではないはず。元気だった苗はどこへ行ってしまったのかと、しゃがんで植えた場所をよく見ると、干し草のように干からびて茶色くなった苗を見つけた。根っこからきれいに引き抜かれ、茶色くカリカリに乾いていた。
どうしてこんなことになってしまったのだろうと、しばらく考えて思いついた。犯人はきっと鳥だ。干からびた落花生を見ると、双葉(豆の部分)だけがきれいになくなっていて、根や葉は残っている。きっとハトかカラスがやってきて、苗の豆の部分だけをついばんで、残りはポイッと捨てたのだろう。水を吸ってふくらんだ豆は、とてもおいしかったに違いない。30本もあった苗が1本残らず食べられてしまったのだから。
鳥が畑をヨチヨチと歩き、律義に苗を1本ずつ引き抜いては、豆を取って食べる姿を想像すると、おかしいやら、悔しいやら。鳥に食べられる可能性は定植するときに頭にあって、豆の部分は土から出ないように隠して植えたのに、それでもおいしい豆があると気付いた鳥の感性には脱帽するしかない。楽しみにしていた塩ゆでもバターピーナッツも幻となってしまった。家庭菜園といえども、自然相手に作物を栽培する大変さを早くも体感させられた。
それでもめげない私は、落花生の跡地に、やはり種から育てたオクラを約30本植え、今、収穫を楽しんでいる。オクラの天ぷら、オクラの煮浸し、オクラの浅漬け、オクラの味噌汁、オクラのごまあえ……。数を植え過ぎたうえ、今度は予想外に順調に育ち、食べきれないほどに収穫できる。毎日、オクラを使ったメニューを考えるのに必死だ。
山野を彩る季節の植物たち ~ヒガンバナ~
美しくも、どこか心をザワつかせる深紅の花を付けるヒガンバナ。秋の彼岸頃、川の土手や田んぼのあぜなどで一斉に花を咲かせる。地中にタマネギに似た形の鱗茎(りんけい)(球根)を持ち、毒があるが、昔はデンプンの毒抜きをして飢饉(ききん)のときの食用にしたのだとか。そんな理由で田畑の周りにたくさん植えられた。根の毒はネズミやモグラを作物に近づけないともいわれている。身近で目立つ花だからか、曼珠沙華(まんじゅしゃげ)、お盆花、狐の花火と、別名も多い。花と葉が同時に見られないため「花知らず葉知らず」と呼ぶ地域もある。
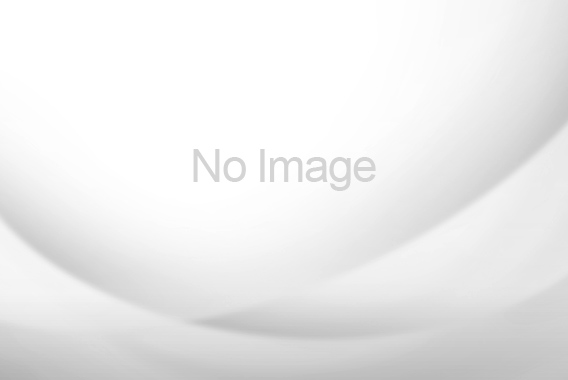
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
ココロ踊る!山麓生活のススメ