
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
家づくりについて、2カ月以上かけて工務店と詳細な打ち合わせを重ねて、やっと正式な設計図が完成し、着工へとこぎ着けた私たち。地鎮祭を行い、地盤調査(その土地が建物の重さに耐えられるかの調査)も問題なくクリア。いよいよ、基礎工事を始める段階になったが、その前にもう1つ必要な調査があった。それは、埋蔵文化財の照会。この土地は遺跡の上にあるかもしれず、工事前に発掘調査が行われることとなった。実際に、近くでは遺跡も発掘されている。さて、私たちの土地に、遺跡は眠っているのだろうか。
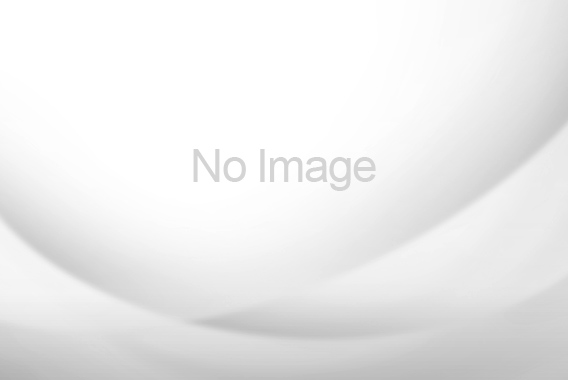
北杜市大泉にある金生遺跡。縄文時代の住居跡などが復元されている
北杜市には知られているだけで1000カ所もの遺跡(埋蔵文化財包蔵地)があるという。中でも有名なのが国指定史跡の金生遺跡(きんせいいせき)。そこでは縄文時代の住居跡や、祭祀(さいし)が行われた場所が見つかり、土器や石器のほか、装飾品も発見された。北杜市には、今も地中に埋もれたまま、調査されていない遺跡があるそう。
私たちが購入した土地は埋蔵文化財包蔵地の範囲に該当していて、新規に住宅建設などの土木工事を行う場合は発掘調査が必要になる。どのような内容なのか、数年前に調査を済ませたという隣家のおじさんに話を聞いてみた。すると、家屋の角を指さしながら「ウチはここから大昔の住居跡が出ました。調査員が来て、深さ50㎝以上掘っていましたよ。この辺り一体に集落があったというから、お宅もきっと何か出ますよ」とニコニコ笑いながら話してくれた。もし、今の仕事に就いていなかったら、発掘調査の仕事をしたいと思っていたほど遺跡や古代史に興味がある私は、とてもわくわくしてきた。
「もし、この土地から国宝級のお宝が出てきたら、億万長者になれるのかな。山梨には武田信玄の埋蔵金伝説もあることだし」と私が言うと、夫は「そんなのあるわけがないでしょう。第一、この辺りはもっと古い時代の遺跡じゃないの?」と至って現実路線。それでも、大きな縄文土器とか、ヒスイの首飾りとか、重要な物が発掘されるかもしれないと思うと歴史ロマンに期待が膨らんでしまう。一方で、不安もチラリと脳裏に浮かぶ。お宝が出たら、古代人が埋葬されている可能性もゼロではないな……。何が出るのか、はたまた何も出ないのか。実際に掘ってみるまでは誰にも分からないだけに、宝くじを買ったときのようにドキドキする。
調査当日、私は興味津々で調査に立ち会うことにした。まずは重機で地表から50㎝ぐらいの表土を取り除いていく。すると早速、「何かありそうだね」と重機を止めて手作業に切り替える調査員たち。「出ましたか?!」と駆け寄ると「私たちは主に土の硬さや色の違いで遺跡の有無を調べています。ここは、周りに比べて土の色が濃いでしょう。この地域では黒っぽい色の層から遺跡が発掘される場合が多いのですよ」と教えてくれた。
やがて教育委員会の方も加わり、打ち合わせが行われた結果、後日、改めて本格的な調査をすることになった。
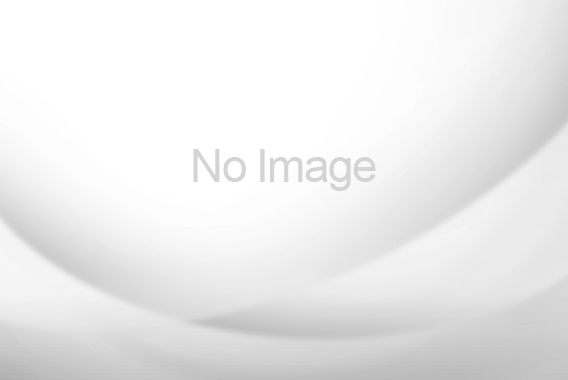
夏の炎天下で行われた調査。遺跡がある可能性が高くなってきた
その後はすべて手作業で発掘調査が行われた。炎天下、数名の調査員が地面にしゃがみ込み、移植ゴテや木のヘラなどでひたすら土を掘る仕事は見るからに重労働で頭が下がる。
一週間ほどして調査終了の連絡が入った。埋め戻される前に急いで見学に行くと、写真などで見たことがある、いかにも遺跡らしい凹凸がある。「これは何ですか?」と聞くと「詳しい調査をしないと分からないのですが、今までの調査から推測すると、平安時代初期の住居跡だと思います。柱やかまど跡のほか、数個の土器も出土しました」とのこと。
平安時代といえば源氏物語や枕草子などが執筆された時代。貴族たちが栄華に満ちた生活を送っていたイメージがある。しかし、目にした住居跡は、それとはかけ離れていて、6畳の広さがあるかどうかという小ささ。しかも、家とは思えないほどの簡素さだった。それについて尋ねると「平安時代とはいっても、地方の庶民は縄文時代とほとんど変わらない生活をしていて、住居も竪穴式のとても簡素なものだったんですよ」と教えてくれた。いくら庶民とはいえ、平安時代なら木造の家に住んでいただろうと思っていただけに、貴族の生活との違いが衝撃だった。
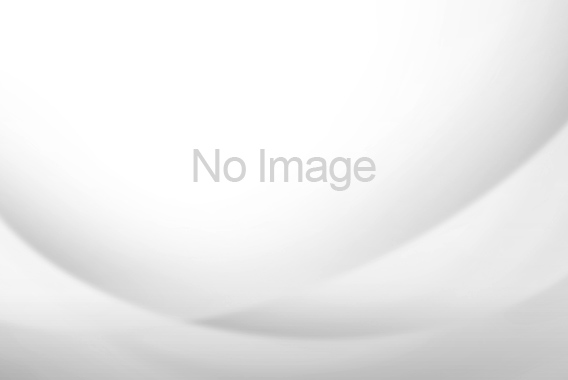
平安時代初期と考えられる住居のかまど跡。敷地の南西側から発掘された
調査員によると、この辺りは平安時代初期に鍛冶工房を中心とした集落があったと分かっているので、たぶんそれに関係する人の家ではないかという。しかし、ここに暮らしていたのは30年から長くても50年ほどで、その後はどこかへ引っ越していったそう。当時の人にとって、八ヶ岳山麓の気候は生活するのに厳し過ぎたのではないかという見立てだった。
ということで、わが家の遺跡は「世紀の大発見」ではなかったけれど、1000年も前に同じ場所を選んで暮らしていたのはどんな家族だったのだろうと、想像すると楽しかった。日々の生活の合間に、八ヶ岳や南アルプスの山々を眺めては、私と同じように、きれいだなと思っただろうか。
興味ついでに、どうして北杜市に遺跡が多いのか聞いてみたところ、この地域だから特別に遺跡が多いわけではないそう。全国のいろいろなところに古代からの遺跡があったはずだが、詳細な調査が行われないままに、消えてしまったところも多いのだとか。この地域は山あいで、大規模な開発が行われなかったために、今でも残っているそうだ。
遺跡は一度壊してしまったら、もう二度と元には戻らない。だから、地道に調査・研究をして、歴史を後世に伝えていくことが大切なのだと話してくれた。私たちも調査をしてもらったおかげで、家を建てる土地の歴史を知れてよかったと思った。調査後に遺跡は埋め戻されて、無事に家の基礎工事が始まった。
ちなみに後日、市へ提出した書類をよく確認したら「(土地の所有者は)埋蔵物についての権利を放棄します」という一文があった。もし、金銀財宝が発掘されたとしても、どうやら私たちのものにはならなかったらしい。
山野を彩る季節の植物たち ~リンドウ~
野の花がめっきり少なくなる晩秋。そんな時期、枯れ草の中で目を引くのがリンドウの花。秋の花の代表だが、霜で周りが真っ白になる頃になっても見掛けるときがあって、花の強さに感動する。花が開くのは晴天時だけ。つぼみはソフトクリームのように花弁がねじれていて、その姿もかわいらしい。
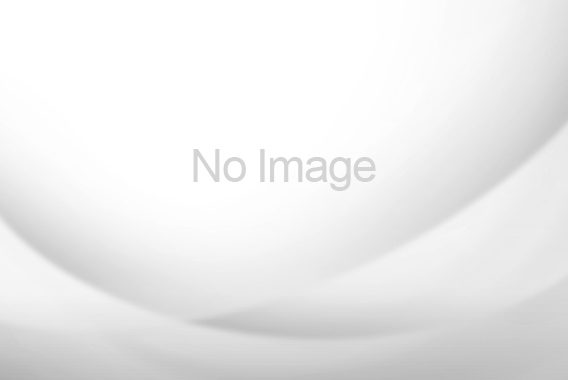
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
ココロ踊る!山麓生活のススメ