
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
朝起きたら、庭の小さな菜園へ行って野菜を収穫。そして色とりどりのシャキシャキ野菜を使って食事の準備をする……。土いじりをして、自然の恵みを感じられる暮らしに憧れている私。その1つとして家庭菜園をするのが、長年の夢だった。手に入れた山麓の土地で、まずやってみたかったのが畑作り。ちょうど季節は春。野菜の栽培を始めるのにピッタリの時季だ。
とはいっても、数年前にベランダでミニトマトやキュウリをプランター栽培したことがあるくらいで、畑作業の経験や知識はほぼナシ。まずは書店で「家庭菜園の始め方」といった、初心者向けの本を数冊買って、勉強するところからスタートした。いずれは、旬の野菜はスーパーで買わずに、自分で育てたもので賄いたいと思っている。地産地消よりもっとコンパクトに、自分で作って自分で食べる「自産自食」が目標だけれど、さて、うまくいくだろうか。
家庭菜園を始めるにも、道具がなくては何もできない。今、家にあるのは、プランター栽培をするときに買った小さなシャベルが1つだけ。書店の次は、ホームセンターへ行って、スコップと三本鍬(くわ)を買ってみた。これで野原を耕して、畑のスペースを作ろうと思う。
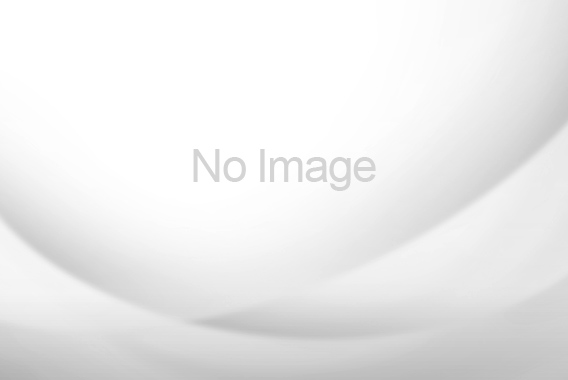
自宅で採れた野菜を使って料理をするのが夢(写真はイメージです)
作業の日は両親も手伝いに駆けつけてくれた。購入した土地の南側を畑に使うことに決めて、くわを振り下ろす。以前、畑として使われていたからか、もともとそのような地質なのか、30cmほど掘っても小石ひとつ交じっていない。畑にピッタリの土だと思った。
だけど、くわが気持ちよく入るかといえば大違いだった。芝やササ、ススキなどが広く根を伸ばしていて、それを取り除くのに思いのほか苦労する。特にササは、地中深くで固い根がつながっている。スコップで土を掘り起こし、根を切る作業がキツイ。ススキも難敵で、根が深く張っていて、スコップすら刺さらない。そこでくわの刃を振り入れてテコの原理を使い、力ずくで引き抜こうとしたら、買ったばかりのくわの刃があっさりと曲がってしまった。トホホ……。

肌寒いくらいの気候なのに、夢中で作業するうちに大汗をかき、気付いたら手にはマメができていた。大人4人が交代で休みながら作業して、2×4mほどの区画を耕すのに丸1日を費やした。私が抱く、のどかな家庭菜園のイメージからは遠く、重労働の開墾そのものだ。でも、できたばかりの小さな畑にジャガイモを植えると、夢のかけらを手に入れた気がして、充実感に満たされた。
ほかにも何種類か植えてみたかった私が「もう少し畑を広げたいな」と言ったら、「これ以上は、手作業では無理がある」と言って、父が翌週、実家で使っている耕運機を持ってきてくれた。家庭菜園用の超小型耕運機だけれど、機械の力は絶大で、あっという間に3倍ほどの広さの畑ができた。先週、あんなに苦労して耕したのは何だったのだろう。これなら、始めから耕運機を借りればよかった。でも、手にマメを作って耕す体験も大事だったと思いたい。
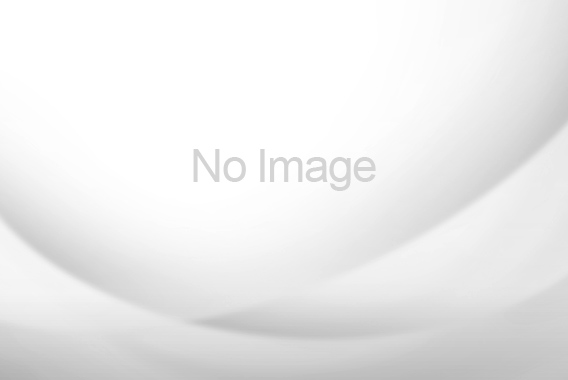
余裕の表情で耕運機を使い、畑を広げていく夫
さて、ここには何を植えようかと、家庭菜園の本を見ながら考える。週末しか手入れができないうえ、水道がないので水やりもできない。そこでサツマイモ、オクラなど、植えた後にあまり手がかからない野菜を選ぶことにした。
本に紹介されている作物の中で、特に興味を感じた落花生栽培にも挑戦したい。落花生は、花が終わると子房が伸びて土に潜り、その先に豆ができるという。その不思議な生態を観察してみたかったし、何より自分で作った豆を食べてみたかった。落花生栽培……それが、予想外の展開となる。(つづく)
山野を彩る季節の植物たち 〜マツムシソウ〜
青紫色が涼しげなマツムシソウ。小さなたくさんの花が集まって、1つの花のような形を作っている(頭花)。花名の由来はマツムシが鳴く頃に咲くからといわれている。マツムシソウは2段階で咲くのが面白い。小さな花のそれぞれから、まず出てくるのは雄しべで、そこから花粉を出す(写真左手前の花)。すべての花粉を出すと雄しべはきれいに落ちて、次に白い雌しべが伸びてくる(写真右奥の花)。雄しべ、雌しべを時間差で出すのは、他の花の花粉をもらって受粉する工夫だといわれている。
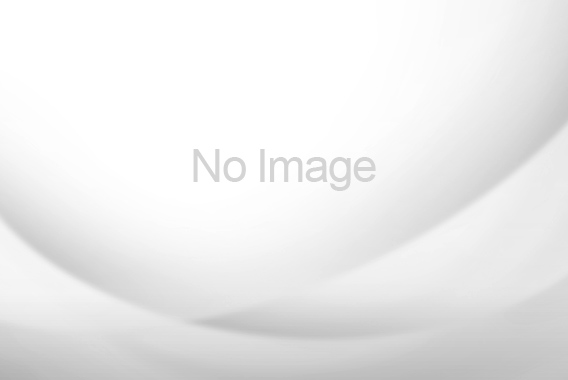
執筆=小林 千穂
山岳ライター・編集者。山好きの父の影響で、子どもの頃に山登りをはじめ、里山歩きから海外遠征まで幅広く登山を楽しむ。山小屋従業員、山岳写真家のアシスタントを経て、フリーのライター・編集者として活動。『山と溪谷』など登山専門誌に多数寄稿するほか、『女子の山登り入門』(学研パブリッシング)、『DVD登山ガイド穂高』(山と溪谷社)などの著書がある。現在は山梨で子育てに奮闘中。
【T】
ココロ踊る!山麓生活のススメ