
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
金子コード(ケーブル・医療用チューブの製造販売、食品の生産販売)
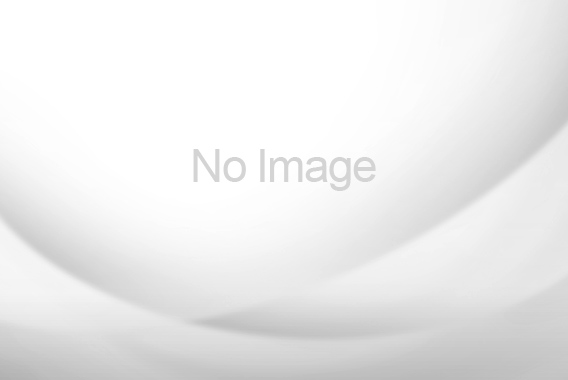
金子智樹社長
事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第18回は、前回に引き続き、電話コードなどの各種ケーブルや医療用カテーテルを製造販売する金子コードのケース。電話コードの需要が激減し事業承継どころでなくなった金子コード。後編では、そのピンチをどうやって脱却したのか、そして、無事に承継を果たした金子社長は、その経験をどう生かし、さらに後継者に会社をどう引き継ごうとしているのかを紹介する。
2003年に予定していた承継を延期し、親子で経営再建に奔走した。従業員のリストラという苦渋の選択をしたものの、それでも状況は厳しいまま。あわや倒産か――。そんな場面で救いの一手となったのが、10年前からじっくり育ててきた医療部門だった。この年、カテーテルの生産販売事業が初めて黒字化しており、その可能性を評価した金融機関から融資が下りたのだ。
「一般社員として働いていた頃、医療に進出しようとする社長の方針に文句を言う社員の声をよく耳にした。大量のお金と時間をかけて社長の道楽に付き合わされてたまらない、と。しかし、もし、あのとき医療に進出していなければ、今金子コードは存在しなかったかもしれない。この時、経営者として長期的視点を持つことの大切さと、新規事業に取り組むことの必要性が身に染みた」と金子社長は厳しい顔で振り返る。
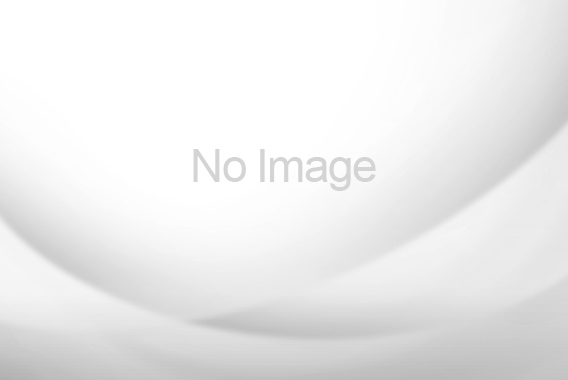
2代目社長である父・金子正一氏は電話コードの技術を生かしてカテーテルの製造を始めた。軌道に乗るまで10年もの期間を要したが、現在、同社の売り上げの70%以上を支えている
最悪の時期を脱した2005年、金子社長は38歳で3代目社長に就任した。「社長になるに当たって、父からはいろいろなアドバイスをもらったが、特に印象に残っているのは、人の問題。これから先、誰をサポートに付け社長業をするのかをしっかり考えろと言われ、社長になるまでの期間に人事戦略を考えることができた」と金子社長は語る。
金子社長は、就任に当たり「大きな方針転換はしない」と決めていた。「社長が代わることで、少なからず社員の中には不安を感じる人もいた。最初の社員たちへのあいさつで、大きな方針転換はしない、と伝えた。なぜなら、就任前から私は常務・専務として先代と一緒に経営に携わっていた。社長になったからと急に変えるのは、それまで自分がやってきたことまでも否定することになるからだ」(金子社長)
さらに、金子社長は社長を務める期間を3つのステージに区切ることを考えた。
「仮に、父が承継を予定していた65歳まで社長を続けるとしたら、ちょうど金子コードは100周年を迎える。そうすると、社長を務めるのは27年間となる。ただ、27年は1つのことを取り組むには長過ぎるため、9年で区切り、3つのステージごとに目標を立てて取り組むことにした」という。2012年までの第1ステージで取り組んだのは、人材育成や財務強化など会社の基盤づくり。そして現在は第2ステージで「生み出せ、育てよ、NO.1になれ!」をテーマに新規事業に挑んでいる。
「電話コードの技術をカテーテルに生かすなど、1から10の事業をつくることはできた。ただ、過去の成功体験を踏襲すると、必ず失敗する。既存事業ももちろん進化させていくが、これからは0から1をつくることも必要な時代。そこで今、NO.1になれる新たな新規事業に挑戦している」(金子社長)
新規事業を考えるうえで金子社長が求めたことは2つ。1つは、10年くらいじっくり時間をかけて育てることが必要だが、その先の成長が期待できる事業。これは、大企業の社長の任期が平均6年なので、中小企業である金子コードはそれ以上の時間をかけてじっくり取り組むことで、大企業が参入できないような事業をつくることを狙った戦略だ。もう1つは、既存事業の延長線上にないということ。そうでなければ、リスクヘッジになりにくく、視野も広がらないからだ。
この2つの条件を満たす事業分野として、東南アジア市場などを模索する中で見つけたのが「食」だった。人が生きるうえで欠かせない重要なテーマの「食」を扱い、必要とされる会社になりたいと考えた。すでに2015年に食品部を立ち上げている。最初の事業として育てているのが、チョウザメの卵、キャビアの養殖だ。
「卵が育つのに7~8年かかるため参入障壁が高い。さらにキャビアのような高級食材は値崩れを起こしにくい。食の事業というだけでなく、富裕層ビジネスと陸上養殖の側面があり、これまでとはまったく違う人脈が広がっている」と説明する金子社長。今はまだ少量しか生産できないが、すでに飲食店からの引き合いが増えているという。3年後には量産が可能で、業績に寄与する見込みだという。
ただし、立ち上げたのはキャビア部ではなく食品部。キャビアの生産が軌道に乗れば、他の食品にも展開する予定だ。海産資源は減少を続けている。陸上養殖の技術をより多くの魚に生かすことができれば、この先の食卓の魚を守ることにもつながると考えている。新規事業を考えるときは社会貢献の意味合いも忘れないようにしている。
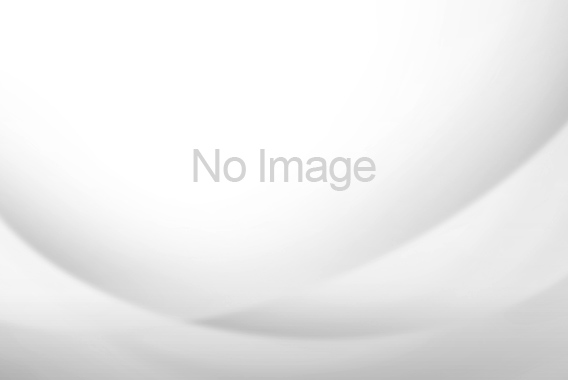
新規事業として食品部を立ち上げ、キャビアの生産事業に進出。3年後には安定して量産できる体制が整う予定だ
「海外や医療分野の新規事業の立ち上げに関わってきた社員が今、リーダーになっており、彼らが今度は若手社員に新規事業のノウハウを伝授している。医療分野進出のときに社内で反発があったことを踏まえ、新規事業に社員が納得して取り組める風土づくりも意識している。最近、新型コロナウイルスの感染拡大により中小企業は苦境に立たされているが、チャンスの時代ともいえる。昔は新商品、新事業の開発レベルの取り組みしかできなかったかもしれないが、今後は、オープンイノベーションや共創といった概念を持つことで新産業の創出も可能だ」(金子社長)
こうした新規事業への挑戦は、事業承継においても大きな意味を持つと金子社長は話す。
「親の会社を継ぎたがらない人が多いのは残念だと思っている。その理由の1つに、父の事業が自分のやりたいことではないから、という意見をよく聞くが、それならやりたい事業を自分でつくればいい。私も最初から電話コードが好きだったわけではない。親の会社を引き継いで新規事業を起こす場合、既存の資産や人脈を使えるので、ゼロからスタートするより成功の確率は高まるはず。この恵まれている環境を生かさない手はない。迷わず継いでもらいたい」
しかし、一方では「受け身で承継すると失敗するだろう」ともアドバイスする。「事業承継の主役は現役社長だと思われがちだが、実際の主役は引き継ぐ子どもの側だ。親はまだまだ譲ってくれそうにない……と待っているのではなく、自分の人生なので、いつ社長になるかは自分で決めるべき。3年後に社長をやりたいから譲ってくれと自分で言うくらいでなければうまくいかない」と、金子社長は後継者に覚悟を求めた。
後継者がそうした覚悟を見せれば、継がせる側もそれに応えてほしいとも話す。「かじ取りが2人いると会社はうまくいかないので、息子が覚悟を決めたのであれば、親はその思いを尊重して譲ってあげてほしい。私自身がこのように考えられるのは、父が自分を尊重し任せてくれたからだ。そのことに感謝している」
現在、金子コードのグループ連結売り上げは47億円(海外法人は除く)。そのうち75%が、父が会社の生き残りを賭けて始めた医療事業だ。「この先、どんな苦境が訪れても、事業構造を柔軟に変えながら、永続的に成長できるような企業にしていきたい」と熱意を燃やす金子社長は、自ら新規事業に挑戦し、社会に貢献できる会社に育てていきたいと考えている。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際