
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
ナベル(鶏卵の自動選別包装装置の製造・販売)
事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第26回、第27回は、鶏卵の自動選別包装機を製造するナベル(京都市)。一度は次男の隆彦氏に事業承継したが、南部会長はちゃぶ台返しをしたという。曲折を経て現在の形となった中で見えてきた創業社長ならではの苦悩と工夫を紹介する。
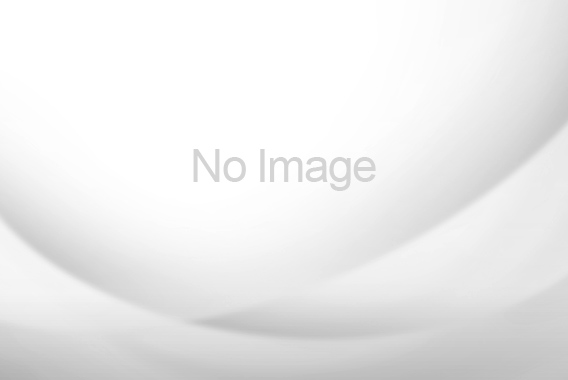
南部邦男(なんぶ・くにお)
1948年生まれ。高校1年生の時、父親が経営する“町の電気屋”が倒産。父と共に電気機器の制御盤の組み立てを行い、生計を立てる。働きながら立命館大学2部文学部を卒業。77年、南部電機製作所(87年にナベルに社名変更)を設立。卵の選別包装機の市場で、国内シェア80%以上、世界シェア第2位の企業に成長させた。2018年に長男の邦彦氏に事業承継し、現在は同社の取締役会長を務める。
なぜ、次男への事業承継がうまくいかなかったのか。南部会長は次のように振り返る。
「ニホンザルのボスザルの交代は、ボスが後継者を指名するのではなく、若くて血気盛んなサルが、弱ってきた先代を追い出すんです。そういう意味で、先代ボスザルである私が、若きボスザルを横暴だと見て、ちゃぶ台返しをした、ということです。次男に対して、決定的に何か気に入らないポイントがあったわけではありません。先代のボスザルのほうが、まだ心技体共に元気で、承継する準備ができていなかったのです」
70歳を過ぎてもなお、第一線にいたいと思うのは、南部会長が創業社長だからという理由のほかに、南部会長の労働観、人生観も影響している。
「ドイツの哲学者・カントは言いました。『もっとも平安な、そして純粋な喜びの一つは、労働をした後の休息である』と。しかし、残念ながら、私はそうは思えないんです。私なら、こう言うでしょう。『もっとも平安な、そして純粋な喜びの喜びは、労働の中にこそある』と。男たるもの、畳の上で死ねると思うな、最後まで世のため人のために働いてこそだという思いがあります。当時は、事業承継を人生の引退と思っていました。今ならそれは違うと分かります」(南部会長)
続けてこう語る。
「この会社を創業し、育ててきた私は絶対的な存在で、いつ、どんな判断も自分で引っ繰り返せると思っていました。それがそもそもの間違いです。ただ、間違いではあるものの、引っ繰り返すことはできてしまう。そこが最大の矛盾ですよね。本人はそれを矛盾だと自覚していない。周囲から見ると、とんでもない裸の王様です。その王様がなまじ実力を持っているから困ったものなんです」(南部会長)
失敗からの学びと反省の思いを語る南部会長だが、次男の跡を継いで社長に就任した長男の邦彦氏のことはどのように見ているのだろうか。
「日々、ガマンの連続ですよ。ただ、ハッキリしているのは、二度と私のほうから社長を変更することはしない、ということです。邦彦は分かっていないかもしれませんが、私にはもう、ちゃぶ台返しという手段はないんです。もうやってられない、社長なんかやめてやる!というちゃぶ台返しをするカードを持っているのは、今は邦彦のほうなんです」(南部会長)
事業承継は、自転車の運転のようなものと南部会長は語る。
「最初は補助輪をつけ、それを外したら、親が荷台を持ちながら練習します。持ってるよ、持ってるよと言いながら、徐々に手を放すわけですよね。小さなケガで済むなら転ぶ経験も必要です。いつまでも手を離さなかったり、子どもが一生懸命運転しているのに、荷台から無理やり進行方向を左に曲げたり右に曲げたりするのは、親子両方に大きなストレスになります。そのためには、見ざる、聞かざる、言わざる、に徹することです」(南部会長)
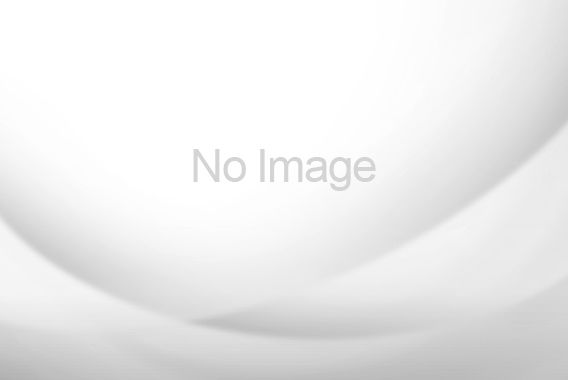
ナベルの鶏卵選別包装機は世界70カ国以上に輸出されている。写真はマレーシア法人「ナベルアジア」の社員たちの集合写真。南部会長が自ら創業し、大事に育ててきた会社だからこそ、事業承継には覚悟が必要だった
しかし、16歳から約55年商売をやってきたこともあり、経験値は豊富だ。
「経験から、危ない場所が分かるんですよね。あかんあかん、そっちに行ったらデコボコの道があると、どうしても口を出したくなってしまうんです。私が邦彦に『もうおまえに任せてるんやから』と言ったら、『お父さん、それ今年になってからもう100回以上聞いてますけど』と言われました(苦笑)。事実、任せ切れていないんですよね。
これまでは役員会議にも出席していましたが、そろそろ手を放す時期だろうと思っています。ただ、無条件で手を放すのはよくない。例えば、2期連続赤字を出したら、あるいは、キャッシュフローがいくらまで下がったら辞表を出しなさいなど、何らかの約束はしたいと思っています。私の心身の健康のためにも」(南部会長)
曲折を経験した南部会長だからこそ言える、事業承継のアドバイスを聞いた。うまくいく秘訣は「目に見える問題と、目に見えない問題に分けて考えること」だという。
「もちろん業種・業態によって違いはあるという前提で、まず目に見える問題、すなわち、退任後の地位や役割、退職金や処遇については、先代から提示するべきであろうと思います。議論の余地はあるとは思いますが、この段階ではおそらく、先代の言い分はすべて通るでしょう。
ここで、受け継がれる側は、どんな条件の下で自分が社長になるのかがハッキリします。先代の退任後の役割によっては、実質的には今までと変わらない場合もあります。同じように考えないといけないな、と覚悟をするべきです。いずれボスザルは弱っていきますから、それまでぐっとガマンです。ここをうやむやにして、明日から社長をやれ、などの一言で交代をするから、トラブルが起こるんです」(南部会長)
一方で、目に見えない問題については、受け継がれる側、つまり子どもが表していくべきだと話す。
「それはすなわち、会社をつくった先代に対する尊敬の念を表すような行動や言動です。社員の前で先代への敬意を態度で表すのもいいでしょう。その思いを出さずに、自分が会社を作ったような顔をして社長になると、これもまたトラブルの種になります。特に、中堅・中小企業の息子は高学歴です。経営学などを学んでいたらなおさら、絶対的な自信を持って会社に入ってきます。でも、経営学はあくまでも学問であり、実際の経営とは違います。承継のスタート地点において、目に見える問題と目に見えない問題をこのようにハッキリさせておくことで、承継で起こるかなりのトラブルを防ぐことができると私は考えます」(南部会長)
一度は会社を離れた次男の隆彦氏も今は復帰し、開発担当の取締役をしている。

南部会長と現社長を務める長男の邦彦氏(右)。「親の期待通りに経営する必要はない。息子らしい会社にしていってほしい」と南部会長はエールを送る
「兄弟で経営をするのは難しいことだと思います。今は私という共通の敵がいるから関係性は良好ですが、私が会社から離れた後も、仲良くやってほしい。私がやってきた55年間の常識と、2021年の常識は違うこともあるでしょう。私の期待通りに経営をする必要はありません。息子らしい会社にしていけばいいと思います。だから、私から息子に何か言うとしたら、『まぁ、頑張れよ』の一言です」(南部会長)
鶏卵業界は今、鶏インフルエンザなど、さまざまな課題を抱えている。若き日々に、自分たちを支え、応援してくれた恩を、南部会長は忘れていない。「養鶏業界の工務部門として会社を育ててきた。今後は業界のためにできる恩返しの道を探りたい」と考えている。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際