
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
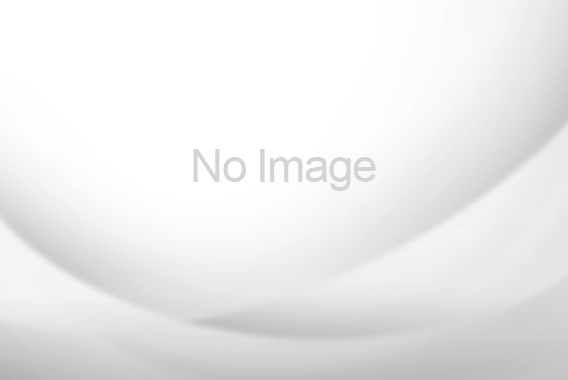
中井政嗣(なかい・まさつぐ)
1945年、奈良県出身。1973年、お好み焼き専門店「千房」を開店。2018年に三男の貫二氏に事業承継し、代表取締役会長となる
千房(お好み焼きチェーンの運営)
事業承継のヒントを紹介する連載の第45回は、大阪市浪速区に本社を構える、お好み焼きチェーン「千房」の創業者、中井政嗣氏。高級路線に踏み切った「ぷれじでんと千房」や「千房エレガンス」など新業態も次々に展開し、現在、全国に72店舗を運営する。3人の息子に恵まれた中井会長は、2018年に三男の中井貫二氏に事業を承継した。
中井政嗣会長は、1945年、奈良県の農家の子どもとして生まれた。きょうだいは7人。家が貧しく、中学を卒業した後、兵庫県尼崎市の乾物屋にでっち奉公に出た。5年間働いた後、姉の夫が経営する洋食レストランでコックの修業を開始する。しかしあるとき、義兄から「後継者を探しているお好み焼き屋があるので、そこを継いで独立しろ」と勧められた。

現在も大阪千日前にある千房千日前本店。この場所からスタートし、全国へと店舗を広げた
「私は西洋料理のコックになりたかったんです。お好み焼きは食べるのは好きでしたが、商売として関わりたくはなかった」と当時を振り返る中井会長。しかし、義兄にさとされ、1967年に千房の前身となる「お好み焼 喜多八」を継ぐ。
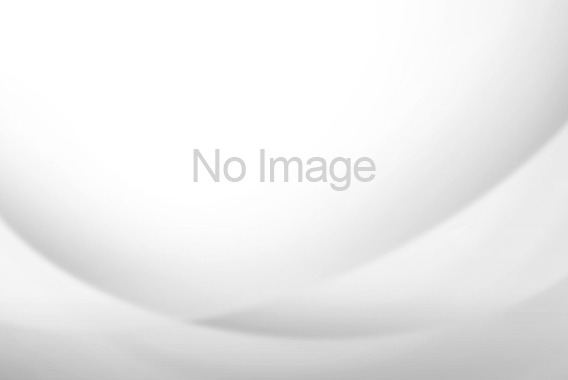
千房のお好み焼きはふわふわの生地が特徴
「お好み焼き屋は嫌だ、という当時の思いが今の千房を作る大きな原動力になっていきます。その頃の私は、お好み焼き屋なんて、一人前の人間が携わる商売ではないという偏見を持っていたんです。お好み焼きに関わるのが恥ずかしい、カッコ悪いと思っていた。だから、そこで働く従業員はもっと嫌だろう、恥ずかしいだろうと思ったんですね。従業員を募集しても、来てくれなくて当たり前だという思いが根底にあったんです。だからこそ、従業員が胸を張り、自信を持って働けるようなカッコいいお店を作りたい。カッコいい会社になろうと思ってやってきました」(中井会長)
独立して6年目、ようやく喜多八が軌道に乗り始めた頃に、大家から借りていた店舗の明け渡しを言われた。移転先の店舗を探し、1973年に大阪千日前に「お好み焼千房」の1号店をオープンした。
従業員が誇りを持って働けるよう、どんどん新しい挑戦を続けた中井会長は、「千房には“日本初”と冠がつくものがたくさんある」と胸を張る。
とはいえ、最初から72店舗にまで広がるとは考えていなかった。「2店舗目を出店したときには、チェーン展開すると決めていました。それでも、当時5人の従業員がいたので、それぞれを店長にして、5店舗を目指そうといった程度の気持ちでした」と中井会長は振り返る。
予想を超えて大きく展開できた理由は3つあると中井会長は分析する。それは、「味がいい」「値段が安い」「立地がいい」の3つ。多店舗化にあたりこの3つの要素を厳守したのだ。しかし、いい立地の場所は当然、家賃が高くなる。
「飲み屋街のど真ん中という好立地の1号店は、保証金や権利金などで初期費用は5000万円ほどかかりました。周囲は大反対です。でも、私は絶対ここだと思いました。なぜかというと、競合店舗がいないからです。誰も、こんな高い家賃を払ってお好み焼き屋をやろうなんて思わない。予想通り、お客さまを独占できました。この経験から2店舗目以降も好立地に出店するという戦略を続けたのです」(中井会長)
店舗を拡大し、売り上げは右肩上がりだった。「20代の頃、『中井さん、景気はどうや』と周囲に聞かれるので、正直に『むちゃくちゃいいですね』と答えていたら、『あいつは生意気や』と批判されました。本当のことを言ったらダメなんだと分かり、それからは『ぼちぼちでんな』と答えるようになりました」と中井会長は笑う。

2013年にPeachの機内食に採用された
2013年には大阪府に本社を置く格安航空会社(LCC)のPeach Aviationの機内食に採用された。「お好み焼きが機内食に採用されたのは、世界初です。それまでは、お好み焼きは匂いが充満するからと機内販売は敬遠されていました。しかし、匂いが充満するからいいという逆の発想で採用していただき、これが大成功でよく売れました。匂いがただようから、お好み焼きを食べたくなるんですね」(中井会長)

高級感漂う「ぷれじでんと千房」の内観(大丸心斎橋店)
庶民的な食べ物という従来のお好み焼きのイメージを打ち破り、1985年には都ホテル大阪内に初めて高級食材を使った「ぷれじでんと千房」を開業。2006年にはさらに鉄板焼きメニューなどオリジナルメニューを加えた「エレガンス千房」もオープン。「2020年に東京・虎ノ門に開店した『琥(こはく)千房』は、1人単価15000円以上です。お好み焼きをディナーとして楽しんでいただけます」と中井会長は話す。
中井会長が後継者について真剣に考え始めたのは、千房の一号店オープンから40年たった2013年。3人の息子に恵まれたが、当初は親子承継以外の選択肢も考えていたという。「優秀な社員に譲ることや、株式上場も視野に入れていました」と話す中井会長。しかし、親族以外に承継するには、中井会長にはいくつかの懸念があった。その一つが、千房は、創業当初から非行少年や元暴走族などの若者を社員として受け入れてきたことだった。
「店舗を拡大していく中で、常に人手不足に悩まされてきました。そこで、学歴、学業の成績、身元保証人を一切問わず、意欲さえあれば採用してきました。その中に非行少年や元受刑者がいたんです。私は過去を一切問いませんでしたから、知らなかったのですが、彼らが立派に更生して店長などを務めるようになり、実は過去にいろいろあったと聞くことがあったんですね。そうすると、知り合いから『うちの子がちょっとやんちゃなんだけど、預かってくれないか』と頼まれる機会が増えていきました」と中井会長は話す。
2009年から法務省の依頼で社会復帰支援センターに出向き、受刑者と面会。本格的に元受刑者の採用支援を始めた。現在は日本財団と連携し「日本財団職親プロジェクト」を立ち上げ、思いを同じくする他企業とともに活動を続けている。この取り組みは中井会長がリスクをとりながらも、覚悟を持って始めたものだが、株式上場をすると株主の意向を気にする必要が出てくる。
実際、最初は社内にも反対意見があったという。「客商売なので、お客さまが怖がるのではないかと言われました。でも、この取り組みがよいか悪いかと尋ねると、みんな『いいこと』だという。損得ではなく、善悪で判断する。これがすべてです。再犯を起こす人の7割が無職というデータがあります。就労支援が再犯防止につながるのです。殺人といった重大犯罪や再犯率の高い薬物、性犯罪は除き、今までに45人を採用しました」(中井会長)。
親族承継を意識していた中井会長は、1996年、地方銀行で働いていた長男に声をかけ、千房への入社を実現させた。「ただ、当時は完全に彼を後継者だと決めていたわけではありませんでした。社員の夢や希望をなくしたくないという思いもあったからです」。
現場を知るため、長男には皿洗いから始めさせた。「店長にも社長の息子だと思わず、厳しく教育してくれと言い聞かせていました。でも店長はやりづらかったと思います。長男はよく酒の場に出掛けていました。私は飲まなければ付き合えないような業者とは付き合わなくていいと思っていましたから、長男にも行かなくていいと言っていました。でも、社長の息子だからと取引先に誘われると、断れなかったのでしょう。当時は私も彼を怒ってばかりでした。怒れば怒るほど、彼はお酒に逃げていきました」。
そしてあるとき、長男は体調を壊してしまう。異変に気付き、中井会長が病院に連れて行ったときには、もう手の施しようがないほど重度の肝硬変と診断された。2013年の年末に病気が発覚し、翌14年の5月に44歳の若さで長男は他界した。深い悲しみの中、中井会長は三男の貫二氏に「戻ってきてくれないか」と連絡をする。貫二氏は、「分かりました」と即答し、14年7月に千房に入社した。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際