
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
エーワン精密(コレットチャック・自動旋盤用カムなどの製造)
事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第21回は、東京都府中市で工作機械部品や切削工具を製造するエーワン精密の創業者の梅原勝彦氏だ。現在は相談役を務めている。
エーワン精密は、創業してからの経常利益率が平均35%の高利益体質を誇り、一度も赤字を出していない。梅原氏は時間をかけて高収益で強い会社をつくってきた。リーマン・ショックの2009年度は売り上げが前年から35%落ちたというが、その際でも利益率は23%。その盤石な経営基盤が揺らぐことはなかった。
梅原氏は東京都・港区で町工場を営む両親の下に生まれた。「幼い頃から工場の音を聞きながら育った」という。ところが、小学校に入ってすぐに父の会社は倒産してしまう。極貧生活に転落し、小学校を卒業した後から梅原氏は町工場で働き始め、10代はろくろの技能者として修業を積んだ。
22歳のとき、東京府中市の電子部品メーカーの下請け企業に呼ばれた。そこはそれまで梅原氏が働いてきた小さな工場とはまるで違っていた。「初めて自動旋盤を見た。今まで身に着けた技術では今後太刀打ちできない」と梅原氏は悟った。「若かったからできたこと」と言うが、梅原氏はろくろの技術をすべて捨て、自動旋盤の技術を一から学んだ。

エーワン精密の経営を軌道に乗せた自動旋盤用「カム」
「管理者候補として呼ばれたものの、自分には学歴がないので、このままここで働き続けてもせいぜい課長止まりだろう。もっと自分の力を試してみたい」と奮起した梅原氏は、1965年、26歳のときに独立を決意する。その後1970年に現在のエーワン精密の社名で法人化を果たした。
創業時のエーワン精密は、自動旋盤用の「カム」という工具製造がメイン事業だった。「旋盤にこのカムを取り付けることで刃物の動きが変わり、継続して同じ部品を作ることができる。カムは機械の刃物を制御するソフトウエアみたいなもの」と梅原氏は説明する。 大手メーカーが製造していたカムは高額で納期が遅かったため、スピードを重視した梅原氏はカムの製造で会社をすぐに軌道に乗せた。
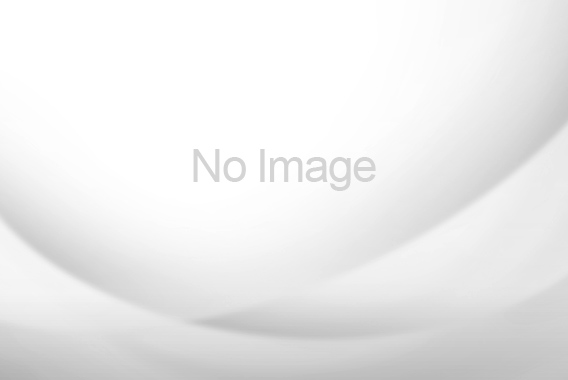
エーワン精密で製造するコレットチャックは、短納期が評価され国内シェア6割を誇る
だが、間もなくして製造業にもデジタル化の波がやってくる。「数字制御の機械が出てきたときに、やがてカムは必要なくなるだろうと瞬時に悟りました。カムに代わって何を主力商品とするかを考えた際、工作機械で加工する材料をつかむコレットチャックという部品なら需要がなくならないと注目しました。約2000社あるカムのお客さまがそのままコレットチャックにもスライドできることも好都合でした」(梅原氏)
この目の付けどころが当たった。現在、エーワン精密は、コレットチャックの製造において国内シェア6割を占めるまでになっている。そして、同社の売り上げ約17億円のうち7割を占める事業に成長した。

うめはら・かつひこ
1939年、東京都港区生まれ。戦後間もなく、父が経営するねじ製造の町工場が倒産し、一家離散。12歳から父の知人の工場ででっち奉公をしながら夜間中学を卒業。65年に兄と日本初のカム専業メーカーを創業。70年にエーワン精密を設立。76年から着手したコレットチャック事業を主力事業とし、高収益構造を築き上げた。2007年に社長を退任し取締役相談役となる
ただし、コレットチャックの市場規模は決して大きくはない。そのため、近年は売り上げの拡大をめざし、エンドミルやドリル、カッターなどの切削工具の研磨・製造にも参入している。量産を得意とする大手企業ができない、1本からの少量多品種の製造に対応することによって評価を上げ、今後の成長が期待できる事業に育ちつつあるという。
「事業を考えるポイントとして共通しているのは、まず消耗品であること。そうした商品は長期間ずっと受注できます。そしてもう一つは、大手が参入できないニッチな分野でトップになれる可能性があることです」(梅原氏)
また、梅原氏は「適正価格」にもこだわった。同社が高い利益率を維持できているのは、販売を自社で手掛け、価格決定権を持ってきたからだ。そうして出した利益を工場の設備投資と社員教育の投資に当ててきた。
梅原氏には3人の子どもがいるが、創業当初から承継は「親子承継はしない」と考えていた。子どもたちは小学生になるまで父親が経営者であることを知らなかったという。「親子承継を否定するわけではない。ただ、いい血が長く続くとは限らない。100年続いた徳川家の将軍も直系ばかりではない。親子承継に固執すると選択肢が狭まってしまう」と梅原氏は考えた。
そうした意識を持つ梅原氏は2003年、株式上場にも踏み切った。「会社を公のものにしておくことを意識して、上場を決めました。経営において公私混同が一番よくない。特に他人に承継してもらうなら、お金の面ではよりクリーンにしておく必要があります。上場することで、会社が公のものになり、クリーンな経営をしていると認められます。それが大切だと思いました。上場すると自分の会社ではなくなりますが、私にとって、そんなこと一向に構わなかったんです」(梅原氏)
2007年、68歳で梅原氏は社長を退き相談役となった。「タイミングは年齢的なもの。創業者なのでもう少し長くやってもよかったかもしれないが、老害が出る前に辞めたいと考えた」という。
梅原氏が後継者に選んだのは、林哲也現社長。林社長は実は、株式上場を担当した際に同社の審査を担当した証券会社の社員だった。エーワン精密のことを詳細に知り尽くした林氏は同社にほれ込み、入社してきたという。「ものづくりの会社なので、社員のほとんどが技術者。数字や経営に強い林氏が後継者として適任だと考えました」と梅原氏は説明する。
梅原氏は社長退任と同時に代表権も手放している。「創業者で、力があり、やり手で社員にも人気のある人間が代表権を持って会長としてとどまったら何も変わらないでしょう。共同代表の期間は設けず、すぐに代表権を持たない相談役になりました。引退とはそういうものです」
そうは言っても、やはり創業者だ。「81歳になった今でも会社のことが気になってしょうがない」と笑う。毎朝出勤し、社員の顔を見て少し話してお昼には帰るのが日課だ。「今でも夢に見るのは仕事のことばかり。妻からは、社長を辞めたのに何も変わってないと笑われます。でも、創業者はみんなそうだと思いますよ。死ぬまで会社のことが気になるものです」
事業承継がうまくいく秘訣について聞くと、梅原氏は「利益を出すこと」と明言する。
「税金を払いたくないからと利益を出したがらない経営者も多い。でも、企業の役割は、雇用と納税です。利益をしっかり出して納税していることが、社員の雇用を守ることにもつながる。厳しい言い方かもしれませんが、毎期赤字という会社は、世の中から必要とされていないということです。かの松下幸之助氏も、利益は世の中から必要とされている尺度だとおっしゃっています。ときどき、「かわいそうだから子どもには継がせられないので後継者がいない」と言う社長がいます。もうかっていない会社は誰も継ぎたがりませんよ。しっかり利益を出していい会社にしていれば、親子承継でも、第三者承継でも、必ず継ぎたいという人が現れます」(梅原氏)
同社には山梨県の工場も含め、現在約100人の従業員がいる。梅原氏は従業員たちに定年までにローンを完済した状態で家を持たせてあげたいと望んでおり、実際多くの社員が若いうちから持ち家を取得しているという。
「おかげさまで、健全な経営をしていると銀行からの信頼も厚くなるんです。うちの社員が銀行に行って住宅ローンを組もうとすると、すぐに審査が通る。だから社員も辞めない。まれに欠員が出ても知り合いや家族を紹介してくれます。当社は定年まで働き続けてくれる人が増えています。創業時から、自分が勤めたくなるような会社にしようと思って、一生懸命いい会社に育ててきた結果です」と梅原氏は胸を張る。
これから先もエーワン精密がさらに世の中に必要とされる会社であり続けてほしいと梅原氏は願っている。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際