
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
ナベル(鶏卵の自動選別包装装置の開発・製造・販売・修理)
事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第26回は、鶏卵の自動選別包装機を製造するナベル(京都市)の南部邦男会長。1964年に創業し、国内の鶏卵選別包装機のシェア80%以上もの会社に育て上げた。南部会長は2018年に長男の邦彦氏に事業を承継している。
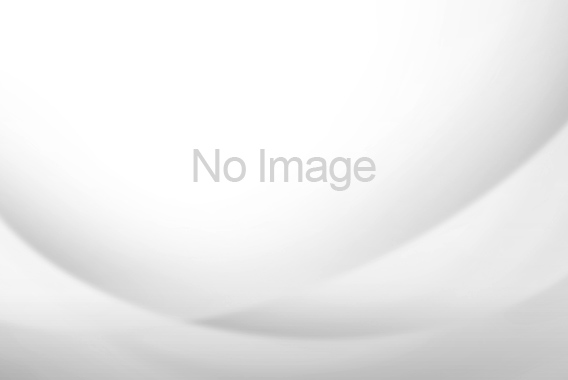
南部邦男(なんぶ・くにお)
1948年生まれ。高校1年生の時、父親が経営する“町の電気屋”が倒産。父と共に電気機器の制御盤の組み立てを行い、生計を立てる。働きながら立命館大学2部文学部を卒業。77年、南部電機製作所(87年にナベルに社名変更)を設立。卵の選別包装機の市場で、国内シェア80%以上、世界シェア第2位の企業に成長させた。2018年に長男の邦彦氏に事業承継し、現在は同社の取締役会長を務める。
ナベルの創業のきっかけは、南部会長の父親が経営していた街の電気店の倒産だったという。当時高校1年生だった南部会長と父親が、大手家電メーカーから電気制御を請け負う会社として南部電機製作所(現ナベル)を創業した。
当時から南部会長は「下請けの事業だけではつまらない。せっかく会社経営をするなら、もうかる事業をしたい」と考えていたという。
数年事業を続ける中で、南部会長は、養鶏場など鶏卵業界の課題を知る。ニワトリが生む数万個もの卵を、重さ別に分けてパック詰めし、ホチキスで止めるのは大変な作業だった。当時、鶏卵の機械は欧米からの輸入品しかなく、国産の機械は重さ別に仕分けるだけで、パック詰めの機能はなかったという。養鶏場や選別包装業の会社から、「海外の機械は高額なので、ぜひ国産の機械を作ってほしい」と請われ、南部会長は鶏卵の選別包装機の開発に没頭していく。
「当時の日本は戦後復興期。製造業は伸び盛りで、業界全体が自信にあふれていました。私自身も、卵の選別包装機械くらい作れるだろう、と思っていたんです。従業員は14人。20~30代の血気盛んな若者たちが、昼間は下請けの電気制御の仕事をして、17時以降は鶏卵装置の開発に集中し、夜遅くになったらみんなで飲みに行く。その頃の泣き笑いの楽しい思い出はたくさんあります」(南部会長)
1975年、最初の試作機ができあがり、南部会長たちは喜び勇んで養鶏場での試験に出向いた。超音波でパックをシールする機械だったが、それは大失敗に終わった。
「卵の選別包装機ではなく、卵割り器でした(苦笑)。それでもありがたかったのが、養鶏場の皆さんが非常に温かく応援してくださり、もう1回出直してこい。卵はたくさんある。多少割れても気にせんでいいから頑張れ、と言ってくださったんです。ここがナベルという会社の基礎になっています。我々は養鶏業界の工務部門である。この恩は絶対に忘れたらあかんと思っています」(南部会長)
開発に着手しておよそ6年、1979年に周囲の応援のおかげもあり、ついに日本初の鶏卵選別装置が完成した。

1979年、国内で初めて製品化した鶏卵全自動選別包装装置。鶏卵移送時の破損率を劇的に下げる、移送速度封殺制御技術を開発した
1992年にはマレーシアに海外1号機となる鶏卵選別包装機を輸出し、2003年に現地法人を設立した。その後も順調に海外展開し、今ではアジア、欧米、アフリカなど、世界71カ国で同社の機械が使われており、ナベルは従業員約200人、売り上げ60億円超の企業に成長した。
事業を拡大していく過程には、苦難もあった。35年ほど前には米国の競合企業に特許侵害で訴えられ、4年にわたる裁判を戦った。結果的に和解で決着したが、このときの苦い思い出から、特許申請にも力を入れてきた。
「生きるか死ぬかの大変な経験をして、そこからは特許を基本に据えるべきと考えました。特許申請書類をひたすら書いて、今では数百件もの特許が出願されています。鶏卵選別包装機械では、年間の特許出願数は世界ナンバー1です」(南部会長)
自ら会社を興し、新しく生み出した製品により会社を成長させてきた南部会長にとって、仕事は人生そのもの。それゆえに、事業承継のプロセスは、苦難の連続だった。
南部会長には2人の息子がいる。かつては「親子承継はしない」と公言していた時代もあったというが、株式非公開企業においては、同族経営のメリットのほうがあるのではないか、と考えるようになった。大学を卒業し、それぞれの就職先で働いていた息子2人に、「ナベルに入らないか」と南部会長のほうから声をかけた。

長男の邦彦氏は、2002年に京都コンピュータ学院を卒業し、04年、ナベルに入社。18年10月に事業を承継し、現在社長を務める
「ある日突然、ナベルに入社するという話ではなく、大学在学中くらいから話をして、徐々に息子たちもその気になっていきました。2人は同時期にナベルに入社しています」(南部会長)
息子2人は入社後技術部門などを担当し、2009年にはブラジルの現地法人の立ち上げの責任者となった。
「結果的にブラジル法人はうまくいかなかったのですが、撤退までを2人でやり切りました。私が退任したら、2人で会社を経営していくことになるので、ブラジルでその練習をしてほしいという思いがありました」(南部会長)
息子たちが順調に経験を積んでいた2012年、南部会長が64歳の時に、創業メンバーで副社長を務めていた丸山勉氏を社長にしている。しかし、事情により2年間で丸山氏はナベルを退社することになり、再び南部会長が社長に復職した。丸山氏は現在、子会社の社長として復帰している。
「創業時から苦楽を共にしてきた彼に社長をやってもらいました、でも私にその覚悟ができていなかったから彼はやりづらかっただろうし苦労したと思います」(南部会長)
次に事業承継が大きく動いたのは、2018年4月。南部会長は次男の隆彦氏を社長に就任させた。
「もともと、入社時から2人に対しては、次男のほうに指揮をとるように伝えていました。先代を超えていこうとするような、後継者として必要な乱暴さは次男のほうがありました」(南部会長)
ところが、この体制は半年しか持たなかった。南部会長が「気に入らなかったので、ちゃぶ台返しをした」というのだ。その後、同年10月に長男の邦彦氏が社長に就任し、南部会長は代表権を手放した。「もう二度と、自分から社長を替えることはしない」と南部会長は断言する。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際