
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
神戸物産(業務スーパーの運営、フランチャイズ展開)
事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第40回は、フランチャイズチェーンを含め、全都道府県で業務スーパーを展開する神戸物産(兵庫県加古川市)のケースの後編。創業者沼田昭二氏は、2012年2月に当時31歳だった長男の博和氏に事業承継した。その後、2トップ体制で引き継ぎを行い、2017年5月、すべての役職から離れて退社した。
当時763店舗の業務スーパーを運営していた神戸物産を潔く退いた沼田氏。この潔さには周囲からも驚かれたという。沼田氏が事業承継を急いだ理由が2つある。1つは甲状腺がんと脳幹脳梗塞という2度の大病を患ったこと。もう1つは、新たな使命感が生まれたことだ。
「私は元気なときは毎月2~3回、海外のさまざまな国を訪れていました。これまでに50カ国以上、500回は海外に行っていると思います。海外の状況を見れば見るほど、リスクを感じるようになったのです。今回のロシアとウクライナの争いもしかり、政治情勢、地政学的にも、リスクが全くないというエリアはありません」と沼田氏は強い危機感を口にする。
一方で、日本の貿易収支を見ると、2021年までの過去10年間では、黒字になったのは2016年、2017年、2020年の3年だけ。海外投資による利子や配当の受け払いが巨額のため、経常収支では依然として黒字が続いているが、今後はどうなるか分からない。日本には資源がないため、化石燃料が輸入できなくなったらどうなるのか、という危機感も沼田氏は強く覚えているという。
「日本の地方はどんどん疲弊しています。それを回復させるために、地方創生とエネルギー開発の融合を、北海道、九州、東北でやりたい、という新たな使命感が生まれました。10万円というわずかな資本金から会社を興し、皆さんのおかげで業務スーパーを大きく成長させることができました。博和君という優秀な後継ぎに恵まれたので、その感謝の思いも込めて、今後は日本の食糧自給率とエネルギー自給率の低さという課題を解消する事業に残りの人生を懸けたいと考えたのです」(沼田氏)
2016年、62歳で日本の食糧自給率とエネルギー自給率アップを大義名分とした「町おこしエネルギー」を設立し、代表取締役社長に就任した。自身で育て、大きく成長させた神戸物産を退くことにためらいはなかったのだろうか。

沼田昭二(ぬまた・しょうじ)
神戸物産創業者。町おこしエネルギー会長兼社長。1954年兵庫県生まれ。兵庫県立高砂高校を卒業後、三越に入社。1981年に食品スーパーを創業。フランチャイズ方式で「業務スーパー」を全国展開する。2012年、長男の博和社長に事業承継した
「私は恐らく、ゼロからつくり上げることが得意なんです。周囲の経営者を見ても、会長や顧問など、何らかの形で多くの経営者が事業承継した後も居座っています。1つの成功体験なので、どうしてもそこに執着してしまうのでしょう。でも、それでは会社経営は中途半端になります。次期後継者が早く意思決定できる環境をつくらなければ、厳しい時代に生き残ってはいけません。私は病気になった時に、私利私欲は絶対に出さない、残りの人生は次世代のために使う、と神様に願掛けをしました。そこに強い使命感と義務感を持っていましたから、退社することに何のためらいも感じませんでした」
沼田氏が退社した直後は、家族で食事をしたときに博和社長から会社の話や相談をされるときもあったというが、今はほぼ仕事の話はしないという。
「話を聞かなくても、見ていれば分かります。ありがたいことに、神戸物産の株式の時価総額は1兆円を超えました(※)。それほどの会社を経営するには、当然大変なことがいろいろあります。神戸物産には確かにパワーもスピードもある。しかし、だからといって決して経営がラクなわけではありません。
※2022年4月11日時点
それでも博和君は愚痴ひとつ言わず仕事をして、土日はしっかり家族サービスもしています。自分自身は土日も関係なく働き、家族にさみしい思いをさせてきましたから、そういう博和君の姿を見るとよくできているなと感心します」
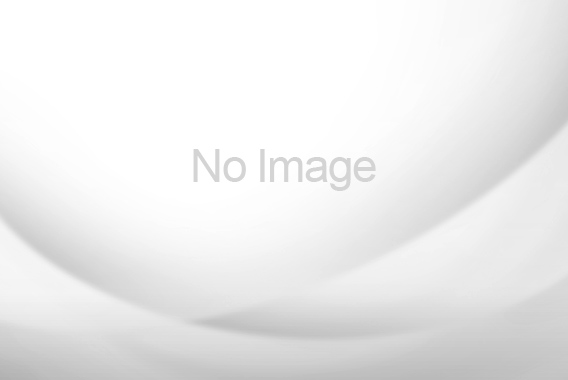
全都道府県に展開する業務スーパー。国内外で製造するオリジナル商品が強み
2トップの時代はCEOと社長の立場だったが、沼田氏が神戸物産を退社したことで、二人は再び、ただの親子に戻った。
「仕事中は自分の息子でも、沼田社長と呼んでいました。それは嫌だな、早く辞めたいなと思っていました。社長ではなく、息子として見るほうが楽です。私が会社を離れたため、またただの息子の博和君に戻りました。スッパリ引いたので、仕事に関してケンカをした記憶もありません」
博和社長の入社後、1年ずつ部長、取締役、社長と計画的に段階を踏んだように、沼田氏は株式の譲渡も計画的に進めた。

沼田博和社長
「最初に病気になった時から、株式は早く譲渡したいと考えていました。数回に分けて子どもに譲渡したほか、2012年に設立した業務スーパージャパンドリーム財団にも寄付しました。同財団の資産額は国内有数の規模となっており、海外で活躍できるスポーツ選手や芸術家の人材育成に当てています。自分で経営している会社なので、1年後、2年後に財務や収支がどうなるかは大体予想がつきますから、早め早めに粛々と進めました。怖がりなんですよ。子どもの頃からよくお母ちゃんにそれで怒られていました。ただ、株式の譲渡で感じるのは、日本は海外に比べて税率が高いんです。それも日本の課題だと思いますね」(沼田氏)。
「自分は幸せな事業承継ができた。大成功だった」と振り返る沼田氏に、これから事業承継をする経営者へのアドバイスを聞いた。
「願わくは、どうか承継する子どもさんを信じてあげてください。お子さんも一生懸命努力していると思います。それに対して、あれが足りない、ここがダメだと言われたらいい気はしません。大切なことだけ伝えて、あとは遠くから見守る。信じてあげることがスタートだと思います。自分の分身ですから、親が信じなくて誰が信じるんですか。信じる気持ちは、必ず子どもさんに伝わります。もちろん、自分が人生を懸けてつくってきた会社なので、口を出したくなる気持ちもよく分かります。だからこそ、スパッと辞めて任せたほうがいい。もちろん、無責任に離れるのはダメですから計画的に進めて、大丈夫だと思ったら少しでも早く離れたほうがいいと思います」
そうはいっても、向き・不向きはある。「経営者は従業員とその家族を守る責任があるため、どうしてもダメなら、子どもではなく優秀な従業員を立てるしかない」と前置きしながらも、沼田氏は「それでも私は、基本は子どもが継ぐべきだと思います。企業の合併・買収(M&A)を否定はしませんが、例えば大手の傘下に入ると、サラリーマン社長が自分の任期中の利益だけを考え、短期的な経営方針になってしまうこともあります。それが今の日本が世界における競争力を落としている原因の1つだと考えています」と語る。
新たに立ち上げた町おこしエネルギーでは、日本初の地熱発電所のフランチャイズ展開を進めている。フルオーダーで発電所の建設にはこれまで10年ほどかかっていたが、それを1~3年で実現するという。同時に、北海道や九州で農地を購入して6次産業化も進めている。「6次産業化とは、1次産業としての農林漁業と、2次産業としての製造業、3次産業としての小売業などの事業との総合的かつ一体的な推進を図ることです。これによって豊かな地域資源を活用し、地方の活性化が実現できます」(沼田氏)。
「神戸物産を辞めてほっと一息ついたと思ったのですが、今はさらに忙しくなっています」と沼田会長は笑う。残りの人生を、大きな使命を果たすために力を尽くしたいと考えている。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際