
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
坂東太郎(ファミリー向けレストランチェーンの運営)
事業承継を果たした経営者を紹介する連載の第6回は、茨城県を中心に、ファミリー向けの飲食チェーンなどを展開する坂東太郎のケース。看板店であるそば・うどん・すしの和食ファミリーレストラン「ばんどう太郎」のほか、焼き肉、とんかつ、すし、ステーキ、カニ、コーヒーといった専門店も営業している。
創業者の青谷洋治会長は、「親孝行・人間大好き企業」を経営理念として、社員を幸せにする会社経営を続けてきた。2016年に息子の英将氏に会社を承継したが、現在も代表権を持つ会長として坂東太郎の経営を支えている。事業承継の方針に込められた青谷会長の思いに迫る。
郊外型ファミリーレストランをチェーン展開する坂東太郎は、「親孝行・人間大好き企業」という一風変わった経営理念を持つ。この場合の「親」とは、生みの親だけでなく上司や先輩など、お世話になったすべての人のことだとしている。この経営理念を考えたのが、創業者の青谷洋治会長だ。
同社を象徴する制度の1つが、店舗でフロアサービスを担当する女性従業員を「女将さん」と名付けた「女将制度」だ。パートで働く女性従業員の定着に悩んだ青谷会長が考え、2007年に導入にした。店舗ごとに任命された女将はリーダー的な役割を担う。現在は約70人の女将さんがおり、年に一度全員が集まる女将大会も実施する。
「“女将さん”は魔法の言葉。役職を与えることで、やりがいや責任感が生まれ、みんな生き生きと仕事をするようになった」と青谷会長は話す。
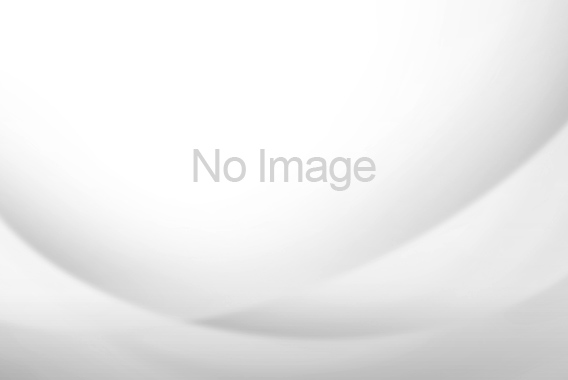
接客のプロである「女将さん」は約70人。全員が集まる女将大会では、自己成長体験をテーマにした作文コンクールも実施する
青谷会長は1951年、茨城県で野菜を栽培する農家の長男として生まれた。当時、農家の息子は家業を継ぐことが当たり前とされていた。そのため、青谷会長が小学校の卒業文集に書いた「社長になりたい」という夢は、周囲を驚かせた。同級生たちは、「青谷が社長になんかなれるわけがない」とからかったという。「そのとき自分の中に生まれた悔しさは、今も自分の胸の中にある」と青谷会長は話す。

青谷洋治(あおや・ようじ)会長
1951年、茨城県出身。専業農家の長男として生まれ、20歳で農業から飲食業に転身。75年に独立。86年に法人化し株式会社坂東太郎を設立。2016年に息子英将氏(現社長)に事業を承継し、代表取締役会長となる
農家に生まれたから、農家として生きる。そんな決められたレールから抜け出して、自分の人生を歩みたいという思いがあった。しかし、中学3年生の2月、病気で母親が亡くなる。戦争から帰ってきた父は心臓を患っており、思うように働ける状態ではなかった。青谷会長は高校進学を諦め、家業を継ぐしかなかった。
忘れかけていた夢がよみがえったのは、20歳の時だった。そば屋を立ち上げる知り合いがアルバイトを募集しているという話を聞き、どうしても「社長になりたい」という夢を追いかけたくなった。農家を手伝ってくれた妹のおかげで、青谷会長は飲食の世界に足を踏み入れることになる。
「家族に迷惑をかけてまでこの道を志したのだから、必ず成功しなければならない」という一心で、青谷会長は修業に励んだ。飲食の世界は、一人前になるのに10年はかかるといわれていたが、3年半で独立を果たす。1975年、青谷会長が24歳の時に、茨城県の境町に1号店をオープンした。20坪ほどの小さなお店からのスタートだった。
創業後、順調に業績を伸ばし、5店舗を運営するまで成長していた。86年には法人化を実現。ところが、そんな青谷氏をピンチが襲う。バブル崩壊直前の1990年頃、人手が足りなくなってしまったのだ。募集をしても応募者がいない。採用してもすぐに辞めてしまう。古株社員が次々とお店を離れていく。それでもお客さまは日々たくさん来るため、業務に支障が出る。これ以上スタッフが辞めたら労務倒産してしまう、という経営危機に陥ったという。
まずは、従業員をしっかり休ませなければと考えた青谷会長は、閉店後、従業員をすぐに帰して、お店の片付けや翌日の準備は自らがするようになった。5店舗すべての業務を終え、朝方、帰り道に必ず母親の墓に行き、手を合わせる毎日だった。大きな危機感を抱えて、当時の青谷会長には、母親に祈るしかすべがなかったのだ。
そんな日々が数カ月続いたある日、墓参りをしているとふっと体の力が抜け、母親の声が聞こえたという。
「働く人が幸せじゃないから、社員は辞めていくんだよ」
幻聴かもしれないこの言葉に、青谷会長は目が覚める思いだったという。青谷会長はすぐに全従業員を集め、頭を下げた。「みんなを幸せにしようと思ってやってきたけれど、心の底からみんなにその思いが伝わっていなかったと思う。申し訳ない」。
そして、従業員全員の家庭を訪問して、家族や生活環境まで理解しようと努めた。また、1人ひとりと膝を突き合わせて座って話す「社長塾」を始めた。従業員は任意で参加できる仕組みで、夢や目標を語ったり、時には不平不満も漏らしたりもする。この社長塾は、現社長の英将氏にも受け継がれている。

2019年4月にオープンしたばかりの「ばんどう太郎」みらい平店。創業から44年たち、現在坂東太郎は直営で77店舗を展開。売り上げはグループ全体で100億円を超える
これまで何事も計画的に進めてきた青谷会長は、事業承継についても計画性が大事だと考えた。長男の英将氏は、大学卒業後、飲食店コンサルティング企業に入社した。「全国の飲食店経営者とつながりができ、人脈と視野を広げることができるだろう」と青谷会長が勧めた。その後、英将氏は自分の意志で同業他社に転職した後、坂東太郎に入社した。
承継に当たり、青谷会長は「飲食業はスピードの速い業界で、自分自身も24歳で起業した。息子が30歳になるまでには承継できればいいが、遅くとも40歳までには譲るのが承継する側の役目だろう」と考えていた。
何より気を配ったのは幹部をはじめとする従業員の気持ちだった。「二代目社長に対して、息子だから後を継ぐんだろ、と社員が思ったら、その後の会社はうまくいかなくなる。みんなが社長を認め、支えたいと思うまで待つ必要がある」と考え、青谷会長は当時の幹部全員と面談を重ねて、反対する人が1人でもいれば承継はしないと決めていた。
「会社は社長のものではない。従業員やお客さまのもの」という思いがあったからだ。社長の交代によって、従業員やお客さまに不利益があってはいけない。そのため、タイミングには慎重だった。「事業計画をしっかり立て、その通りに後継者と一緒に歩けるようになったら承継する。無理をする必要はない。また、景況の変化も見据え、いつなら安全に引き渡せるかの見極めも大切」と青谷会長。さまざまな状況が整った2016年、英将氏が38歳の時に事業承継を果たした。

青谷洋治会長(左)と、息子で現社長の英将社長。青谷会長は、承継時に「あなたを信じる」と息子に伝えた
その後も青谷会長は代表権を持ち、社長就任から5年間は英将氏の横で伴走すると決めている。そして、現在はその4年目だ。「5年たったら、今度は後ろからバックアップしていきたい。事業のやり方はそれぞれ考え方があるので、自分流にやっていけばいいし、失敗もたくさんした方がいい。ただし、人はもうかるからという判断で、時には本質的なことを誤るときがある。経営者にとって最も大事なことは“ブレない”こと。社長がブレないよう、しばらくは後ろから支えていきたい」と青谷会長は話す。
そんな青谷会長は事業承継について、周囲の経営者やその子どもからさまざまな相談を受けることが多いという。
「トップがなかなか譲ってくれない、という後継者側の悩みを聞くこともたびたびある。確かに、時代を見る目は、もしかしたら子どもの方があるのかもしれない。でも、経営というのは、一時的に売り上げを確保すればいいというものではない。経営者は長い目で経営を見ている。10年20年、あるいは100年続く会社にするための視野や器が本当に備わっているかを自分に問うてほしい。良い面・悪い面含め、社長や会社の現状をどれだけ客観的に語ることができるかが大事」と話す。
一方、事業を引き渡す側に対しては、次のようにアドバイスする。
「何より大事なのは、後継者を信じること。そのために、たくさん会話をしてほしい。仕事のことだけではなく、人としての器を広げるような会話をたくさんして、勉強の機会を与えてほしい。会社の売り上げを伸ばすことももちろん大事だが、それ以上に、会社の事業がどのように社会の役に立つのかを考えられるように育てることが大切」とアドバイスする。
68歳になる青谷会長は、今、1つの大きな目標を持っている。それは、地元筑波山の麓に体験型の「母の里山」をつくることだ。農業体験やさまざまなワークショップができる里山づくりを計画しており、学びの場にしたいと考えている。10年越しの大きな夢の完成は、東京五輪後だと語る。
今後の坂東太郎に対しては、「なんとなく、呼び捨てではなく“さん付け”してしまうような、地元に愛される会社であってほしい」と話す。そのためのかじ取りを、英将氏に期待している。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際