
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
堀田カーペット(ウールのウィルトンカーペットの製造・販売)
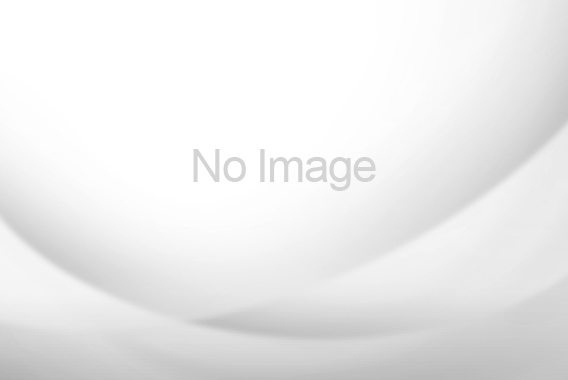
堀田繁光(ほった・しげみつ)
1951年生まれ、大阪府出身。大阪工業大学を卒業後、1973年に堀田カーペットに入社。1991年に社長に就任。2017年に長男の将矢氏に事業承継し、代表取締役会長となる
事業承継のヒントを紹介する連載の第47回は、大阪府和泉市に本社を構える堀田カーペットの2代目、堀田繁光会長。高度経済成長期から、職人とともにウールにこだわった高品質のカーペットを作り続けてきた。父親の創業した会社に入社し、火の車だった経営を軌道に乗せた堀田会長。2017年に長男の堀田将矢氏に事業承継した。その承継までのストーリーを堀田会長と長男の将矢氏に聞いた。前編では、堀田会長自身の入社と父親からの事業承継、そして将矢氏を承継者に決めるまでを振り返る。
堀田カーペットの創業は1962年。堀田会長の父が大阪府和泉市でスタートした。「創業当時、私はまだ中学生くらいでした。創業者ではありますが、父は特にカーペット製造の経験があったわけではありません。たまたま知人が経営していたカーペット会社を閉めるという話があり、父が受け継いだのです。最初は出資者として関わっていたのですが、事業を軌道に乗せるために、製造も含め経営に関与していったと聞いています」と堀田会長は説明する。
工場は自宅から10分ほどの距離にあった。堀田会長は父が運転するトラックの助手席に乗せられ、300キロもあるカーペットを運ぶ手伝いもしたという。その後、堀田会長は大阪工業大学に進学。自動制御技術の研究所への就職が内定したところで、父から「会社に入ってくれ」と言われる。「もっと早く言ってくれよと思いましたが、のんきな学生ということもあり、職業に関してそんなにちゃんと考えているわけではありませんでした。結局、父に言われるまま、1973年に堀田カーペットに入社しました」(堀田会長)。
入社して分かったのは、創業から11年たっていた堀田カーペットの経営が火の車だったということ。「当時、十数人の従業員を抱えていましたが、経営はずっと自転車操業です。ものづくりは設備投資が必要ですから、利益を出すまでに時間がかかるんですね。初めて貸借対照表を見て、会社を経営するというのは大変なんやな、と思いました。2~3年働くうちに、会社の事情がより詳しく分かってきて、これは何とかしなければまずいなと思いました。もっと営業をせなあかん、もっといい製品を作らなあかん。とにかく会社をつぶさないために、急務の課題一つひとつに取り組んでいきました」と堀田会長は振り返る。
当時、大手メーカーからの下請け業務がメインだった堀田カーペットの起死回生の方法は「脱下請け」だと堀田会長は考えた。しかし、それは一朝一夕にできるものではなかった。
「その頃、一般家庭の多くが部屋にウールのカーペットを全面施工していました。ですから、当社の主力製品は一般家庭用のカーペットでした。作れば売れるという時代で販売面ではあまり苦労はしませんでしたが、ブランドメーカーへの卸売価格が安く、利益が出にくいというのが問題でした。だから、利益率を上げるには付加価値をつけた自社製品を売り出すことが大事だと思ったんです。ただ、下請け業務をまったくやめてしまうと、売り上げが急減して会社はつぶれてしまいます。下請け業務を維持しながら自社製品を作り、自ら営業して販路を開拓していかなければなりませんでした」(堀田会長)

堀田カーペットが作る、ウール素材のカーペット
ここから堀田会長は、ホテルや飛行機、自動車、人工芝、電車など、さまざまな用途に向けて営業をかけて、販路を拡大していった。「ものづくりの本質は、気付きを与え、ないものを提供し、困っていることを解決することです。耐久性が必要な用途には、それを重視した製品を製造するなど品質にこだわり、とにかく他社がやらないことをやろうと必死でした」と堀田会長は話す。
地道な営業と高い品質が認められ、1983年には東京の一流ホテル、オークラの大宴会場「平安の間」に敷くカーペットを受注した。「オークラへのカーペット納入会社としては新参者なので、最初は一般フロアの2フロア分しか任されませんでした。しかし、納入後3年くらいしたときに、オークラの担当者さんに、他の会社のカーペットは時間がたつとかなり伸びてしまうけれど、堀田カーペットの製品は、その半分しか伸びなかったとほめていただきました。このように品質が評価された結果、ホテルでは大事な施設である大宴会場『平安の間』のカーペットを納入するチャンスをいただいたのです」と堀田会長は胸を張る。
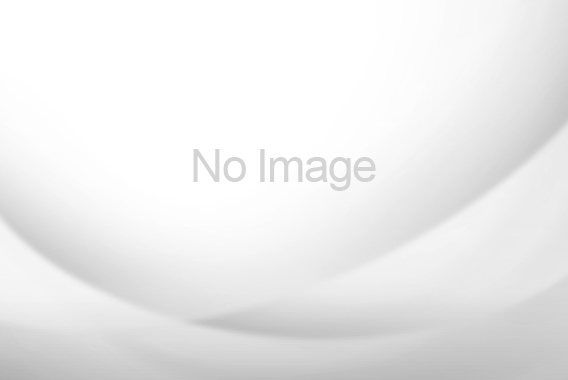
堀田カーペットの製造工場。50年ほど前に日本で生産されたウィルトン織機を何度もメンテナンスをしながら大切に使用している
1998年、「Jフリーズ」というカーペット用の糸を開発し、たくさんの特許の中でもこの特許取得は堀田カーペットの立つ位置を決めるものとなった。これは現在のレギュラー商品にも使われている。
堀田会長の努力の結果、入社時には1億数千万円だった売り上げが1990年には10億円にまで成長した。しばらくは専務の立場で、父と二人三脚で経営を続け、1991年に社長に就任、事業承継を果たした。
父親から引き継ぎ、軌道に乗せてきた会社の後継者について、堀田会長はどのように考えていたのだろうか。「営業担当がいるわけではなく、社員のほとんどが職人。社員の中から、財務や経営にたけ、社長が務まる人材を選ぶのは難しかった。もし息子が継がなければ、会社を畳もうとさえと考えていました。会社の将来に関しては、息子に引き継ぐか、会社を畳むかの二つの選択肢しか考えていませんでした」と堀田会長は話す。
2005年頃から、堀田会長は会社の行く末を考え始めた。当時は赤字経営から抜け出し、無借金の状態だった。「このまま畳むことはできる。ただ、30人程度の社員を抱え、彼らの生活も考えなくてはならい。当社をひいきにしてくださるお得意さまもいる。どうすればいいものか……と悩んでいた」という。そんな心境で2006年には長男の将矢氏に「後を継ぐか継がないか決めてほしい」と電話をした。将矢氏はその電話では即答せず、「考えさせてほしい」と答えたという。
将矢氏は1978年に長男として生まれた。物心ついた頃から、自分の家業はカーペットメーカーだという意識を持っていたという。「カーペット製造という家業に関しては、どちらかというとポジティブな印象を持っていました。ただ、父から後を継げと言われたことはなかったし、自分が社長になるなんて子どもの頃はほとんど意識していませんでした。というより、何も考えていなかったんですよ。祖父母からはよく『3代目』と言われていましたが、当時はその意味もよく分かっていませんでしたね」と将矢氏は振り返る。
北海道に住んでみたいという理由から北海道大学に進学し、卒業後はトヨタ自動車に就職した。調達部でガラスやゴム製品のバイヤーを担当。世界中で製造されるトヨタ車の部品の価格や発注先に関与するグローバルな仕事だった。そんなやりがいのある仕事をしていた将矢氏に堀田会長から承継の意思を確認する電話があったのは、入社から6年たった頃だった。

堀田会長(写真左)と長男の将矢氏。会長は「息子が会社を継がないなら畳むことも考えていた」と言う
「突然ではありましたが、自分には家業があると分かっていたし、どこかのタイミングで継ぐのかもしれないという思いはありました。トヨタの仕事は面白くやりがいはありましたが、この先30年を想像したときに、このままトヨタで働くイメージが湧かなかったんです。サラリーマンだと出世にも限界があります。あとは、身近に育った家業に対してポジティブな印象を持っていたのも大きいですね。さすがに即答はできませんでしたが、きちんと考えて戻ろうという決断をしました」(将矢氏)
実際に将矢氏が入社したのは2008年。29歳だった。堀田会長は将矢氏の決断について、次のように語る。「家業を継ぐには、大きな覚悟が必要です。2008年頃はちょうど業界でも変化が起きていて、カーペットの市場は縮小していました。しかも広い面積に敷きつめるカーペットも、当社が得意としていたロールタイプではなく、タイルタイプの製品が主流になりつつありました。難しい経営環境ではあるけれど、覚悟を決めたのならやってみたらいい、という思いで、迎え入れました」
しかし、大企業のトヨタ自動車から従業員30人の堀田カーペットに入社した将矢氏は、そのギャップに苦しむ。「今思えば、自分自身は未熟だったと思いますが、当時は、とにかくいつもイライラしていました」と将矢氏は振り返る。次回、後編では、そんな将矢氏に、堀田会長が事業を承継したプロセスについて紹介する。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際