
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
エビス(足袋の製造・販売)
事業承継のヒントを紹介する連載の第41回は、「ゑびす足袋本舗」のブランドで足袋を製造するエビスのケース。1861年創業の老舗企業だが、5代目社長時に倒産の危機に陥った。5代目社長の娘で6代目として経営を引き継ぎ、同社を立て直した白記澄子氏の話をもとに後継者の立場から見た事業承継のポイントを探った。
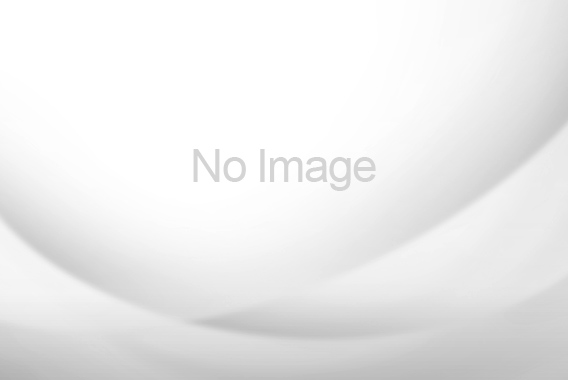
白記澄子(しらき・すみこ)
1973年大阪生まれ。神戸芸術工科大学を卒業後、広告制作プロダクション、博報堂を経て独立。2014年にエビスに入社し、6代目社長となる
ゑびす足袋本舗は、江戸時代末期に福田正三郎氏が大阪で装束商「たちばな屋」を創業したのが始まりだ。以来160年にわたり、足袋メーカーとして足袋の製造・卸を展開してきた。個人商店を法人化したのは戦後間もない1947年12月、3代目の福田冨久蔵氏の時代だ。冨久蔵氏は、親の急死と戦争で兄弟を亡くしたことにより、大阪大学を中退して家業の足袋屋を継いだという。
「他社とは違う、いい足袋を作らなければ、生き残っていけない」と考えた冨久蔵氏は、まだ「人間工学」という考え方がほとんど浸透していなかった時代に、人間の足に合った、体に負担のかからない足袋作りをめざし、研究に力を入れた。型と生地を徹底的に見直して開発した足袋が、今のゑびす足袋本舗の足袋のベースとなっている。
「当時は綿かナイロンの足袋しかなかったと聞いています。そして、正式な場にはやはり伝統的な綿がふさわしいとされていました。しかし、ナイロン足袋は伸びるのでシワが出にくく、サイズの違いによる痛い思いもありません。さらにサイズ展開が少ないため、専門店の在庫数が少なくて済みます。一方で綿は0.5センチ刻みで、細型・ふつう型・ゆったり型など多くの在庫が必要になります。このため、ふつう型の綿足袋の4サイズくらいと、ナイロン足袋を在庫に持たれるケースが増え、正式な場所でも履けますよと間違った案内をされるケースも出てきています。また、着物を購入していただいたからと安価で粗悪品の足袋をプレゼントされたり、ワゴンの安い足袋でお客さまを引き込む材料にしたりする場面も増え、足袋は痛いものだ、足に合わなくて当然だという認識が常識になってしまいました」(白記社長)
さらに、「ナイロン足袋は滑るため足への負担が大きい。靴ならかかとがありますが、草履の場合はありません。それなのに滑りやすければ、ずっと足に力を入れておく必要があります。また、正絹に比べ強度があるため着物を痛めてしまい、安物買いの銭失いだ」と白記社長は説明する。こうした問題を解決するために冨久蔵氏は研究を重ね、綿でありながら伸縮性があり、足に負担のかからない足袋を完成させたのである。

ゑびす足袋本舗こだわりの、伸びる綿足袋。3代目の福田冨久蔵氏が開発した
冨久蔵氏は白記社長にとって母方の祖父になる。一緒には暮らしていなかったが、「年始に社長の家に集まり新年の挨拶をし、社員がおとそを飲み、折り詰めを食べるというのが恒例でした。孫である私も端で食事をしていたので、社員さんたちと年に1度は顔を合わせていた」と話す。
「私が知る祖父は“やさしくて面白いおじいちゃん”でした。社交的で明るく、とにかく好奇心旺盛。70歳を過ぎてパソコン教室に通ったり、カラオケ教室に通ったりしていたのを覚えています。また、白髪でしたがパーマをかけていて、ちょうネクタイにステッキを持って歩く、ハイカラなおじいちゃんでした」と白記社長は振り返る。
しかし、経営者としては厳しい一面も持っていた。白記社長がエビスに入社した後、祖父の時代を知る職人から、「経営者としての冨久蔵氏は、足袋作りに関して一切の妥協を許さない、厳しい人だった。『これでいいだろう』と作った足袋を見せても、何度もやり直しになり、なかなか認めてもらえなかったときもある」というエピソードを聞いた。
そんな冨久蔵氏には息子がいた。ゆくゆくは後を継いでほしいと考えていたそうだが、息子も冨久蔵氏と同じように理系の道に進み、研究職に就いた。そこで冨久蔵氏は、長く働いていた社員の1人を4代目社長に任命した。その社長の時代に、会社の資金の横領事件が発覚した。
この一件から、信頼できる身内から後継者を選ぶしかないと考えた冨久蔵氏。白羽の矢が立ったのが、娘婿である白記社長の父親だった。白記社長の父親の実家は鉄鋼業を営んでおり、次男だった父は兄と一緒にその会社で働いていた。しかし、その業績は低迷していたという。そんなときに冨久蔵氏から誘われ、白記社長の父が5代目に就任した。しかし、この事業承継により、ゑびす足袋本舗は苦境に陥ることになった。
父親が社長に就任したのは、白記社長が大学生のときだった。白記社長はすでに実家を離れて暮らしており、妹が父の社長就任と同時にエビスに入社したため、「父親の後は妹が継ぐだろう」と考えていたという。
白記社長は大学を卒業後、広告デザインのプロダクションを経て、広告業界大手の博報堂に入社し、デザイナーとして働いた。30代には独立し、大手企業の広告を手掛ける一方で、中小企業のブランディングにも力を入れていた。祖父母が病気で倒れたのをきっかけに大阪に拠点を移し、東京・大阪を行き来しながら働いたという。成果を出し、クライアントにも信頼され、仕事は順調だった。
そんな生活が、母からの1本の電話をきっかけに一変する。「長く担当していた税理士をお父さんが辞めさせたらしい。どうも会社がうまくいっていないみたい。ちょっと様子を見て来てくれへん?」。
そこで白記社長は知り合いの税理士を連れて、父親の元に訪れた。すると父親は一言、こう言い捨てた。
「もう、やめますねん」
白記社長は驚き、「これまでゑびすの足袋を買ってくれていたお客さまはどうするの?やめるに当たって、愛用いただいていた得意先やお客さまが困らないために、何か方法は考えているの?」と聞くと、「そんなん、俺は知らん」と言う。江戸時代から続き、祖父が努力して大きくした会社に泥をかけてやめるつもりなのか、と白記社長はあわてた。
父が継いだ頃に働いていた営業社員は、祖父が作った靴下会社を分社化したタイミングで移ったため、足袋業務のエビスに残ったのは、祖父の時代から働いている80代を超える社員3人だけ。足袋の製造を続けてはいたものの、営業活動をほとんどしていないため、新規の受注は増えない。当然、売り上げは右肩下がりだった。
税理士と一緒に財務状況を見ると、想像以上にひどい状況だった。「辛うじて借金はなかったけれど、会社のキャッシュはほぼ尽きていました。」(白記社長)。
商品はいいものを作り続けていたので、白記社長は「本当に廃業しないといけないのか、立て直せないのかを見極める必要がある」と考えた。
白記社長は独立後、大手企業の企画やデザイン業務以外に、中小企業のサポート・プライベートブランドの立ち上げのプロデュースをなりわいとし、他社を立て直すことに成功していたため、「家業を見ないままのれんを下ろすのは後悔するような気がした」と話す。
2014年に入社し、エビスの6代目社長に就任しながらも、これまでの自分の本業とエビスの仕事を掛け持ちする形で、準備も全くなしの事業承継に挑む白記社長の闘いが始まった。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際