
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
SNSなどに架空の投資話を掲載して、金銭などをだましとるSNS型投資詐欺が増えている。警察庁発表では、2024年1月から6月の被害発生数は総数で3570人に上る。男性ではLINEやFacebookからの接触が多く、女性ではInstagramが多い。有名人をかたった「なりすまし詐欺」で被害に会うケースもある。なぜこうした事態になっているのか。詐欺の実態と背景、とるべき対策について考えてみたい。
例えば、ある60代男性のケースでは、インターネット上の有名人が投資を勧める広告をクリックしたことが発端だったという。有名人を自称する者とSNSのアカウントを交換するとアシスタントが紹介され、投資話についてやりとりが始まった。
勧められるままに投資用の専用サイトを開設して、指定された口座に入金すると、専用サイト上で運用利益が上昇していく。「もっともうけられる」と唆されて要求に応えていった結果、合計で6300万円がだまし取られてしまったという。なりすまし詐欺では、有名な実業家など、事業の成功者や経済に強いと思われる有名人になりすまして投資話が持ちかけられてくる。海外では大富豪になりすましたケースもある。
今、なりすまし詐欺では生成AIが使われることも増えているのも大きな懸念材料だ。本物そっくりの偽の動画や音声を生成して、なりすまされると見抜くことが難しい。実際にディープフェイクを使って、海外ではある企業のCFOになりすましてテレビ会議に現れ、会計担当者に40億円を送金させた事件も起きている。
この他にも、なりすましサイトに誘導されたり、偽メールをクリックしてマルウエアを送り込まれたりして、金銭や個人情報を盗まれるといったケースは後を絶たない。急増しているのが現状だ。
こうしたなりすまし詐欺への対策としては何が考えられるのか。まず電話やメールなどの発信元が本物かどうかを確認することだ。有名人であれば公式アカウントからの発信情報などを確認しよう。有名人が無料の投資教室などを運営することは基本的にはあり得ない。裏をとることが肝心だ。
自社サイトへと誘導しようとする企業の場合も、本物かどうか確認する必要がある。国税庁の法人番号公表サイトでその法人が実在するかどうか確認できるし、金融商品取引業者であれば、金融庁のサイトで登録業者かどうかをチェックできる。無登録業者との取引はリスクが高いので避けることだ。
「必ずもうかる」「あなただけ」といった甘い誘い文句は危険が一杯だ。そんなもうけ話があったら誰でもやっているし、そういう話は存在しないと考えた方が良い。金融庁では「未公開株」や「新規公開株」などの詐欺的な投資勧誘話への注意喚起を促している。信頼できる証券会社など以外では取引するべきではないだろう。
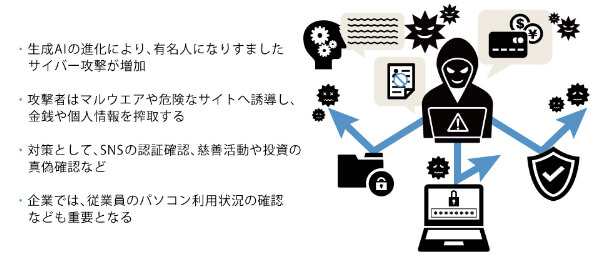
架空の暗号資産への投資や偽物の投資アプリを使った詐欺も増えている。投資したりインストールする前に、インターネットでの口コミを調べるのは当たり前だと心しておくべきだ。それでも巧妙にわなを仕掛けてくるので、振込口座に不審な点がないかどうかなど、常に警戒心を持っておくことが望まれる。
企業であれば従業員のサイト閲覧やメールのやりとりにも警戒したい。パソコンの利用状況を把握し、全てのログをとって不審な点があれば管理者に通報する仕組みなども必要になる。標的型攻撃や不正アクセスを監視するソリューション、従業員向けの訓練を導入するのもお勧めだ。ソリューションと人材教育の合わせ技で臨もう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=高橋 秀典
【MT】
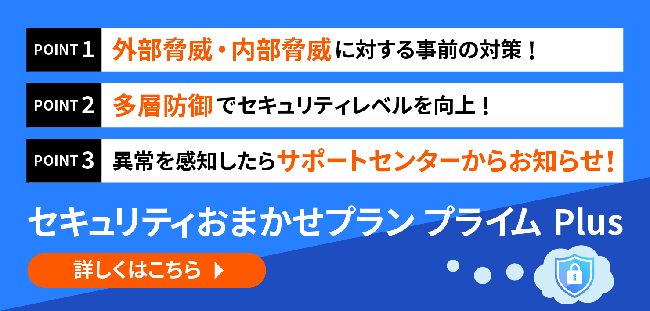
強い会社の着眼点
審査 24-S1007