
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
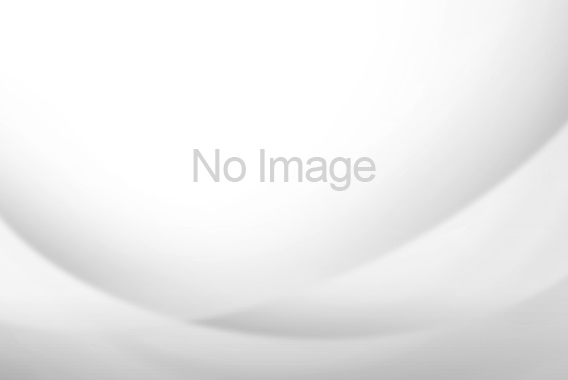
第21回から第5ステップ「事業戦略を立て直す」を説明しています。事業戦略を立て直す方法として、第21回にアプローチ11「大口取引よりも、小口取引」、第22回と第23回でアプローチ12「作業平準化のビジネスモデル」を解説しました。今回は3つ目のアプローチ13を紹介します。
お客さまの要求に現場で応えていくのがサービスなので、サービス業はお客さまがいなければ成立しません。従って、何か商売を始めようと思ったとき、どのような人がいて、その人たちが何を求めているのかを考えなければなりません。
人が外出先で空腹を感じたとき、その人は空腹を満たすために「何か食べたい」と思うはずです。しかし、そこで食べたいものがあっても、たまたま持ち合わせているお金が少なければ食べられない場合もあります。また、どんなに食べたいものがあるからといって、人はどこまでも移動できません。つまり、何かしたいと思っても、現実的な「制約」を考慮して、限られた選択肢の中から最適なサービスを選択しているのです。
一方、サービスを提供する側も、何か商売をしたいと思っても何でもできるわけではありません。店を構えると、その後何かあっても簡単には移動させられません。また、従業員の人数やスキルはサービスの内容や品質を決め、店舗面積は最大客数を決めます。会社側も「制約」の中でサービスを提供しています。
つまり、そこにいるお客さまの制約が潜在的な要求をつくり、それを受けて提供すべきサービスの内容や規模が決まってしまうのです。さらに、そこにいるお客さまが時代の流れの中で変化していくと制約も変わっていき、それによって要求も変化します。そうなると、これまで提供していたサービスの内容を変えなければならなくなります。
製造業は、場所がどこであっても同じ商品を作れるため生産の立地の制約をほとんど受けません。ただ、どこで作っても同じなので、大変厳しい国際的市場競争にさらされます。
お客さまありきのサービス業は、お客さまがいるところでしかサービスを提供できないため、製造業のように国際的な市場競争にさらされないというメリットがあります。しかし、そこにいるお客さまが変わっていけば、サービス内容もそれに合わせて変えていかなければならない厳しさがあります。
顧客の変化に合わせてサービス内容を変化させた実例を紹介しましょう。芳野病院は北九州市若松区にある中規模病院です。1913年に故・芳野三郎氏が開業した頃は性病治療もする診療所でした。当時の若松は石炭の積み出し港として栄えており、国内外の船員や港湾労働者で花柳界は賑(にぎ)わい、性病患者も多かったからです。
二代目院長の故・芳野敏章氏が後を継いだのは1957年。高度成長期の北九州地区は工業地帯となり、人口が膨らみました。敏章氏は外科、脳神経外科、内科、整形外科、循環器科、産婦人科と診療科を広げ、病床数も20床から161床にし、総合病院に転換しました。
1997年に現院長の芳野元氏が3代目に就くと、今度はリハビリテーションにかじを切ります。背景には産業構造の転換に伴い、急速に進み始めた周辺地域の高齢化問題がありました。若松区周辺には救急車で運ばれてくる重症患者を受け入れる大型の急性期病院が多数ありました。そこで中規模の芳野病院に求められる役割は、大型病院の後方支援病院として、急性期治療を終えた高齢者を日常生活に戻すことだと位置づけたのです。
そこには「欧米の病院と比べて、日本の病院のリハビリ部門が見劣りしており、いずれその重要性が高まる」という元氏の市場環境の変化に対する先見もありました。こうして、在宅復帰を支えるリハビリ施設と専門スタッフを充実させていったのです。今では理学療法室、作業療法室、言語療法室などを設ける一方、肺炎予防や食欲増進のため、歯科衛生士による口腔(こうくう)ケアにも力を入れています。リハビリ専門スタッフは60人弱。一人ひとりが多様な技術を身に付け、回復期リハビリ病棟の在宅復帰率は全国平均約70%に対し、芳野病院では85%を超えています。
また、訪問リハビリテーションの他、認知症高齢者用のグループホーム施設、住宅型有料老人ホームも設立し、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らせるように事業を横展開しています。こうした取り組みが評価され、最近は地域包括ケアの先進病院として、全国から連日のように視察者が来るまでになりました。
芳野病院は、時代の流れの中で地域住民の要求がどこにあるのかを常に見定め、小さな診療所を総合病院に、さらにそれをリハビリに特化した病院へと業態を変えてきました。芳野病院は自分たちがしたいこと、してきたことを続けませんでした。まず地域住民ありきで、それを制約にして自分たちのサービスの内容や提供方法を変化させてきたのです。
多くの会社はこれまで、業務改善を通じて生産性を向上させてきました。この手法の重要性は言うまでもありませんが、それに加えて芳野病院では、あえて潜在的なお客さまとなる地域住民の要求にサービスの内容を合わせ、生産性を上げてきたのです。
芳野病院がリハビリ部門の強化を始めた90年代は「リハビリ治療は医者のすることではない」という見方をする医師が多かったそうです。それでも元氏は、地元の高齢患者と対話する中から、在宅復帰の支援こそ地域で求められていると確信し、病院の中身を変えたのです。
執筆=内藤 耕
工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。
【T】
中小サービス業の“時短”科学的実現法