
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
世の中は「時短」という言葉であふれ返っています。新聞でもテレビでも、会社でも家でも、時短という言葉を聞かない日がないほどです。
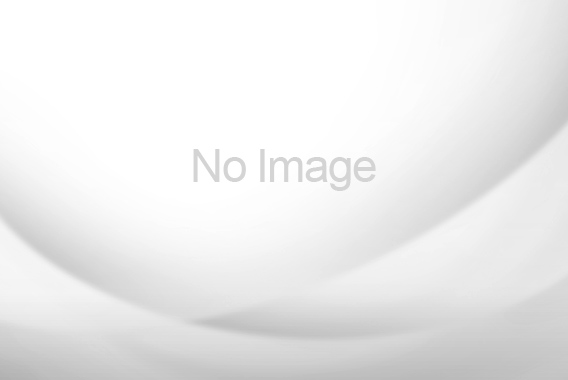
ただ、どうすれば時短を進められるのかが分かっておらず、にっちもさっちもいかない会社が多いように思います。現場を回ると、総論として時短を進めることに異議を唱える人はいませんが、個別の議論になると難しい問題がたくさん出てきて、結果として時短が進んでいないのが実態です。
経営における短期的な優先事項は、売り上げや利益の確保です。当たり前のことですが、会社を存続させるにはある一定の固定的な経費があって、それをまかなうだけの売り上げがなければ、会社はあっという間に倒産してしまいます。だからこそ、経営者は何が何でも売り上げを立てようと、日々、従業員と共に奔走しているのです。
一方、時短を進めようとするとき、最も手っ取り早い方法は何かというと、残業の削減です。残業とは、従業員が働かなければならない基準を超えた時間です。そもそも基準を超えているのですから、会社が従業員の長時間労働を解消して時短を実現しようと思えば、まず「残業を減らせ」という号令をかけるのは一見合理的に見えます。ただ、時短を推進する担当部署は、普通は人事部門。会社がまず確保しなければならない大事な売り上げに直接的な責任を負っていない、いわゆる間接部門です。
実際に生産活動を担っている現場の従業員からすれば、時短のために「残業を減らせ」と人事部門から言われても、何だか絵空事のように感じてしまいます。「減らせ」と言われる残業には仕事がひも付き、その仕事の向こうにはお客さまがいる。そしてそのお客さまが代金を支払ってくれるから、会社は売り上げを立てられるのです。
だから、「残業を減らせ」と言われると、「じゃあ、売り上げが減ってもいいのか」と言い返したくなります。人事担当や経営者は売り上げが減っては困るので、「仕事をやり繰りして、何かとかうまくやれ」としか言えなくなってしまう。このような不毛なやり取りがもたらすものは、サービス残業です。
お客さまに迷惑はかけたくない。残業削減は会社の至上命令になっている。間に挟まれた従業員は、仕事を家に持ち帰って対処する。よって、残業時間だけが減って従業員の実質的な収入が減るという深刻な問題も引き起こし、従業員の意欲減退は避けられません。働き方改革を進めたら、サービス残業がこれまで以上に横行するというのは皮肉な展開です。
ここで改めて問いたいのは、本当に時短を進められないのか、ということです。会社にとっても従業員にとっても、さらにお客さまにとっても、負担や迷惑をかけない時短の方法は本当にないのか。
さらに欲張れば、時短を進めながら、会社はその目的である売り上げや利益を伸ばして成長し、従業員は収入を増やし、お客さまはよりよい商品やサービスを得られれば最高です。「そんな虫のいいことなんてできるはずがない」と誰しも今は思っています。でも、本連載はそこを考えていきたいのです。
売上高や利益額を少なくとも維持しながら時短を進めるためには、現在と同じ仕事量を残業せずにこなさなければなりません。それはつまり、同じ仕事量を今より短い労働時間でできるようにすることです。これがいわゆる「生産性向上」です。時短のかけ声と共に、生産性という言葉も頻繁に耳にするようになったのは、このためです。
しかし、この10年以上、国も会社も「時短だ!」と叫びながら、この時短という言葉が一向に消えていかないのは、生産性向上の方法論が確立できていないことの証左です。経営者にやる気が見られないとか、現場の店長がサボっているからとか、そういうことではなく、生産性向上の方法、時短のアプローチが誰も分からないのです。
特に、長時間労働で深刻な問題を抱えているのがサービス業です。サービス業、もしくはサービス産業と言ったほうがいいかもしれませんが、それは非製造業全般をさしており、卸売り、小売り、宿泊、飲食など多様な業種を幅広く含みます。現場ではたくさんの女性が働いています。育児などをしながら働く場合も多い女性にとって、長時間労働は到底受け入れられません。女性活躍の観点からも、サービス業の生産性向上はとても重要なのです。
ただし、サービス業の現場は、お客さまありきで動いています。そのお客さまは「気まぐれ」で、製造業のように見込みを立て、計画的に仕事を進められません。気まぐれというのは、「いつ来店するか」「何を求めるか」を正確に予測できないということです。
さらに、サービス業を営んでいる会社は大半が中小零細で、地方で商売をしています。大企業の生産拠点の多くは海外に移ったため、地方の主役はサービス業です。そして、小さなサービス業の現場を支えているのは、経験を積み上げてきた「職人」とも呼べる人たちです。飲食店の料理人や接客係、食品スーパーの店員、生花店や眼鏡店のスタッフ、理美容師や薬剤師などをイメージしてもらえばよいと思います。
彼らはただでさえ、長時間労働で忙しく働いています。しかも、店舗間の競争が激しくて、お客さまのためにもっとよいサービスを提供しなければならない。それなのに、何だかよく分からない生産性向上について「勉強して、工夫しろ」と言われても、そんな余裕はありません。
執筆=内藤 耕
工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。
【T】
中小サービス業の“時短”科学的実現法