
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
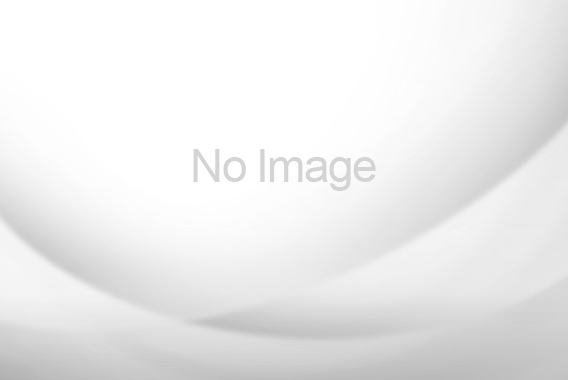
今回は、第3回で紹介した「第1ステップ、アプローチ1 プロット分析」の続きです。前回の最後に、平日と週末の2パターンでシフト編成している会社の例を紹介しました。
客数が少ない平日でも出勤者数はほぼ固定されているので、現場の業務量が減って手待ち時間が増えても、従業員は何も言ってきません。客数が少なければ売り上げも減少しますので、労働投入量が固定されていれば、この現場の生産性は低下していることになります。
反対に平日でも客数が多い日があるでしょう。そのような日は現場の従業員は忙しく、人手不足と感じ、会社に不満を訴えるかもしれません。経営者は「忙しい日」を気にして生産性を上げようとするケースが多いのですが、私は「暇な日」の生産性に関心を持つべきだと指摘しているのはこのような状況があるからです。
「ギリギリの人数だと、お客さまからクレームが出ます」。経営者がシフト編成をするときに、作業量に応じて投入人数を最適化しようとすると、現場からたびたびこのように言われます。おそらくそれを言われた側も何となく納得してしまい、固定的な人員数が多くても仕方ないと思ってしまいます。
これに対して、「実際に現場で何か問題が起きたのか」「お客さまから具体的なクレームや不満が出たのか」と聞いても、きちんとした回答は戻ってきません。現場では、このように感覚的な議論が具体的な根拠もなく進められているのが多くの会社の実態で、これが生産性向上を阻み、時短の障害になっているのです。実はある会社で業務量とミスの数を調べたところ、逆相関になっていました。つまり暇なときにミスが多く、忙しさが必ずしもミスの原因ではないのです。
もし、客数200人を従業員20人で対応して現場が問題なく回り、お客さまも不満を感じていなければ、少なくとも20人以上の投入は過剰になります。その生産性をもってすれば、客数が400人、500人の対応も、もしかしたら25~30人程度の投入で十分で、それ以上の人数の出勤は必要がないのかもしれません。この現場は人手不足どころか相当な人余りの様相を呈していて、言い方を変えれば時短の余地、投入人員の削減余地がいくらでもあります。
投入すべき従業員の適正人数を感覚的に決めるのではなく、あくまでもデータとその検証を基に科学的にシフトを管理すべきです。一瞬の忙しさから従業員が「人手不足です」と言ったため、それを検証せずに人を増やしていくとどうなるでしょう。忙しい時間帯は問題なく仕事を回せるようになりますが、ピーク前後の手待ち時間をそれまで以上に持て余し、少しの忙しさでも「人手不足状態だ」と感じてしまうかもしれません。
人手不足を「人の補充」で解消すると、一般に繁閑の差が大きいサービス業の現場ではどんどん人が増えていきます。そうではなく、「必要な労働量」という視点を持たなくてはいけません。先ほどのプロット図で、客数が200人を下回ったときも投入人員が最低20人に固定されていましたが、客数が100人ならば、生産性から計算される業務量は理論的に半分のはず。そして実際に10人にするには、客数が少なくなってもやらなければならない業務の割り振り、つまりマルチタスク化が必要です。
このように現場を必要な労働量という視点で見直していくと、業務分担の固定化が実は問題だと気がつく場合が多い。もし同じ業務を半分の人手でこなそうとすると、言われなくても現場は作業分担を見直し「一人二役」で働きます。会社が指示しなくても勝手にマルチタスクで働くようになるのです。
マルチタスク化は低稼働時に大きな効果を発揮し、それによって総労働時間が減って時短も進められ、より多くの休日を与えられるようにもなります。結果として、会社は生産性を上げられるのです。だからこそ、必要な労働量を抽出する上で、プロット分析のような手法が不可欠なのです。
ここで例示したプロット図の会社が特殊な現場なのかというと、そうではありません。私はさまざまな業種でこのプロット分析を実施していますが、ほぼすべての現場で、労働投入量の大きなばらつき、高い固定的投入量という傾向が出ています。人件費は会計学では固定費に分類されます。これは人件費を年間合計で見ているからです。もし日々の業務量に合わせて労働投入量をしっかりシフトに反映させていけば、固定費である人件費をシフトによって変動費的に扱えます。
山梨県の「石和健康ランド」(運営はクア・アンド・ホテル)でも、このプロット分析を使って配置人員を適正化してきました。2013年に人員シフトの見直しをはじめとする現場改革をスタートさせ、翌2014年度の総労働時間は前年度比95.0%、さらに2015年度は同94.7%と減っていきました。
もともと、石和健康ランドのシフト編成は単純でした。同施設は24時間営業で、風呂とサウナをメインに飲食やカラオケ、マッサージ、散髪、アミューズメント、宿泊などのさまざまなサービスを館内で提供しています。以前は部署ごとに「早番」「遅番」「深夜番」の3種類のシフトで営業していました。例えば、「フロントの早番は午前○時出社、午後○時退社」「風呂場の遅番は午前○時出社、午後○時退社」という固定化されたシフトで、団体予約が入るなどお客さまが増えると分かっても、出勤人数を増やしていませんでした。
「お客さまが多かろうが少なかろうが、基本的にシフトは同じでした。定められた休憩時間になれば、仕事が忙しくても休憩に入る。逆にお客さまが少なくて暇を持て余していても、特に何かをしなければいけないとも考えない。そんな職場でした」。同施設を経営する、クア・アンド・ハウスの荒井清隆取締役はそう苦笑いしました。
執筆=内藤 耕
工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。
【T】
中小サービス業の“時短”科学的実現法