
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
大企業のサプライチェーンにサイバー攻撃が広がる中、中堅・中小企業にとってもセキュリティインシデント(情報セキュリティに関連する事故)はいつ起きてもおかしくない状況にある。しかし、「対岸の火事」のように受け止めている企業も多いのではないだろうか。こうした心構えだと、いざインシデントが発生した際に、対処が後手にまわって被害が拡大する恐れもある。では、具体的にどんな対応を考えておく必要があるのだろうか――。転ばぬ先のつえとして考えておくべきことをまとめてみた。
ビジネスのデジタルへの依存度が高まっている今、セキュリティインシデントはどの企業にとっても大きな被害につながる恐れがあり、インシデント対応を怠った場合、経営者には法的責任と社会的責任が問われることもある。
具体的には、インシデント発生時に取締役などの責任ある立場の者が事態収拾に対して善処しなかった際には、善管注意義務違反による法的責任や損害賠償を求められる可能性がある。また、サプライチェーン攻撃によって周囲に被害が広がり、さまざまなリスクの拡散はもちろん、営業機会の損失やイメージダウンをもたらし、売り上げの低下やさらには企業としての存続の危機に直面する場合もある。
サイバー攻撃によって想定される代表的なインシデントとしては、(1)情報の漏えいやデータの改ざん、(2)データそのものの破壊や消失、(3)情報システムの機能停止などがある。特に近年、データを暗号化してシステムが使用できない状況を作り出し、復旧を条件に身代金を要求するランサムウエアの攻撃も増えている。
警察庁サイバー警察局が2025年9月に発表した「令和7年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると攻撃手法も巧妙化し、データの暗号化に加えて機密情報の窃取も行い、身代金を支払わない場合はデータを公開すると脅迫する二重恐喝も横行している。こうした攻撃は企業活動に深刻な打撃を与え、対応を誤ると事業継続すら危ぶまれる事態に発展する可能性もある。
これらインシデントによる被害は、時間が経過すると連鎖的に拡大する可能性がある。例えば、データ流出量が増大し、機能停止に追い込まれるシステムが増加すれば、事業停止による機会損失が増大していく。このため、被害を最小限に抑えるために適切な対応が欠かせない。具体的な対応としては、次の3つの段階に分けて実施することが望ましい。
1. インシデント発生時の検知と初動対応
2. インシデントの報告と公表
3. 復旧と再発防止
また、企業は適切な情報セキュリティ対策を確立した上で、これらの段階を踏んで対応する必要がある。まず、インシデントの検知は以下のような方法で行われる。
・導入されているウイルス対策ソフトやネットワーク監視ツールからのアラート
・セキュリティベンダーからの通知
・取引先や顧客など外部からの通報
次に情報セキュリティ責任者は、検知した内容を経営者に報告し、以下の初動対応を実行する。
・ネットワークの遮断
・感染機器の隔離
・システムの停止
さらに全ての関係者に対してインシデントを報告し、二次被害の発生を防ぐ。この際、被害の内容や状況に応じて、適切な対象者に適切なタイミングで報告する必要がある。併せて、必要に応じて警察や所管の官庁などへの届け出やメディアへの公表も迅速に行う。被害の拡大を防ぐ、という意思をもって素早く必要な対応を最優先で実行するのが基本だ。
セキュリティ担当者は、被害の拡大を防止した後、復旧と再発防止に取り組む。最初のステップは、インシデントの実態を正確に把握するための情報整理だ。システムやネットワークのログを基に、以下の項目を明らかにする。
【整理すべき項目】
・インシデントの種類と内容
・対象事業と責任者、担当者
・被害を受けたシステムの内容や構成
・発覚日時と発生日時
・被害の状況とビジネスへの影響
・対応の時系列での経過
・想定される原因
次に、セキュリティ担当者は原因を究明する。自社の対策で不十分だった点を分析し、具体的な対応策を練り上げ、経営者と共有する。また、今後の訴訟リスクに備え、インシデントに関連する証拠データを保全する。
最後のステップでは、対策を施した上で停止していたシステムやサービスを復旧し、再発防止策を社内に徹底する。これには新たな技術的対応やルールの再策定、従業員教育の徹底などが含まれる。小手先の対策に終わらせず、必要に応じて時間のかかる対応策も断行する必要がある。
ウイルス感染やランサムウエア、情報漏えい、システム停止などインシデントの種類によって整理すべきポイントや対応策は異なる。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「中小企業のためのセキュリティインシデント対応の手引き」などを参考にし、対応が困難な場合は外部の専門家に支援を求めることも検討すべきだろう。
重要なのは、日頃からインシデントの発生を検知する対策を導入し、発生を想定した対応策を用意すること、そして発生時には被害の拡大防止を最優先に取り組み、最後に根本的な再発防止策を講じることだ。セキュリティインシデントは経営リスクであり、経営課題としての対応が求められている。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです。
執筆=高橋 秀典
【TP】
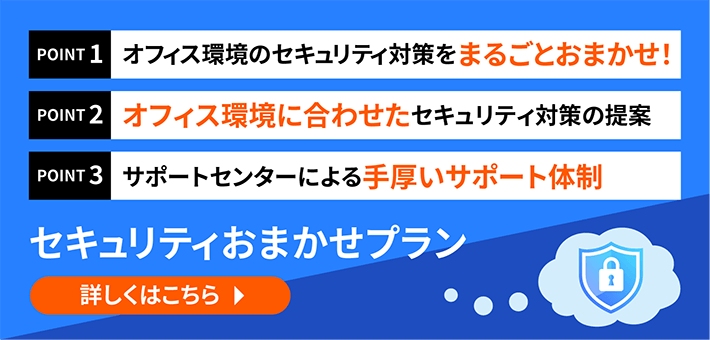
最新セキュリティマネジメント