
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
北星鉛筆(鉛筆の製造・販売)
事業承継のヒントを紹介する連載の第43回は、東京都葛飾区で70年にわたり鉛筆を作り続けている北星鉛筆の杉谷和俊会長のケースの前編。鉛筆の市場規模が縮小していく中で、時代に合った新製品を生み出し、持続可能な会社をめざしてきた杉谷会長。そして2019年、長男の龍一社長に事業承継を果たした。バトンを引き継ぐにあたり、杉谷会長が大事にしたのはどんなことだったのだろうか。

杉谷和俊(すぎたに・かずとし)
1947年北海道生まれ。1952年に家族で上京。1970年、拓殖大学経済学部を卒業後、北星鉛筆に入社。営業部長、専務を経て1994年に4代目社長に就任。2019年に長男の龍一社長に事業を承継し、非常勤取締役となる
北星鉛筆を創業した杉谷家の祖先は徳川幕府に書記(祐筆)としてつかえていたと伝えられている。幕府解体後に職を失い、屯田兵として北海道に渡り、杉谷木材を開業。鉛筆のもととなる板を製造し、全国に販売していた。それというのも、文字として情報を残す仕事である書記を務めていたこともあり、これからは筆に代わる便利な筆記用具として、大量の鉛筆が必要な時代になると察知したからだ。
その後、関東大震災で工場を焼失し、経営に行き詰まっていた東京の月星鉛筆という鉛筆製造会社を杉谷会長の祖父、安左衛門氏が買い取る形で1951年に設立したのが北星鉛筆だ。祖父の後、杉谷氏の父親、叔父とバトンが渡され、1994年から杉谷会長が4代目の社長を務めた。
杉谷会長は物心ついた頃から、鉛筆を製造する家業を見て育った。「われわれが小学校に入る頃がちょうどベビーブームで、最も鉛筆が売れていた時代です。地域の文房具店などの小売店でも鉛筆の売り場が確保され、平積みにしてどんどん売れていました」と杉谷会長は振り返る。
大学時代は中小企業研究ゼミに所属していた。「後を継ぐことを具体的には考えなかったけれど、頭の片隅では意識していたのかもしれません」と杉谷会長は語る。しかし、その頃にはシャープペンシルやボールペンなども普及し、筆記具の多様化が進んだ結果、鉛筆は以前のようには売れなくなっていた。
就職活動の前に父親から「会社に入るか?」と聞かれたとき、杉谷会長は祖父の教えを思い浮かべた。「鉛筆はわが身を削って人のためになり、真ん中に芯の通った人間形成に役立つ、立派で恥ずかしくない商売だから、鉛筆のある限り利益などは考えず、家業として続けなさい」。
「祖父の教えは大切にしたいと思いました。しかし、鉛筆はどんどん下火になります。鉛筆だけで続けていくのは難しい。それでも、いまある土地や工場の機械を使いながら、鉛筆だけにこだわらなければ、バトンをつなげていく可能性はあると考えました」(杉谷会長)。
大学を卒業してすぐに北星鉛筆に入社。まずは現場で鉛筆用木材の板「鉛材の乾燥」板焼の仕事からスタートし、製造、営業など全職場を経験した。
しかし、営業においては、当時のメインの販売先である問屋を訪問しても「もう来なくていい」と言われてしまう始末。「私の顔を見ると、問屋さんも取引縮小を言いづらくなるので、そんな対応になったのだと思います」と杉谷会長は振り返る。当然、鉛筆の売り場はどんどん縮小されていった。
そんな事業環境の中、「どうしたら売れるのだろうか?」と、杉谷会長は試行錯誤を続けた。工場を改善し、生産性アップにも務めた。「祖父がよく言っていました。『自分たちの商売を動物に例えて考えてみなさい』と。鉛筆はウサギのようなもの。軽快に跳ねて時代に合わせて変化していく。もし太って豚のようなウサギになったら、小回りが利かなくなり、他の動物に食べられてしまう。つまり、身の丈に合った大きさで続けていきなさいという意味だったと思います」。
日本の鉛筆メーカーの大手には三菱鉛筆やトンボ鉛筆がある。そうした大手は鉛筆以外の事業を展開したり、海外での製造に切り替えたりしている。国内に200社以上あった鉛筆メーカーは、今や30社ほどに減っている。
そうした中で杉谷会長は、祖父の教えの通り規模は追求せず、身の丈に合った大きさで存続していこうと第一に考えた。そのために、改めて鉛筆、そして北星鉛筆が世の中に提供できる価値は何かを考え抜き、新製品開発に取り組んだ。
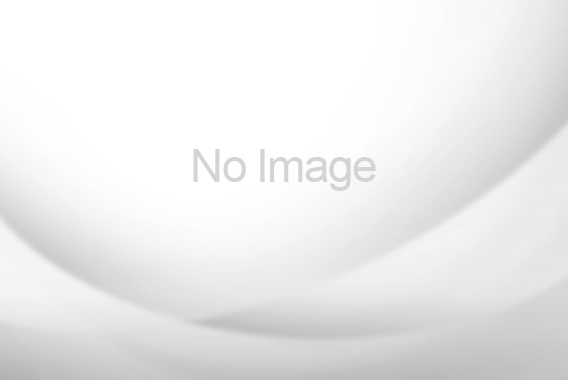
北星鉛筆の主力商品、削らずにシャープペンシルのように書ける「大人の鉛筆」
そして生まれたヒット商品が「大人の鉛筆」シリーズだ。鉛筆の利点は、絶対に書けること。ボールペンやシャープペンシルは、インクや芯がなかったりして書けないときがある。「鉛筆は削られてさえいれば、必ず書けます。だから、選挙の投票で候補者名を書くときは今でも必ず鉛筆が使われるのです」。この利点をヒントに、開発した商品が「大人の鉛筆」シリーズ。これは、シャープペンシルの形で鉛筆の芯を使用し、削らずに書ける鉛筆だ。「うるし塗りの大人の鉛筆」や「大人の色鉛筆」など派生製品も多く開発し、現在同社の人気商品となっている。
「当時は私が社長としてバトンを持っていましたから、バトンを持っている私が生き残っていくための新製品や新サービスを考えないといけません。考えられなくなったら次の人にバトンを渡すべきでしょう。それが、私が考える事業承継です」(杉谷会長)
新製品開発ともう1つ、杉谷会長が力を入れたのが工場見学だ。小売店での販売拡大はもう期待できない。いかに価値を発揮し、地元で存続していくかと悩んだとき、「工場見学で地元の人たちに会社を知ってもらおう」と考えたのだ。
以前から工場見学は実施していたが、ガラス張りにして中を見学できるような作りの工場に建て替え、1989年から本格的に見学者を受け入れ始めた。今では葛飾区から委託され、区内のすべての小学校の児童が見学に訪れている。新型コロナウイルス感染拡大前はタイやインドネシアなど、海外からの見学者も多かったという。工場見学は有料だが、希望者が絶えない。いまや同社を支える事業の1つになっている。
北星鉛筆に入社したときから、杉谷会長は次に渡すバトンについて考えていた。「いくら自分の代に頑張っても、後継者がいなければ意味がありません。自分がバトンを持っている間に、次にバトンを渡す人をつくらなければならないと考えていました」。
杉谷会長は2人の息子と1人の娘に恵まれた。結果的に事業を引き継いだのは長男の龍一社長。しかし龍一社長は、大学時代までは格闘技にのめり込んでいた。「勉強はあまりしていなかったと思いますが、私はそれでいいと思っていました。あまり勉強して優秀になると、別の会社に入ってしまいますから。勉強よりも、体力を養うクラブ活動を楽しんでほしいと考えていました」。
ただ、杉谷会長は自分から龍一社長に「後を継いでほしい」とは伝えなかった。「承継は本人の意思が必要です。こちらがどれだけ後を継げと言っても、本人にやる気がなければ社長業は務まりません。あれをやれ、これをやれと親が言うと、自分では何も考えない、できない子どもになってしまう。あくまで自分で発想し、行動できなければ、次の時代は乗り切れません。われわれの時代の前までは、売れているものを見てまねして作ればそれなりに売れました。でも、われわれの代からは発想の時代ですから。見てまねをするのではなく、自分の発想を商品化してオンリーワンの商品を作らなければ、うまくいきません」。
杉谷会長は、子どもの教育において心がけていたことが1つだけある。「仕事の愚痴を子どもたちの前で言わない。その一方でいかに鉛筆を作るのが楽しいのかは時に口に出して、鉛筆メーカーの社長業に夢が広がるようにと意識していました」。
「これは父を見ていて気付いたのです。私が子どもの頃、父はよく、出張に行った話をうれしそうに話してくれました。出張は楽しいぞ、ホテルが豪華でご飯はおいしくて……と。子ども心に、出張とはそんなに楽しいものなのかと思って聞いていました。実際、大人になって自分が出張に行くと、安宿でそんなにいいものではなかった(苦笑)。そのときに、父がなぜそう言っていたのか、合点がいきました」
仕事の楽しさを伝え、後継者が夢を持てるようにする。その杉谷会長の教育方針の結果、龍一社長は大学を卒業後、北星鉛筆への入社を自ら希望した。杉谷会長と同様、一般社員として現場から働き始めた。
執筆=尾越 まり恵
同志社大学文学部を卒業後、9年間リクルートメディアコミュニケーションズ(現:リクルートコミュニケーションズ)に勤務。2011年に退職、フリーに。現在、日経BP日経トップリーダー編集部委嘱ライター。
【T】
「事業承継」社長の英断と引き際