
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
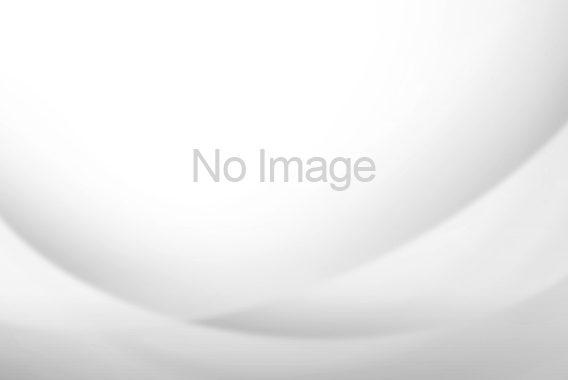
近年、インターネット環境があれば、さまざまなWebサービスを利用できるようになりました。インターネット経由でデータが保存できるクラウドストレージも、その1つです。本記事では、クラウドストレージの仕組みについて紹介します。
ICT総研が2020年6月に公開した「クラウドストレージサービス市場動向調査」によると、国内でクラウドストレージを利用する個人ユーザーは、2018年度で4684万人でしたが、2019年度は4962万人に増加。さらに2022年には5561万人に増加する見込みです。
また、業務で利用しているクラウドストレージに満足している理由の第1位は「データ保存容量の大きさ」。続いて「運営会社が信頼できる」「情報セキュリティが充実している」という結果になっています。
クラウドストレージはビジネス、プライベート問わず、多くの人に身近なサービスになっているといえます。
クラウドストレージは、オンラインストレージとも呼ばれており、インターネット経由でデータが保存できるサービスです。企業での利用においては、業務データの保存や従業員間での受け渡しはもちろん、社外の人とのデータの受け渡しが可能なクラウドストレージもあります。
ここでは、クラウドストレージの仕組みと種類について解説します。
ストレージとは、データの書き込みや読み込みを行う記憶装置です。ストレージの保存形式は大きく3つに分かれ、パソコンやスマートフォンなどの端末に使われる場合もあれば、クラウドに使われる場合もあります。
ファイルストレージ方式
ファイルストレージとは、パソコン内でデータやファイルを保存する方式です。一般的には、WindowsやMacOSなどにも採用されており、多くの人になじみの深い方法です。ファイルストレージは、ファイルを「フォルダ名/ファイル名」のように管理しています。例えば、My Documentsフォルダにsample.docxファイルを保管している場合は「My Documents/sample.docx」となります。
ブロックストレージ方式
ブロックストレージとは、ファイルやデータをブロック上に分解して保管するストレージ方式です。ブロックストレージは、記憶領域を「ボリューム」と呼ばれる単位に分割し、ボリュームを固定長の「ブロック」にさらに分割する方法で管理します。
「ボリューム」と「ブロック」には、特定の番号が振られており、ユーザーの要求する容量にあわせてデータを共有します。そのため、取得したいデータへ高速でアクセスできます。また、ブロックストレージにはファイルストレージのような階層構造が必要ありません。AWS(Amazon Web Services)で提供されている、Amazon EBS(Amazon Elastic Block Store )という仮想サーバーと共に利用するブロックストレージサービスが有名です。
オブジェクトストレージ方式
オブジェクトストレージとは、階層構造を取らないデータ保管方式です。オブジェクトストレージはファイルストレージと異なり、データサイズやデータ数の保存制限がないため、大容量のデータ保存に適しています。
そのため、オブジェクトストレージはクラウドストレージの保存方式として最も多く採用されているのです。「オブジェクト」と呼ばれる単位でデータを管理し、階層は持たずにフラットかつ依存関係もない状態で保管します。オブジェクトストレージはIDを伝えれば、すぐにデータを取り出せるため、アクセスが容易な特徴があります。
これらのストレージ方式で保存されたデータは、物理的なハードウエア、あるいはクラウドで利用される仮想サーバーなどに格納されます。クラウドストレージの場合はインターネット経由で仮想サーバーに接続し、クラウドストレージを利用します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワークは依然高い注目を集めています。外部から社内データを共有できるクラウドストレージは、テレワークと相性が良いといえるでしょう。総務省が公開する「令和2年 通信利用動向調査報告書(企業編)」によると、利用しているクラウドサービスの内容として「ファイル保管・データ共有」と回答した人が全体の59.4%を占めており、今後のさらなる伸長も予想されます。自社の目的にあわせて、最適なクラウドストレージの導入を検討してはいかがでしょうか。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【MT】
覚えておきたいクラウド&データのキホン