
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
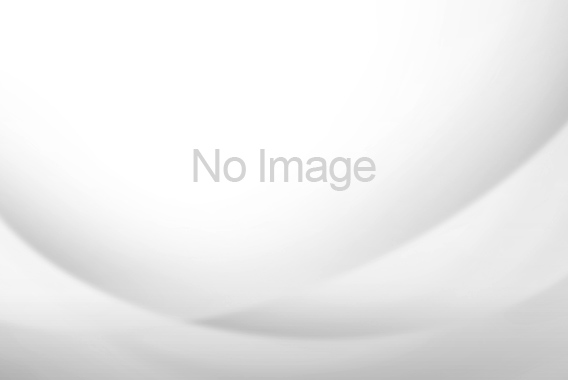
業務で使用するデータの保存先は、HDD(ハードディスクドライブ)やUSBメモリーが一般的ですが、最近ではクラウド上でデータ共有ができるサービスも増えています。本記事では、クラウドを利用したデータ共有サービスのメリット・デメリット、選ぶ際のポイントなど解説します。
クラウドを利用したデータ共有サービス(以下、クラウドデータ共有サービス)には、いくつかのメリット・デメリットがあります。
メリット1:専用の機器を用意せずにデータのやり取りが行える
HDDやUSBメモリーでデータを管理する場合、それらの外部ストレージも管理する必要がありました。仮にデータが入った外部ストレージを紛失した場合、アクセスできなくなります。
一方でクラウドデータ共有サービスは、クラウド上にデータが保管されており、インターネットに接続すればデータにアクセスできるので、外部ストレージを管理する必要がありません。
メリット2:複数人と同時にファイルを共有できる
多くのクラウドデータ共有サービスでは、インターネット上で複数のユーザーとデータを共有できます。ファイルを外部ストレージ経由で共有したり、メールに添付してやり取りしたりする手間も不要です。
メリット3:リスク対策になる
外部ストレージでデータを管理する場合、盗難などで本体を破損・紛失するとデータも消失します。クラウドデータ共有サービスであれば、物理的な被害でデータを破損・紛失する可能性を抑えることができます。
デメリット1:情報セキュリティリスクがある
クラウドデータ共有サービスは、ID・パスワードなどを把握していればログインできるため、もしID・パスワードが流出した場合は情報漏えいのリスクが生じます。
デメリット2:自社で障害対応ができない
クラウドデータ共有サービスで障害が発生した場合、ファイルにアクセスできなくなります。ユーザー側はサービスの復旧を待つしかありません。
クラウドデータ共有サービスを選定する際に重視すべきポイントは、主に以下の3つです。
データ容量
サービスや契約内容によってアップロードできるファイルの容量は異なります。また、1ファイル当たり、あるいは1日当たりにアップロード可能な容量の制限が設けられていることもあります。例えばMicrosoftが提供しているクラウドデータ共有サービス「OneDrive」の場合、1ファイル当たりの最大容量は250GBとなっています。またGoogleが提供するクラウド共有サービス「Googleドライブ」は、アップロードできるファイルは1日当たり750GBまでとなっています。扱うファイルの種類や容量を基に選択しましょう。
料金体系
クラウドデータ共有サービスの利用料金は、月額制や年額制、買い切りなどサービスによって料金体系が異なります。例えばBoxというクラウドデータ共有サービスの場合は月額制と年額制が選択でき、年額制の場合は割引が適用されます。1年以上の利用が決まっていれば、年額制を選択するとよい、などといった判断の指標となるでしょう。
また、pCloudというクラウドデータ共有サービスは買い切りプランを用意しており、980USドルで2TBが利用できます。ただしストレージ容量は技術の進化に伴い、容量単価が低くなる傾向にあります。買い切りプランの場合は容量・利用開始時期と料金のバランスを勘案して検討しましょう。
バックアップ機能の有無
多くのクラウドデータ共有サービスは、アップロードした各種データをサービス事業者側がバックアップしており、ハードウエア障害などサービス事業者側の問題でデータが紛失した際はバックアップデータが復元されますが、例外もありますので、バックアップ機能の有無もサービス選定の際に確認しましょう。
補足となりますが、クラウドにバックアップ機能があっても、ファイルの誤削除など、ユーザー起因のデータ紛失が発生する可能性はあります。PCにバックアップできるツールなどが提供されている場合もありますので、自分でもバックアップを行いましょう。
クラウドデータ共有サービスは多くの企業から提供されています。今回はビジネスシーンでも利用しやすいサービスを紹介します。
Googleドライブ
Googleドライブは、Googleが提供しているクラウドデータ共有サービスです。Googleが提供するスプレッドシートやドキュメントなどの保存・共有に加え、WordやExcelなどのデータも保存できます。15GBまでは無料で利用でき、以降はストレージ容量やユーザー数に応じた有料プランが用意されています。
Box
Boxはクラウドコンテンツ管理プラットフォームです。現在提供されているクラウドデータ共有サービスのプランではストレージ容量が無制限となるため、大容量のデータを共有したい場合に便利です。
Dropbox
Dropboxでは、取り扱いデータの暗号化や2段階認証、ユーザーごとの権限付与機能など、情報セキュリティ面にこだわった環境が提供されています。ビジネス用プラン「Advanced」を利用すれば、必要に応じて容量を追加することができます。
firestorage
firestorageは登録不要で利用でき、アップロードできるデータ数に制限がない点が特徴です。広告などが表示されますが、一時的な受け渡しを行いたい場合に役立つでしょう。有料会員になることで広告が非表示になるほか、データ容量が増加します。
OneDrive
OneDriveは Microsoftが提供するクラウドデータ共有サービスです。Microsoftのアカウントがあれば利用でき、複数名でデータの共有・編集・保存といった作業を実施できます。個人で使う場合、データ容量は5GBまで無料。ビジネス向けとしてMicrosoft 365が利用できるプランも用意されています。
どのクラウドデータ共有サービスを使うべきか悩んでいる人には、NTT西日本の「おまかせクラウドストレージ」をおすすめします。Webブラウザー上はもちろん、専用ツールをインストールすればデスクトップ感覚でクラウドストレージのデータにアクセスできます。社外の人とファイルを共有できる機能も用意されているので、データの受け渡しもスムーズに行えます。
データの共有はもちろん、従業員が保有するデータの管理やバックアップも行いたいという場合は、NTT西日本の「データ安心保管プラン」がおすすめです。クラウド上のサーバーを利用して社内データの一括管理やアクセス権設定、自動バックアップなどが行えます。専用サポートセンターが用意されているので、社内に情報システム担当者が不在の場合も安心です。
クラウドデータ共有サービスを利用すると、USBメモリーや外部ストレージなどと比べて物理的なデータの消失リスクを抑えつつ、データのやり取りができるようになります。またインターネット接続環境があれば社外からもアクセスできます。このように、情報セキュリティ対策の向上やテレワーク対応など、クラウドデータ共有サービスにはさまざまなメリットがあるのです。自社のデータ管理に課題を感じている人であれば、検討してはいかがでしょうか。
【おまかせクラウドストレージについて】
・おまかせクラウドストレージのご契約には、NTT西日本が提供する「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光クロス」、「フレッツ光ライト」、もしくは光コラボレーション事業者が提供するFTTHアクセスサービスいずれかのご契約が必要です
・ご利用には、「フレッツ光」などのブロードバンド回線およびプロバイダーサービスのご契約が必要です
【データ安心保管プランについて】
・ご利用には、「フレッツ 光ネクスト」等、プロバイダーの契約・料金が必要です
・サポートセンターでの対応は、日曜祝日・年末年始12/29〜1/4を除く、営業時間内(午前9時〜午後6時)に対応いたします
※「OneDrive」は、Microsoft Corporationの商標または登録商標です
※「Google ドライブ」はGoogle LLCの商標または登録商標です
※「Box」は、Box, Inc.の商標または登録商標です
※「pCloud」は、pCloud AGの商標または登録商標です
※「Dropbox」はDropbox, Inc.の商標または登録商標です
※「firestorage」は、ロジックファクトリー株式会社の商標または登録商標です
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【M】
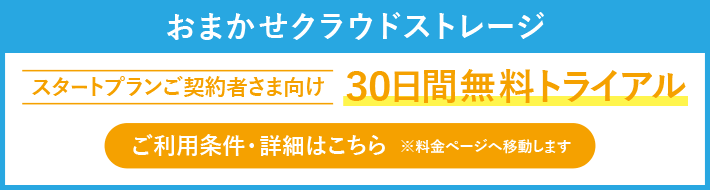
覚えておきたいクラウド&データのキホン