
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
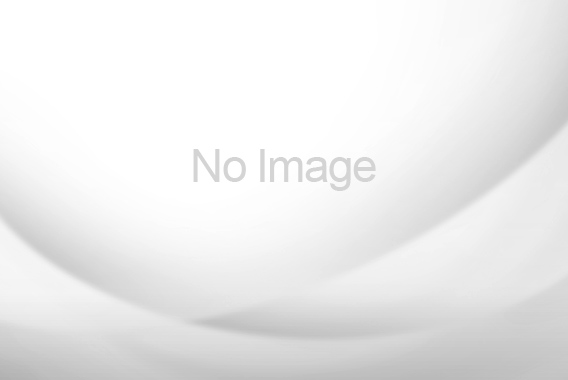
本連載32回で、独立行政法人情報処理推進機構(以下:IPA)が偽の警告画面にだまされないよう「偽セキュリティ警告画面の閉じ方体験サイト」を立ち上げたと紹介した。ウイルスに感染したかのような警告画面を表示する攻撃は、電話をかけるよう仕向けて偽のサポート契約を結ばせるサポート詐欺へとつなげるケースが多い。依然として猛威をふるうサポート詐欺について、IPAでは改めて2024年11月に特集サイトを公開し、注意を促している。どんな手口なのか、詳細を見てみよう。
特集サイトの冒頭で、IPAは「パソコンに偽のウイルス感染警告を表示させるサポート詐欺に注意-『今すぐ〇〇に電話してください』は偽物、絶対に電話しないで!-」と呼びかけている。IPAが"偽物""絶対に電話しないで"と判断を下すほど、疑う余地のない詐欺行為であると注意したい。
実際にどんな手口で攻撃を仕掛けられるのか。特集サイトでは細かく解説しているが、ここでは攻撃を受けたと仮定し、だまされるまでの段階を踏みながらその手口を分かりやすく紹介しよう。
最初の現象は、パソコンの操作中に突然、画面を埋め尽くすように「トロイの木馬スパイウエアに感染した」といった偽の警告が次々と表示される。これはかなりインパクトがあるので、IPAの擬似体験サイトでぜひ体験してほしい。
慌ててキャンセルボタンなどをクリックすると、今度は画面全体に広がるスクリーン表示に切り替わる。この画面上に表示される「✖️(閉じる)」ボタンは偽物で、クリックしても反応しないのでさらに慌ててしまう。
同時にスピーカーからは「すべてのファイルが削除されます」「今すぐサポートセンターに電話してください」といったアナウンスが延々と流れる。IPAでは「これらはすべて電話をかけさせるための細工です」と警告している。
電話番号の上には、マイクロソフトのサポートであるとロゴマークとともに表示される。わらにもすがる思いであろうターゲットとなった操作者には、救いの神にも見えるはずだ。だが、ここで電話をすると攻撃者のわなにはまってしまう。具体的には偽のサポート契約を結ばされ、現金をだまし取られたり遠隔操作でウイルスを送り込まれたりする。
攻撃者はターゲットの心理を逆手に取った巧妙なわなを仕掛ける。最初に偽の警告画面が表示されるきっかけは、広告などに埋め込まれた偽のボタンであることが多いようだ。つまり勤務中に広告を見ていたりする場合で、その行為に後ろめたさもあるだろう。
偽のボタンを押してしまい、「ウイルスに感染した」「ファイルがすべて削除される」といった警告が次々と表示されると、当然パニックになる。そこに救いの手が差し伸べられれば思わず助けを求めてしまうのは当然だ。
さらに攻撃者はマイクロソフトという誰もが知っている企業のエンジニアをかたって噓の説明をする。偽の社員証を表示する場合もあるという。ITに詳しくない者であれば、言われるがままに従ってしまう可能性は高い。相手は知名度のある専門家になりすましているのだから。
相手から言われるがままにパソコンの操作をすると、遠隔操作のソフトを送り込まれる。そこで遠隔操作を承認してしまうと、もう相手のなすがままだ。ターゲットとするパソコンにさまざまな偽の画面を表示させ、いかに問題があるかという噓の説明を次々としてくる。
その上で偽のサポートプランを提示し、金銭を要求する。パソコンが遠隔操作されているため、IDやパスワード、ファイルなどを盗み出されたり、パスワードの設定を変更されたりしてログインできなくなる可能性もある。金銭のやり取りにはギフトカードなどのプリペイドカードが悪用されるケースが多かったようだが、IPAによれば被害が急増した2023年からはネットバンキングによる不正送金の事例が発生しているという。相談窓口には198万円の被害にあった事例も報告されているようだ。
こうした犯罪に従業員が巻き込まれるリスクを、企業は放ってはおけない。IPAが警告しているように「『今すぐ〇〇に電話してください』は偽物、絶対に電話しないで!」を、すぐにでも従業員全員に徹底してほしい。さらに専門家に相談し、万一の際には泥沼にはまらないよう対処法を告知しておきたい。
執筆=高橋 秀典
【TP】
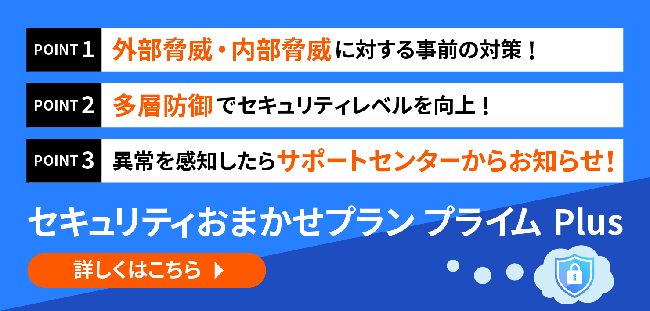
最新セキュリティマネジメント
審査 24-S1007