
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
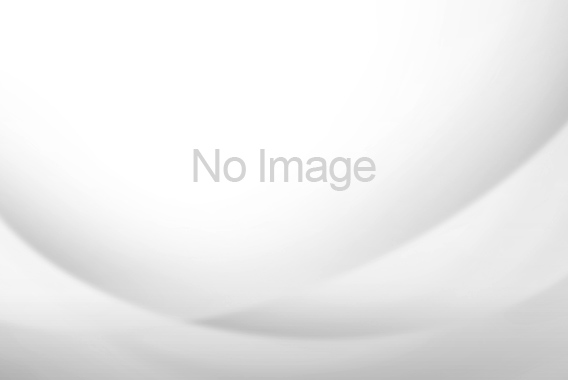
前回から、最後の第6ステップ「データで評価する」を解説しています。まずは評価するデータとして「労働生産性」「総資産回転率」「総資産利益率」の3つを上げ、それぞれ理由を解説しました。今回は、労働生産性を指標として現場改革を進めた実例を紹介し、本連載の最終回とします。
一の湯は神奈川県箱根町で8軒の温泉旅館を運営する1630年創業の老舗旅館です。箱根では2番目の歴史を誇る一の湯は、バブル崩壊後に市場の流れについていけず、1987年当時には経営状況が悪化していました。先代が建てた洋式ホテルも苦戦を強いられ、銀行から資金調達もできない状況でした。そこで15代目に当たる小川晴也相談役が取り組んだのが、労働生産性を指標とした現場改革でした。
小川氏が注目したのは、労働生産性の1つである「人時生産性」の指標でした。「人時生産性」とは、労働時間1時間当たりの粗利益で計算される指標です。しかし、小川氏がこの指標を実際に計算しようとすると、多くの問題に直面しました。最初の問題は従業員の総労働時間の把握でした。旅館業では繁忙期には長時間労働を行い、閑散期に休みを取るため、労働時間を厳格に管理する習慣がありませんでした。今では当たり前のことですが、小川氏はまず労働時間を1分単位で正確に算出しました。その結果、曖昧にしてきた残業代が白日の下にさらされ、すべての従業員に残業代を支払うことになりました。
また、仕入れ高を正確に把握するのは簡単ではありませんでした。旅館の仕入れは日々行われますが、伝票がそろうのはずっと後だからです。伝票内容も問屋によって異なり、管理部門が数字で仕入れ状況を理解するのは簡単ではありません。そこで、その日に必要なものはその日に仕入れて在庫を抑え、伝票と在庫を一致させるようにしました。
当初は人時生産性の計算を10日ごと、月3回のペースで行っていましたが、10日単位では土日の数字が影響するのでデータにばらつきが出ます。そのため、これを週次に切り替え、仕入れや総労働時間は日次で管理するようにしました。2年かけてようやく正確に計算できるようになりましたが、人時生産性は約1400円。これは、一の湯が1時間当たりに計上する粗利益額が1400円しかないということを示しています。
ここから人件費を含めた必要経費を支出すると、全く利益が残りません。粗利益に占める人件費の割合を労働分配率といい、一般的な旅館はそれが40%程度なので、従業員の1時間当たりの平均給与は560円という当時でも低い水準になります。
そこで小川氏は、当時の小売業の平均的な人時生産性の半分に当たる3000円をまず目標にして現場の改革を進めました。これは当時の一の湯の約2倍に当たる金額です。人時生産性を2倍にするには、粗利益を2倍にするか、総労働時間を半分にしなければなりません。
食材などの仕入れを減らすには限度があります。あまり減らすと料理の品質が落ち、宿泊客から不満が出ます。また、旅館は客室数に比例して売り上げが増えていくと一般に考えられていますが、当時の一の湯には設備投資を行って客室を増やす余裕もなく、つまるところ売り上げを増やせない状況でした。
小川氏は、総労働時間を半分に減らすしかないと悟りました。つまり、2人でやっていた仕事を1人で行うようにするのです。小川氏は現場のすべての業務方法を見直し、1つひとつの効率化や省力化を進め、10分、15分という単位で労働時間の短縮を図りました。最初は効果がありましたが、次第に効果が出なくなり、従業員もやる気を失っていきました。
そこで、小川氏はサービスの内容を根本的に組み替えました。同時に、事業戦略を立て直し、「気楽に宿泊できる温泉旅館」をコンセプトとして、宿泊料金も1万円未満に引き下げました。
このコンセプトに沿って、すべての業務で必要なものと不要なものを切り分け、現場から無駄を削っていったのです。ただし、サービスの提供方法の変更はその内容や品質に直結します。そのため、何か新しいことをやるたびに2週間は経過を見守って、宿泊客から決定的なクレームがなければその作業を継続する方法で進めていきました。
最初に行った改革が、宿泊客の靴の管理方法の変更です。それまでは玄関にいる下足番が靴を預かり、チェックアウトが集中する朝はまとめてげた箱から靴を出して玄関に並べていましたが、これにより靴の取り違えも起きていました。そこで、多くの居酒屋で普通にやっている鍵付きのげた箱に宿泊客が自分で収納する方法に変えました。
チェックイン後の部屋への案内もやめました。さらに、部屋での食事提供もやめ、宴会場をレストランに改修してそこで食べてもらうようにしました。一時はバイキング方式も取り入れましたが、結果的には総労働時間が減らず、それよりも、よりおいしい状態で食事を提供できるように、各テーブルに従業員が料理を配膳する方法に戻しました。
この食事の時間帯に、一般的な旅館では、今も従業員がふとんを敷きますが、一の湯ではこのふとん敷きもやめました。宿泊客が簡単に自分で敷けるようにシーツをかぶせた状態で押し入れに入れておき、引っ張り出すだけで良いようにしたのです。「本当にこれで良いのだろうか」と悩んだそうですが、クレームは1件もなく、従業員が部屋に入らないので「気楽でいい」と言う宿泊客が出るほどでした。部屋の冷蔵庫の飲料水販売もやめ、館内に自動販売機を設置して市中と同じ金額で販売しました。
業務の標準化や単純化により従業員のマルチタスク化も進めました。2つの仕事を1人が同時に行うため、それができるよう現場レイアウトも変更しました。宿泊予約数に合わせて、複数の施設を越えた従業員のシフトも組めるようにしています。
こうした努力の結果、人時生産性は20年間で約4倍の5000円に届くまでになり、従業員の所得水準も50%引き上げられました。一の湯は人時生産性を計算し、それを常にチェックしながら生産性改革を進めました。数値を確かめるからこそ間違うことなく、宿泊客が求めるサービスに集中できたのです。
執筆=内藤 耕
工学博士。一般社団法人サービス産業革新推進機構代表理事。世界銀行グループ、独立行政法人産業技術総合研究所サービス工学研究センターを経て現職。
【T】
中小サービス業の“時短”科学的実現法
審査 24-S1007