
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
飲食店を経営していると、その日の集客状況や売れ行きによってどうしても食品が余ってしまいます。廃棄にかかるコストや環境への影響も考えて食品のロスを減らしたいのですが、何か方法はありませんか?
A.フードシェアリングサービスの利用を検討しましょう
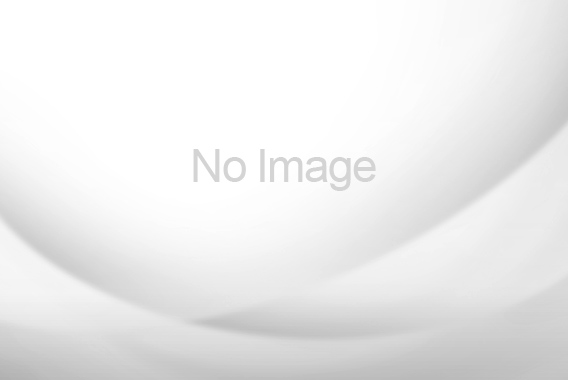
フードシェアリングサービスとは「食品ロス(フードロス)」の削減を目標に、余剰食品を抱える飲食店や小売店と買い手となる消費者やフードバンクを仲介するサービスです。
食品ロスとは、まだ食べられる状態・品質であるにもかかわらず食品が廃棄されてしまうことをさします。例として、フードシェアリングサービスでは次のような食品が取り扱われています。
・賞味期限が迫った食品
・仕入れ後、使用されず余った食品
・見た目や大きさが販売規格外の食品
一般的にフードシェアリングサービスでは、アプリやWebサイトを介して出品された余剰商品を、サービスを利用する消費者が通常より安価で購入できる仕組みになっています。
フードシェアリングサービスには、購入された商品を店頭で直接受け渡すタイプと購入者の自宅まで配送するタイプがあり、主に飲食店で発生する調理済みの余剰食品は、即日の店頭受け渡しに対応したサービスが適しています。
また、2015年9月に国連サミットで採択された「SDGs(持続可能な開発目標)」の実現に向け資源を有効活用する取り組みの一環として、近年食品ロスの削減が世界的に注目されています。
日本国内でも2019年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」が施行されたのを受け、さまざまなフードシェアリングサービスが普及し始めました。
参考■SDGs(持続可能な開発目標)17の目標と169のターゲット(農林水産省)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sdgs/sdgs_target.html
参考■食品ロスの削減の推進に関する法律(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/promote/
そのため、フードシェアリングサービスを利用した食品ロスの削減は、売り上げアップや廃棄コストの削減というメリットだけでなく、持続可能な世界の実現に貢献するという社会的意義があります。
フードシェアリングサービスを利用する際は、希望の利用方法や販売したい食品の特性を考慮してサービスを比較・検討しましょう。
※この記事は2020年10月16日現在の情報です
【T】
困りごと解決ビジネス専科