
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
2007年設立で、2011年4月からインターネット経由でさまざまな食材を首都圏の飲食店に販売し始めた八面六臂(東京・中央)。以前は、鮮魚が中心だったが、飲食店のニーズに応えて野菜や肉などの取り扱いを増やしている。
同社を創業した松田雅也社長は、ITを武器に食材の流通に切り込んで効率的な配送を実現。2000~3000品目を個人経営の飲食店に提供して喜ばれている。かつては銀行やIT業界にいた松田社長がなぜ食品流通に関わり、どのように変革しようとしているのか(聞き手は、デロイト トーマツ ベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)。
斎藤:以前は、ITを駆使した新鮮な魚の販売が中心でしたが、今は扱う商品がだいぶ増えたそうですね。
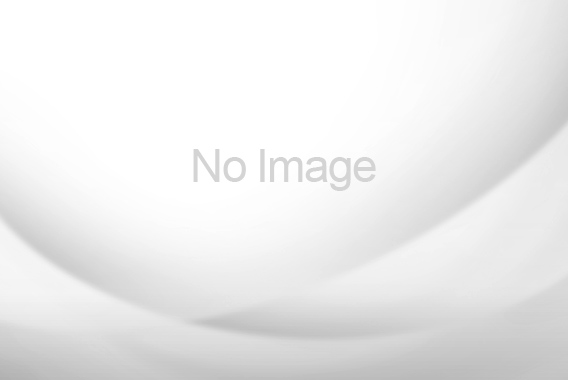
八面六臂の松田雅也社長。1980年大阪府生まれ。京都大学法学部卒業後、銀行などを経て2007年にエナジーエージェント(現・八面六臂)を設立して社長就任。11年4月から現社名に変更し、飲食店向けEC事業「八面六臂」を開始した
(写真:菊池一郎/以下同)
松田:青果や精肉なども扱うようになり、取扱品目が以前より大幅に増えて、2000~3000品目に達しています。全体の3分の1が青果、3分の1が水産物、残り3分の1は精肉、冷凍食品、加工品などです。料理人の要望に応えるため、他の食品ネット通販ではめったに扱っていない珍しい野菜もそろえています。加賀野菜の金時草(きんじそう)や京野菜の壬生菜(みぶな)、ナス1つ取っても大長ナス、小ナス、岡山千両ナスなど幅広くそろっています。こうした食材を扱うための地方からの仕入れルートを5~6年かけてつくってきました。
斎藤:販売先は飲食店ですね。
松田:お客さまは個人オーナーの飲食店(個人店)が多いです。現在、毎月継続的に注文をいただくお客さまは800~1000店ありますが、一度契約していただき、当社の良さを理解していただくと、ほとんど解約はありません。カバー範囲は東京、埼玉、千葉、神奈川で、すべて自社物流網で配送しています。
斎藤:中には少量の注文があると思いますが、配送費用はどうしているのですか。
松田:配送料は先ほどお話しした1都3県どこでも重量に関係なく1回当たり一律500円をいただいています。また年会費4980円の会員サービスに入会していただくと、配送料は無料となります。もちろん、中には1回当たりの金額が100円前後という注文もありますが、それでも構いません。お客さまのある日の注文が100円だけでも翌日は1万円かもしれない。週単位、月単位という長い時間軸で収支を考えるようにしています。
斎藤:1都3県のどこから注文が入るのかはぎりぎりまで分からないでしょう。配送をどのように管理しているのですか。
松田:我々は独自に配送の仕組みを構築し、配送を店1軒単位の点としてではなく、線、そして面で考えています。
一定のエリアごと、配送ルートをある程度決めていますので、配送は一種の路線便のようになっています。飲食店から注文があると、どのルートに乗せれば効率よく運べるかを考慮して配送順を組み立てます。深夜2時までに発注してもらえれば、その日の午前9時から午後3時までの間に納品しています。
それを実現するためには、配送だけでなく、商品のピッキングや梱包も含めたオペレーションをいかに効率化するかが重要です。
これまで、食材の物流は、専門的な仕事で素人には手が出せないと思われていましたが、調べてみると意外とシンプルだし、従来の仕組みではムダに使っている時間も多かった。それに、以前は「八王子エリアなら俺に任せろ」というドライバーがいたりして、物流のノウハウが属人化していました。この状態は、その地域が得意なドライバーがいなければ現場が困ってしまう不安定なものです。
斎藤:そんな属人的な状況があったんですね。

八面六臂では、社内で配送状況を細かく把握できる。松田社長(左)がシステムを操作する様子を見守る斎藤氏(右)
松田:そこで、我々はGPS(全地球測位システム)などを使って、こうしたドライバーにたまっていたノウハウを見える化し、効率よく配送する仕組みをプログラムに落とし込んだのです。こうすることで、誰でもそのノウハウを活用して食材を運ぶことができます。
こうしたコンピューターで管理した配送により、物流原価を下げてきました。今、当社のクルマがどこを走っているか、本社で見ることができます。このシステムがあれば効率的な配送ができます。
斎藤:閉店後の深夜に注文して翌日届くのは、飲食店にとって便利ですね。
松田:従来の食材配送は、外食チェーン店を相手にするビジネスが多く、それぞれメニューがバラバラである個人店をターゲットに配達をする業者がほとんどいなかった。我々は、野菜1パックから届けて、個人店が各地の旬の食材をもっと使いやすくなるようなサービスをめざしています。
斎藤:生鮮食品のネット販売は大手でも苦戦することが多いものです。どうして八面六臂は成功したのですか。
松田:うまくいっていないところは、食材と工業製品を流通させるためのオペレーションが根本的に違うことを理解していない企業が多いと思います。
現在、多くのネット販売は、今日、買い忘れても明日同じものを購入できる商品がほとんどです。しかし、生鮮品はその日限りの商品で次の日に同じものは買えません。バーコードが付いていない商品の流通をどう管理するかが大事になります。生鮮品の流通は、通常のネット販売とは違うのです。
斎藤:食材の仕入れは安定的ではありませんからね。
松田:ですから、我々は、地方から食材を直接取り寄せることはもちろん、築地市場や大田市場など中央卸売市場で仕入れることも否定していません。否定しないどころか、積極的に活用しています。
大きな市場で仲卸から買うのは簡単ですが、大卸と呼ばれる大手の荷受業者と取引するのは大変です。我々も3年前までは相手にされませんでした。流通量が少なかったからです。
つまり、売る力がないと中央卸売市場との取引は難しい。そのためには地道に売る力を身に付ける必要があります。資本力だけで一朝一夕には実現できないのです。
斎藤:地方からの直接仕入れの方が、中央より安く食材を仕入れられそうに思いますが。
松田:それは「産直幻想」ですよ。食材は産地の方が安いとは限りません。地方の産地では基本的に生産者との相対取引なので、鮮魚の場合なら、水揚げ量が少なく、産地の需要が大きければ浜相場は高くなります。ですから、同じ魚でも築地市場の方が安いということもあります。その使い分けが大事なのです。
ただし、価格だけが重要なのではありません。地方には優れた食材がたくさんあります。そうした食材は都市部ではあまり知られていません。当社のバイヤーたちは地方からの仕入れルートをいくつも持っており、各地のおいしい食材を季節に合わせて仕入れています。
こうした地方との関係づくりはシステム化できないので、物流システムとは違い、いい意味で属人的に進めています。また、地方の水産市場ともネットワークを築いて、各地の魚の水揚げについて情報を入手して適切な場所から仕入れるようにしています。当社の仕事は、地方の食材を首都圏で供給する“地産都消”の仕組みといえます。

八面六臂は鮮魚から青果、精肉まで幅広い食材をインターネット経由で飲食店に販売する。写真はその一例で、朝〆で鮮度が高いイシガレイ、皮に縞模様があるイタリア原産のナス(産地は千葉)
日経トップリーダー/吉村克己
※掲載している情報は、記事執筆時点(2017年10月)のものです
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】
注目を集める地方発のベンチャー