
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
1964年、病に倒れた父の後を継ぎ、大阪の小さなプラスチック製品工場の社長となった大山健太郎氏。次々と新しい市場を切り開き、年間1000点もの商品を開発する大手生活用品メーカーへと育て上げた。地方発の小さな企業が大きく成長するための考え方、困難に立ち向かいながらも創業時の熱を持ち続けるための秘訣を聞いた。(聞き手は、トーマツ ベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)
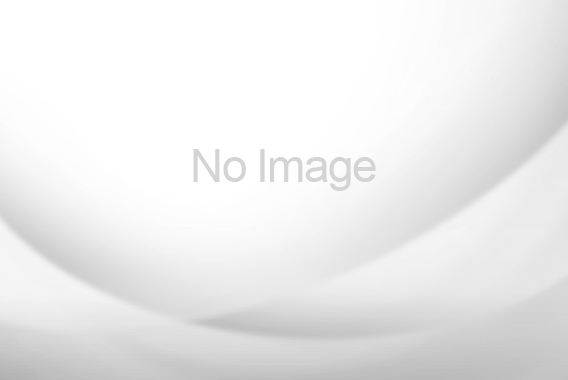
アイリスオーヤマの大山健太郎社長。1945年生まれ。大阪で父が経営していたプラスチック加工の大山ブロー工業(現・アイリスオーヤマ)を19歳で引き継ぐ。71年に株式会社化。89年に本社を仙台市に移転。91年、アイリスオーヤマに社名変更(写真:新関雅士、以下同)
斎藤:アイリスオーヤマは、今までにない商品を作り出し、次々と新しい市場を広げてきました。その歴史は、会社を成長させたいベンチャー経営者にとても刺激になるものだと思います。現在は、宮城県仙台市に本社がありますが、創業は大阪だったんですね。
大山:そうです。19歳の時に父親ががんで亡くなりまして、その時に私が家業を引き継ぎました。父の会社は、東大阪のプラスチック製造業だったのですが、当時は社員5人、年商500万円という本当に小さな下請け工場からのスタートでした。
斎藤:お父さまの背中を見ながら育ち、いつかは自分も家業を継いで経営者になろうと考えていらっしゃったのですか?
大山:いいえ。それまでは会社を継承するつもりなどなく、商売のイロハもまったく分かっていませんでした。ただ、分からないなりにその時に考えたのが、小さくても自社の強みがなければならない、ということです。
では、当社の強みは何かと、探してみたのですが、強みが何もなかったんです。資金力も技術力も営業力も組織力も人材力も、何もない。ただ1つだけ、当社にも強みがあった。それは私の19歳という若さでした。この若さで「もうからないビジネスをもうかるようにしよう!」と考えました。
斎藤:若さを武器に、何から始められたのでしょうか?
大山:人の2倍、働きました。夜の8時ごろに社員が帰った後、朝の8時まで私が機械を回しました。小さな会社だからそれが可能だったんです。そういうことを半年、1年続けていると、営業力がなくても売れるようになります。お客さまにとっては、注文したらすぐ納品されるところほど、便利な下請けはないわけですから。資金力や営業力を強化する前に受注が増えて、21歳前後には工場を増築しなければならないくらいに大きくなりました。
ただ、そこまでであれば、一介の下請け企業で終わっていましたが、私にも志があったんです。それは、「自分の作ったものは自分の価格で売りたい」ということです。そのためには、自社商品を作るしかない。でも、自社商品は資金力や技術力、営業力、販売力がなければ作れません。
斎藤:当時は会社も小さかったと思いますが、どうやって自社商品を作ろうと考えたのですか。
大山:私はどうしたらいいだろうと必死で考えました。当時は金属や木、竹の道具をプラスチック製に切り替えたいという需要が多かった。これはビジネスチャンスだと考え、21歳の時に養殖用のブイを自社開発しました。おかげさまでこれがヒットし、そこから水産業だけでなく、農業の田植えに使う育苗箱を木箱からプラスチックに変えるなど、次々と新商品を作り出し、時代の流れに乗って会社はどんどん大きくなっていきました。
東大阪の工場だけでは製造が追い付かず、宮城県に工場を造ったのは26歳の時です。この時に宮城県を選んだのは、やはり農業向けの製品は東北地方の需要が大きいだろうと判断したからです。
斎藤:いくつかの“カベ”を若さで乗り越えて、会社を成長軌道に乗せられたんですね。しかし、時には、うまくいかないこともあると思います。これまでで最大のピンチは何だったのでしょうか。
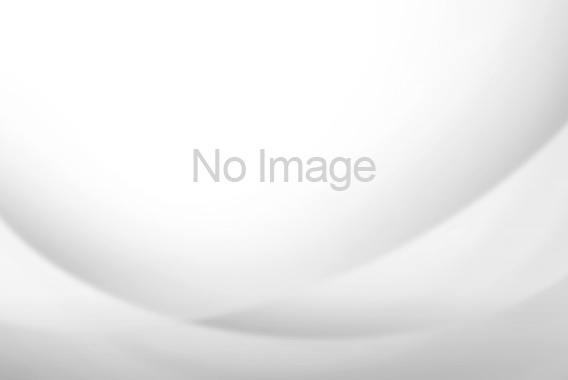
「大山社長のお話には、企業が成長するためのヒントがたくさんある」と、斎藤氏
大山:ちょうど宮城県に工場を造ったのと相前後して起きた、オイルショックですね。プラスチックはすべて石油からできていますので、かなり大きな影響を受けました。10年間かけてためた資金が、わずか2年間で底を突き、倒産寸前になるという地獄を味わいました。
多くの企業は、もうかる製品があると増産しようと次々に投資をしますが、好況の時期は続かない。好況があれば今度は必ず不況が来るんです。それが現実の市場経済なんだと、オイルショックの時に学びました。
その時、やむなく社員を解雇したんです。東大阪の工場は自宅とつながっていましたから、私が小さい頃は社員の皆さんと一緒に食事をして、家族同然でやってきたんです。
それが結果的には社員に給与を払えなくなってしまい、東大阪の工場を閉めて宮城県の新しい工場に集約する判断をしました。今のように新幹線や飛行機などの交通機関もまだ便利ではなかったですから、大阪から宮城に付いてくる社員は少なかった。結局、退社してもらうしかなかったんです。それしか会社が生き残る道はありませんでした。
そこからは、もう2度と社員の解雇はしたくないという強い思いを持ってきました。
斎藤:会社の規模を広げてこられた後、あわや倒産というピンチに直面して、それをどうやって切り抜けられたんですか。
大山:倒産の危機に直面したとき、私は考えました。いかなる時代、環境においても、利益を出せる仕組みを確立しなくてはならないと。つまり、不況時でももうかる会社にしたい。そのためには「人と同じことはしない」ということなんです。同じことをしていると、好況のときはみんな売れますが、不況になるとみんな一斉に売れなくなってしまいます。すると、業界ごとダメになってしまうんです。
それを避けるには、競争のない世界でビジネスをする。これが、ベンチャー企業に大事なことだと思うんです。大企業と同じことをやって勝てるはずはありません。大企業の便利屋になるならそれでいいかもしれませんが、せっかくベンチャーを起業したのなら、違う土俵で戦うべきではないでしょうか。
特に、当時作っていたブイや育苗箱のような産業資材は、景気の波の影響を受けやすい。しかも、零細な企業は大手より影響が大きくなる。技術で1番だ、シェアで1番だと言ったところで、大きな波が来れば、業界全体が低迷してしまうのです。
斎藤:確かに。しかし、どうやって競争のない市場を見つければよいのでしょうか。

「ユーザーイン」の視点で、競争のない新市場を切り開く
大山:売り手側の視点に立つ「プロダクトアウト」の考え方では、大企業に勝てませんし、同業での競争になります。「マーケットイン」の考え方で売っても、これは買い手の視点に立つ発想ですから、結局高いか安いかという価格競争になってしまうので利益を出しにくくなる。
そこで、生み出したのが「ユーザーイン」という発想です。
生活者の目線に立って生活に必要とされるもの、不足しているもの、不満と思われているものを探し出して、商品を作ったり、改良したりするんです。それでこれまでにない、まったく新しい需要を生み出そうと思ったのです。
当社の生きる道を探そうと、日本のメーカー140万社を徹底的に調べ上げ、たどり着いたのが園芸用品でした。まだ盆栽や家庭菜園しかなかった時代に、草花を家の中に持ち込む「ガーデニング」という新たな市場を創造していきました。
ユーザーインの実現には、ほかにもカベがありました。商品流通です。
当時、一般的だったのは、メーカーがいて問屋がいて、小売りがいて消費者がいるという流れです。しかし、当社がまったく新しく開発する商品はどれだけ売れるか未知数ですから、問屋はあまり仕入れたがらない。それがブレーキになって、当社が売りたい商品を市場に効率的に流通させることができないんです。
このカベを越えるにはどうすればよいかと考え、ホームセンターと直接取引を始めました。その時から20年くらいかけて、メーカーが問屋機能を自社内に持つ「メーカーベンダー」という新たな業態を確立してきたのです。
斎藤:ベンチャー経営者と接していると、経営者になってからの期間が長くなればなるほど、創業時に持っていた熱を保ち続けることはすごく難しいという話をよく聞きます。メンタル面で苦しいとき、つらいときもあったと思いますが、何を信念にして乗り切ってこられたのですか?
大山:あまり高過ぎる志を持たないことだと思います。1歩ずつ、着実に進んでいけば、そんなに自分にプレッシャーはかからないんですよ。
身の丈に合ったところで努力をする。その努力を積み重ねて目標とする山に登り、その山の頂上に立ったら、目線が上がったところで周囲を眺めてみて自分の能力に応じた次の山をめざしていく。そうやって成長を続け、志を継続させることが大切なんです。
ですから、19~22歳の時はとにかく働きましたが、それを苦労とは思いませんでした。仕事はかける時間と付加価値が比例します。商品1個分の時間をかければ、1個分の成果が生まれる。そうやって、1歩ずつ目標をクリアしていくんです。
次回は、アイリスオーヤマの新製品開発、地方ベンチャーとしての戦い方などを伺います。
日経トップリーダー/尾越まり恵
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年9月)のものです
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】
注目を集める地方発のベンチャー