
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
オーマイグラス 清川忠康社長
インターネットで眼鏡を売る。従来、視力を矯正するための度つき眼鏡を購入するのは、視力検査や鼻あて、テンプルの調整などが必要なためリアル店舗で行うのが一般的だった。しかし、インターネット通販での“試着”を実現し、眼鏡産地である福井県鯖江市に拠点を構え、町の眼鏡店と提携しながら業績を拡大しているのがオーマイグラスだ。「日本の眼鏡の流通構造を改革したい」と話す清川忠康社長にこれからの展望について聞いた(聞き手はトーマツベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)。
斎藤:清川さんの試みとしてユニークなのが、インターネット通販なのに眼鏡の試着ができるという点かと思います。こんなサービスを始めたきっかけはなんだったのですか?
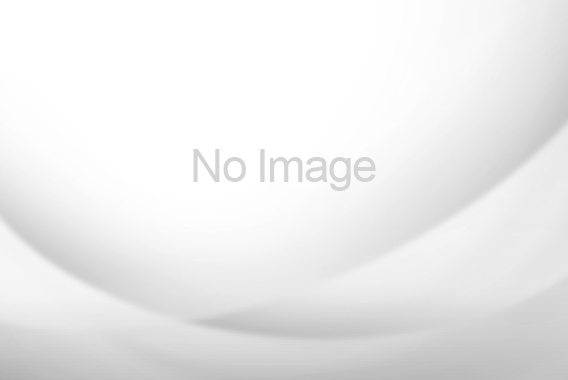 清川:すごくシンプルなんですけど、これまで眼鏡という商材はインターネットには向いていないと思われていました。眼鏡は実際に掛けてみないと装着感が分からないということと、度数の調整をどうしたらいいんだという、2つの大きな問題があってなかなかインターネットで買うのは難しいと。
清川:すごくシンプルなんですけど、これまで眼鏡という商材はインターネットには向いていないと思われていました。眼鏡は実際に掛けてみないと装着感が分からないということと、度数の調整をどうしたらいいんだという、2つの大きな問題があってなかなかインターネットで買うのは難しいと。
そこで我々は送料無料で返品も無料、また5日間5本まで無料で試着できるサービスを始めました。ですからインターネット通販なんですが、店頭で探しているときのように複数から選ぶことができます。それからもう1点、視力検査に関しても、全国1000店舗の眼鏡店と提携していて、近くの店に行けば度数の確認やレンズの処方も受けられます。ネットとリアルが一緒になって、必要なときに補完できる仕組みにしています。
斎藤:なるほど。しかし、そもそもなぜインターネットで眼鏡を売ろうと思われたのですか?
清川:あ、その根本的なところですか(笑)。今回、わざわざ取材にお越しいただいた福井県鯖江市というこの町が非常にユニークでして、日本製の眼鏡の95%がこの小さな町で作られています。
斎藤:95%、すごい! 作っているのは眼鏡のフレームですか。
清川:眼鏡フレームです。メード・イン・ジャパンの眼鏡というと、実はグローバルで有名なブランド、例えば、シャネルであったり、クロムハーツや、ブルガリなどのサングラスってほとんどがメード・イン・ジャパンなんです。この辺の町工場に行くと普通にプラダのものを作っていたりします。ただ、ほかの産業も同じことが起きていますが、最近、日本製の眼鏡というものの需要が縮小してきていて、非常に厳しい状態にあります。
斎藤:もともとは日本製の眼鏡は、ブランド物も含めて強かったと。
清川:強かったんですよ。ただ、これが10年、20年で一気に縮小しました。何分の1かになってしまった。そこで我々が着目したのは、これだけのいいものがあって、しかも円安にもなってきている。日本製の、日本の技術力がもう一度見直される時期に来ているはずだと。そのときに日本だけじゃなく、世界で売っていくためにどうすればいいのかと考えたときにおのずとインターネットにたどり着いたんです。 眼鏡って物が小さいですし、世界中に送りやすい。そこで「TYPE」という自社ブランドを立ち上げました。これなんですけど……。
眼鏡って物が小さいですし、世界中に送りやすい。そこで「TYPE」という自社ブランドを立ち上げました。これなんですけど……。
斎藤:これ、触って大丈夫ですか?
清川:もちろんです。これはまだサンプルという水準のものなんですけど。我々が自主企画して作ったブランドのものを、自社のeコマースサイトや代官山や梅田のTSUTAYA、新宿伊勢丹でも販売しています。現在はまだ日本国内でしか販売していないのですが、海外の「monocle magazine」で取り上げられたり、賞もいただいたりして少しずつ知名度が上がってきました。
斎藤:自社ブランドは何が狙いで立ち上げたのですか?
清川:この鯖江にはたくさんの工場があって、もともとOEM(相手先ブランドによる生産)の産地なんですね。海外のグローバルブランドのOEM需要がどんどん少なくなってきたときに、自分たちでブランドをつくっていかなきゃいけないよねという動きが出てきました。下請けじゃなく自分たちでメード・イン・ジャパンのブランドをつくろうと。
例えば、今治タオルなどはうまくブランディングしていますけど、鯖江はまだまだブランド化されていない。作るところと売るところって、必要なマインドセットも全然違うじゃないですか。在庫リスクも取らなきゃいけないし、ブランド投資もしなきゃいけない。ビジネスモデルが全然違うので、なかなかそこを変えていくことができなかったんです。
斎藤:それは鯖江という町全体としてですか。
清川:そうですね。眼鏡業界というのは非常に独特で、例えば製作過程が240から250工程もあるんです。
斎藤:そんなにあるんですか。
清川:ものすごい分業制なんです。さすがに240社が絡んでいるわけではありませんが、細かく分業しすぎでとても非効率なんです。ですからエンドユーザーとの距離も遠いですし、業界自体のIT化も非常に遅れていて自分たちでブランドをつくろうと思っても肝心のユーザーの要望とか情報が全然入ってこない。
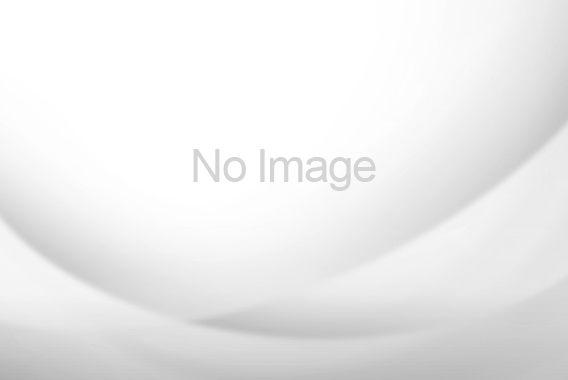 例えばこのサンプルは、プラスジャックという会社に作ってもらいました。そちらも自分たちでハウスブランドをやられていて、4年くらい前に初めてそこの津田(功順)社長とお会いしたとき、そのブランドをインターネットで売りたいとおっしゃるんです。で、商品を見せてもらったら、本当にものすごい種類がある。なぜこんなに作ったんですかと聞いたら、何を作ればいいか分からないから、取りあえず思いついたものを全部形にしたと。
例えばこのサンプルは、プラスジャックという会社に作ってもらいました。そちらも自分たちでハウスブランドをやられていて、4年くらい前に初めてそこの津田(功順)社長とお会いしたとき、そのブランドをインターネットで売りたいとおっしゃるんです。で、商品を見せてもらったら、本当にものすごい種類がある。なぜこんなに作ったんですかと聞いたら、何を作ればいいか分からないから、取りあえず思いついたものを全部形にしたと。
斎藤:なるほど。マーケティングもなしで、ただひたすら思いついたものを作ると。それは非効率ですね。
清川:一方で我々のビジネスはインターネットで、基本は直販です。ちゃんとユーザーの声が入ってくる。この町にはそういったインフラが全然整備されていなかったんです。そこで我々が鯖江に拠点を構えて、手に入れた情報を現場にフィードバックして、それを商品開発に生かしていく。そういう流れが少しずつできつつあります。それをまたOEMにも生かすとまた売れるようになる。
斎藤:オリジナルブランドで培った情報やノウハウをまたOEMに戻していくといったサイクルもできるわけですね?
清川:我々の取引先はこの鯖江に60社くらいありますが、ほとんどが2~3人の家族経営です。そういうところが月に5本、10本とどんどん売れるようになってきて、我々の必要性というのもだんだん高まってきていると感じています。
また自社ブランドも進化していて、これまでは新しいブランドを立ち上げようとすると、有名なクリエーターやデザイナーにお願いして、みたいなやり方が多かったと思うのですが、そうではなくてインターネット発で、2万点もの商品を扱っている我々だからできるブランディングであり、商品開発があると思っています。データを見ながら売れ筋のものを探って、どんどん、オリジナル商品に反映していく。
斎藤:そういったデータは具体的にどういうところを見ていくのですか。
清川:例えば今自社ブランドは「TYPE」と「+omg」という2つのブランドがあって、+omgのほうはまさにデータドリブンで作っています。ターゲットへの訴求の仕方、あとは在庫の持ち方です。色、売れ筋、売れている量をそのまま在庫量に反映する。そういったことをすることによって、在庫回転率がマーケット平均の倍ぐらいになったりする。
斎藤:それはいわゆるSPA(製造小売業)ということですか?
清川:そうですね。これはデータを持っているからこそできる。狙っているところは、例えば「Instagram」のようなものが盛り上がってきているじゃないですか。そういったものを使う新しい世代の人に鯖江の商品を買ってもらうことなんです。
日経トップリーダー/藤野太一
※掲載している情報は、記事執筆時点(2015年9月)のものです
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】
注目を集める地方発のベンチャー