
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
“起業大国”の米国でニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授を務め、「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」などの著書もある入山章栄氏。早稲田大学ビジネススクールで経営学を教える准教授でもある。日本の起業シーンを活性化させるための手法を経営学の視点から評価し、米国との比較を盛り込みながら解説する。(聞き手は、トーマツ ベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)
斎藤:前回は、地方で起業する際のハンディキャップを解消する取り組みについてお話しました。でも実は、地方ベンチャーにとっての重荷は、商圏を広げることができて、東京のベンチャーキャピタル(VC)から出資を受けて、ネットワークさえ確保してしまえば、ないも同然なんです。その他のことは、地方にいて時々、東京へ出張して対応すればいいわけですから。
入山:ハーバード大学ビジネススクールのポール・ゴンパース教授とジョー・ラーナー教授らの共著「ベンチャーキャピタル・サイクル」によれば、米国でVCと投資先との物理的な距離はだいたい60マイル、約100㎞ということでした。広大な土地を持つ米国では近いイメージかもしれないけれど、日本で100㎞といったら結構な距離です。
でも、現代は交通インフラが発達しているから、行こうと思えば週1~2回のペースで上京できる。フィジカルの壁というか、物理的な距離は米国よりも日本のほうが低いのかもしれません。地方に拠点を置いて、その優位性を生かすビジネスを考えられますよね。
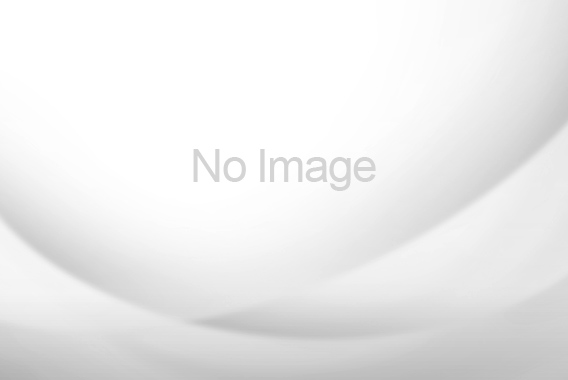
地方のベンチャーのあり方について、米国と日本を比較して解説する入山・早稲田大学ビジネススクール准教授(写真:菊池一郎、以下同)
斎藤:地方の有利な面は2つあると思います。1つはストーリーを組み立てやすいことです。「この街に1000人の雇用をつくる」とか、「故郷で、10年で100個の事業を立ち上げる」などというと共感を得やすい。特に、東日本大震災以降、「共感できるストーリー」が求められるようになっています。みんなが応援したくなる仕組みをつくり、周りを巻き込む力が重視されているんです。
入山:起業には明確なビジョンや強いモチベーションが必要ですよね。地方の人たちは、「ここが好き」という単純な理由でやれる。それが一番、強いわけです。低価格メガネチェーン「JINS」を経営するジェイアイエヌの田中仁社長も、出身地の群馬県で起業家を育てるイノベーションスクールを立ち上げました。「日本のアパレルを救うブランドをつくる」(第1~4回)で登場したライフスタイルアクセント(熊本市、山田敏夫社長)も、「熊本を盛り上げたい」という気持ちが強い。みんな、やっぱり故郷への思いってすごくあります。
斎藤:むしろ、東京のベンチャー企業のほうが、その場所で事業をする蓋然性が少ないので、アピールしにくいんです。
入山:東京のベンチャー企業はある意味、甘やかされているかもしれないですね。資金の調達先や手段がたくさんあって、営業先もたくさんある。人口が多い分、商圏も広い。“東北の雄”とよばれるアイリスオーヤマの大山健太郎社長は「東京は(餌が豊富にある)いけすだ」などと言うそうですが、確かに都心の起業家は恵まれ過ぎているという面があるかもしれません。
斎藤:地方の有利な面のもう1つは、ライバルが少ないということです。ある県で小学生向けにITとものづくりを融合させた習い事教室を運営している会社があります。プログラミングをしたり、3Dプリンターを使ったり、ロボットを作ったりして注目を集めています。こちらの代表はトーマツ ベンチャーサポートで学生アルバイトを経験しており、地方出身者が東京で1年くらい修業をして戻ると、圧倒的な力でトップに立てるという例ですね。
入山:概念的にいうと、東京は立地というリソース(資源)があるけれど、コンペティション(競争)がすごく厳しい。逆に地方はリソースさえ確保できれば、ドミネート(支配)できるチャンスがあって、いきなり勝つことも不可能ではないという仕組みなんですね。
斎藤:地方には、東京にはない貴重なリソースもあるんです。その1つが「農業」です。佐賀県の山奥で起業したベンチャー企業があります。佐賀駅から30~40分かかり、地元の方ですら迷うような場所です。(笑)
製造しているのは、竹炭やお茶のカテキンを使った鮮度保持剤。冷蔵庫に入れておくと3日くらいしか持たない野菜が1週間持つとか、専用装置と併用すると3週間持つといった商品です。周辺が農家ばかりだから、野菜を配送したいお客さんがいっぱいいる。それで、佐賀を拠点に研究を続けているんです。東京でまねしようにもできないビジネスモデルですよね。山奥という土地柄が技術そのものというか。
入山:農業関連のベンチャーは、地方にある利点ってすごく大きいですよね。
斎藤:第2回で紹介した高知・土佐山の“起業キャンプ”も地方ならではの利点を生かしたビジネスモデルです。6カ月の起業プログラムを経て、実際にビジネスを立ち上げる「土佐山アカデミー」です。人口1000人を切った過疎の村で、小学校も中学校も閉鎖されてしまっているほど、何もないところです。
入山:あ、そこで起業するの?(笑)
斎藤:ええ。ビジネスなんか成り立たないと思うでしょう。
 面白いのは、1つの事業で何十万も稼ごうとしないんです。例えば、インバウンド(訪日外国人観光客)に部屋を貸して月5万円、同時にカフェをやって月数万円、クラウドソーシングで仕事を受けて月数万円、というふうに売り上げを積み重ねて月20万円くらい稼ぐポートフォリオをつくります。近所の人が野菜をくれたりするから、月10万円あれば家族4人で暮らせるし、月20万円も稼げればすごく裕福に生活できる。
面白いのは、1つの事業で何十万も稼ごうとしないんです。例えば、インバウンド(訪日外国人観光客)に部屋を貸して月5万円、同時にカフェをやって月数万円、クラウドソーシングで仕事を受けて月数万円、というふうに売り上げを積み重ねて月20万円くらい稼ぐポートフォリオをつくります。近所の人が野菜をくれたりするから、月10万円あれば家族4人で暮らせるし、月20万円も稼げればすごく裕福に生活できる。
実際に移り住んで起業した人に話を聞いたら、「過疎だからいい」というんです。もともとは都心の高級住宅街に住んでいたほうですが、学校では1人の先生が40人の児童を指導するような状況で、子どもの教育環境としては破綻している。自然に恵まれていて、1クラスに児童が数人しかいないような村が魅力なのだそうです。
入山:へえ、面白い。僕が日本に帰ってきた最大の理由は、やっぱり日本のほうが面白いからです。起業シーンでいえば、米国はステレオタイプであまり工夫がない。シリコンバレーに行っても、ルールができ上がってしまっている印象です。日本人は大きな仕掛けをつくるのが下手で、今後の課題ですけれど、単発の面白いアイデアはたくさんある。それぞれの創意工夫で思い思いのことをやる人たちというのが、これまでのお話のようにどんどん出てきていて、大きな変化が起きていますよね。
日経トップリーダー/名嘉裕美
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年6月)のものです
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】
注目を集める地方発のベンチャー