
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
オーマイグラス 清川忠康社長
2011年の創業以来、わずか4年余りでインターネットで眼鏡を売るという流通構造の改革を浸透させてきたオーマイグラス。米スタンフォード大学を卒業した清川社長はなぜ眼鏡を売ることになったのか。第3回は、清川忠康社長に事業を始めたきっかけを語ってもらった(聞き手はトーマツベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)。
斎藤:オーマイグラスを利用して購入されたユーザーからは、良かった点や不満点などどんな声が寄せられているのでしょうか?
清川:良かった点は体験ですね。家で試着できることで家族の意見が聞けたとか、会話が楽しいといった声が多いですね。弊社の顧客も30代の中盤の男性が多いんですが、そういった男性って眼鏡店やセレクトショップに行くときは、奥さんや彼女を連れていって似合うかどうか見てもらうという方が意外と多いんです。家だとそれがいつでも簡単にできますよね。
斎藤:確かに、その眼鏡が自分に似合っているかどうかってなかなか客観視しづらいですし、家族や誰かの意見って重要ですよね。
清川:そうなんです。それから不満な点というか、課題はたくさんあって何とも言い難いですけど……。全部が試着できるわけではなくて、試着できない商品もありますし、検眼のところで家の近くに提携店がないとかそういったこともあります。
斎藤:今、オーマイグラスはどれぐらいの人数で運営されているんですか。
清川:社員は全部で30人ぐらいです。データエンジニアが一番多くて、あとはフルフィルメントですね。つまり、加工や出荷、検品とかも含めてやりますので結構な人数がいます。
斎藤:それってアウトソースしているのではなくて?
清川:アウトソースはしていなくて、全部一貫でやっています。社内でやらないと眼鏡ってなかなか難しいんですね。
斎藤:それも珍しいですよね。しかし、よく考えると証券会社出身でスタンフォード大学大学院への留学経験もある清川社長がなぜ鯖江と眼鏡にこだわっておられるのか。ほかにもいろいろ選択肢があるように思うのですが(笑)。
 清川:もともと日本の物を世界で売るとか、日本のものづくり自体に興味を持っていたんです。以前、経営共創基盤という会社で日本の物を世界に売るとか、製造業の再生みたいなことに携わっていて、そういう点では今の仕事も同じで、眼鏡の流通構造を改革して、日本の製造業のポテンシャルを拡大していきたいという思いがありました。
清川:もともと日本の物を世界で売るとか、日本のものづくり自体に興味を持っていたんです。以前、経営共創基盤という会社で日本の物を世界に売るとか、製造業の再生みたいなことに携わっていて、そういう点では今の仕事も同じで、眼鏡の流通構造を改革して、日本の製造業のポテンシャルを拡大していきたいという思いがありました。
斎藤:それは留学によって、海外から日本を見たことがきっかけなんでしょうか。
清川:そうですね、2003年、2005年、2009年とこれまでに3回で延べ4年間くらい米国での留学経験があります。その学生生活の中で、例えば中国人の学生の数が急激に増えていて、日本人はどんどん減っているとか、そういうことを身に染みて感じるわけです。2009年から2011年はスタンフォードに留学していたんですが、もはや日本って世界から何とも思われていない。GDPで世界3位のプレゼンスなんかなくて、まるで50位ぐらいの扱われようです。ただ、トヨタみたいな会社もあるので、ちょっとフォローしておくかぐらいのレベル感でしか見られていないんです。
斎藤:世界から見た日本のプレゼンスの弱さに危機感を抱いたと。
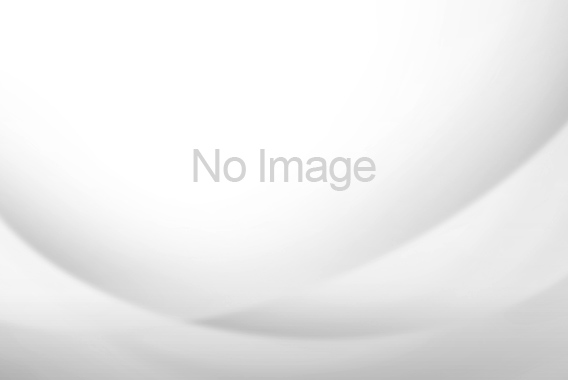 清川:そうです。今、小売業を見ていても、円安になってほとんどがインバウンドですよね。日本の消費力も弱ってきているし、この10年くらいですごく変わったと思います。世界からの見られ方も、実際も。
清川:そうです。今、小売業を見ていても、円安になってほとんどがインバウンドですよね。日本の消費力も弱ってきているし、この10年くらいですごく変わったと思います。世界からの見られ方も、実際も。
第二次大戦後の日本は高度経済成長を迎えるわけですけど、するとパンや牛乳が米国から日本に入るようになりました。米国にいて感じたのは、要は日本は米国系企業にとっておいしい市場だったわけです。
逆に、今の「レクサス」が象徴的で、日本では売っていなくて米国から始まったブランドですよね。トヨタの本当の意図は分かりませんけど、あえて米国の高級車市場に打って出るというのは、米国人に対しての宣戦布告だと思ったんです。米国の高級車市場においてもメルセデスベンツやBMWといったドイツ車は人気ですけど、でもレクサスは新しいブランドでした。最近では少し雰囲気も変わってきましたけど、当初はブランドとかデザインといったものではなくて、中身、コストパフォーマンスで勝っていたように思うんです。
そういうものを見ていて、日本のものづくりってすごいなと。しかし、その一方で戦後の商社マンが見てきた、アフリカに行けば必ずトヨタ車が走っているみたいな、そういう時代は終わるんだなとも感じて。今後、グーグルの自動運転なんかが当たり前になったら、自動車産業もどんどん変わっていく。
そこで眼鏡に戻るんですけど(笑)、戦後の日本の復活を支えてきた根源的なものづくりというものをなくしちゃいけないなと思ったんです。
斎藤:やはりメード・イン・ジャパンを守るべきだと。
清川:そう。ただし今は本質的な、目に見えないクオリティーがある一方で、象徴的な商品であるとか、目で見て分かるクオリティーというか、デザイン性がないとだめなんですよ。
例えば黒縁の眼鏡を黒人とかが掛けていたら目立ちますよね。黒縁眼鏡=メード・イン・ジャパンの眼鏡だみたいな、そういう世界をつくっていきたいと。
産業革新機構さんにもそういう話をしました。オーマイグラスはネクストトヨタだと。眼鏡という一般商材でトヨタのような会社をつくっていかないと、これから世界に飛び立っていく日本のビジネスパーソンの心のよりどころはどこにあるんだと。そういう世界をつくりたい。車ほどの市場規模はないですから、何十兆円は無理です。でも、数千億円規模のビジネスはつくれるだろうと。2020年、2030年、100年後、日本の眼鏡が世界でトヨタのような存在感を持っている。そもそもはそういう思いから始まっているんです。
斎藤:なるほど。ということはここ鯖江市を豊田市のようにしたいというわけですね。
清川:そうなんです。だから、鯖江にこの拠点を作るときに鯖江の市長さんにまずいい場所を探してほしいとお願いしました。ここから100人、500人、1000人と少しずつ雇用を生んでいく。そういうふうにしていきたいと思っているんです。
斎藤:いわゆる企業城下町ですね。
清川:そうです。その中心にオーマイグラスを置こうと。それぐらいの構想を持ってやっています。
斎藤:清川社長のように世の中を変えてやろうという思いで起業する人がスタンフォードにはたくさんいるイメージですが、やはり刺激を受けることは多いんですか?
清川:影響は大きいですね。2015年現在、我々は戦後にイノベーションを起こした人たちの遺産を引き継いでいるだけなんだと思うんです。最近、時価総額を見ていると大きい会社が増えてきていません? アップルとか。10年前、20年前じゃ考えられないような規模の会社が出てきていますよね。一方で日本からはもう大きな会社って生まれないんじゃないかと。ヤフーもグーグルもフェイスブックもみんな米国発です。
斎藤:まだ歴史も浅いですよね。
清川:でも、あれだけ大きくなっていますよね。
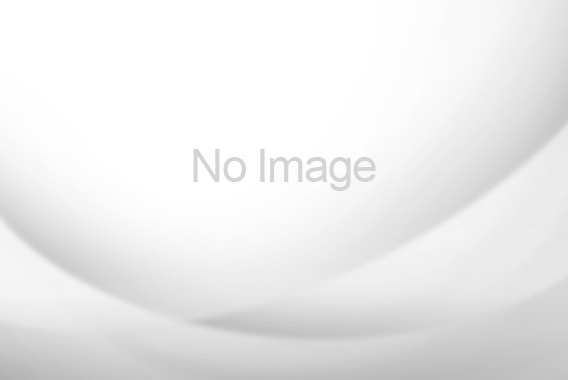 斎藤:ある意味、世界がすごく小さくなってきているので、トップを取った会社が独り勝ちで、一強時代になっていくような傾向があるかもしれません。
斎藤:ある意味、世界がすごく小さくなってきているので、トップを取った会社が独り勝ちで、一強時代になっていくような傾向があるかもしれません。
清川:そうすると、もし自動車産業が縮小していったらそこに日本の企業はなくなってしまいます。海外ではもう日本からイノベーションは起きないと、そういうふうに思われていますから。ですから、新しいイノベーションを起こしていかないと。自分だからこそできること、気づく視点とか問題意識というものを軸にして、ほかの人にできないことをやっていったほうが恐らく世の中に価値を提供できると思うんです。
斎藤:ITベンチャーは東京にもたくさんありますが、確かに事業内容としては米国で出たビジネスモデルを日本で展開するものが多く、オリジナルのものが少なくなりがちですね。
清川:少ないと思います。みな情報を知らないというのが多いと思いますけど。今になって思うのは私がもし学生時代にいろんな情報を知っていたら、もっと早い段階でスタンフォードを受けていますよね。クラスメートにすでにニューヨークで会社を上場させていた人とか、中国で成功してバーンとIPOした人とかが周りにたくさんいる。そうすると、あいつでもできるんだみたいな。じゃあ、俺もやってみようと思ったりすると、そういう環境が普通にあって、早い段階からグローバルな視点が自然に養われる。
斎藤:横のつながりもたくさんあるから、ノウハウも共有できますしね。
清川:そうなんです。出資を受けるとか、メディアに取り上げられるとか、そういうノウハウはみな一緒で、シリコンバレーなどでは横連携でがんがんやっています。
斎藤:そういう意味では東京も少し変わってきて、起業家同士や政治家、市長とか県知事と会って情報共有していくような流れも出てきていると思うんです。ただ一方で地方ではそうしたコミュニティーがまだなくて、情報戦に入れていない。
清川:そうなんです。地方発のベンチャーが難しいといわれるのはまさにそこで。革新機構さんがうちに出資してくれたのはそれも認識している上で、地方と東京の両方をミックスしたベンチャーはどうなのかといった視点があるんじゃないでしょうか。サイトでは「Oh My Glasses TOKYO」って、東京をうたっているんですけど、東京と鯖江との案配がいいんです。
斎藤:東京はPRとか販売などの拠点で、産地は産地として分けて活動していくと。ただ思うのが、普通のITベンチャーはネット完結のビジネスのほうが多いしやりやすい。でもオーマイグラスでは実際に物を作って流通させるみたいな難しいビジネスに挑戦されているわけじゃないですか。その点は相当苦労されたのではないでしょうか。
清川:やはり資金も必要ですし、調達もしなきゃいけないという面では苦労もありますけど、ただ私自身としては上場ありきで仕事をしているわけではないですし、日本のものづくりのグローバル化、そのためにやっているという思いがあるので、そこは苦労というわけじゃないですよね。
斎藤:組織や人材の面ではどうですか。
清川:そこは大変ではありますよね。ソーシャルゲームを作ってきたバリバリのエンジニアや、ずっと小売りをやってきた営業や、いろんなメンバーがいて、もう全然文化も違うから、そこの一体感をつくるのは大変です。ただ、私は30代前半ですけど、優秀なバイヤーには50代半ばの人や経営陣2人も40代で、そういう経験のあるメンバーが来て、安心感が生まれてきたと思いますね。
日経トップリーダー/藤野太一
※掲載している情報は、記事執筆時点(2015年9月)のものです
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】
注目を集める地方発のベンチャー