
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
“起業大国”の米国でニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授を務め、「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」などの著書もある入山章栄氏。早稲田大学ビジネススクールで経営学を教える准教授でもある。日本の起業シーンを活性化させるための手法を経営学の視点から評価し、米国との比較を盛り込みながら解説する。(聞き手は、トーマツ ベンチャーサポート事業統括本部長、斎藤祐馬氏)
入山:僕は起業における地域性にもすごく興味があるんです。日本全国で特に起業への熱い思いや新しいことをやりたいという人たちが多い地域はありますか。
斎藤:中小企業白書2014年版によれば、沖縄は開業率が日本一なんです。「働くところがないから飲食店を開業する」みたいなイメージらしく、毎年、大学を卒業する約4000人のうち、1000人ほどが定職に就かないそうです。
入山:米国でも、シリコンバレーで起業する人が多いのは、暖かいからという話があります。みんな過ごしやすいカリフォルニアが大好きだから、大企業に勤められなくてもいい、ここに住み続けたいと言って。それと似ているんじゃないかな。
例えば、カリフォルニア大学ロサンゼルス校は超一流大学ですが、ビジネススクールの格付け指標であるMBAランキングはそれほど高くないというのは有名な話です。ランキングはMBAを取った卒業生の給料がいかに上がるかに応じて伸びます。ニューヨークのウォールストリートでバンカーやコンサルタントになって高給を取らず、起業する卒業生ばかりだと、大学のMBAランキングも上がりにくいんです。
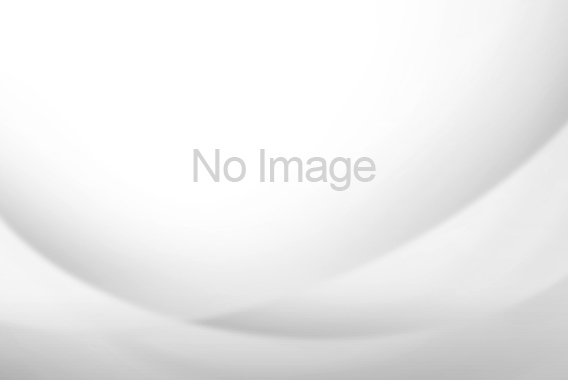
聞き手の斎藤氏も、沖縄について熱く語る
斎藤:イノベーションは異なる領域が接する“際(きわ)”で起きるといわれていますが、沖縄にはこの“際”の最先端とでもいうべき場所があるんです。11年に学校法人として設立された、5年制で博士課程のある沖縄科学技術大学院大学(OIST)です。
予算のほとんどが国からの補助金です。前身の沖縄科学技術研究基盤整備機構の理事長にはノーベル生理学・医学賞を受賞したシドニー・ブレナー博士を招請しました。教員1人に対して学生2人という比率で、教育より研究に力を入れており、大学の公用語は英語。教員と学生の半分以上は外国人という環境です。数学や化学、物理など複数の分野で学際的な研究をしているようです。
豊富な予算があり、最先端の研究を行っている若い人がたくさんいて、開業に対する抵抗のない土地柄となると、面白いビジネスの種やトレーニングの仕組みがあれば盛り上がるでしょうね。
入山:そんな大学があるんですか、沖縄に。知りませんでした。すごいですね。日本で最初にシリコンバレーのようになるのは沖縄かもしれない。外資系のユニークな企業や日本の大手企業、ある程度、軌道に乗ったベンチャー企業の拠点などができると、活性化しそうですね。
米国では、スマートフォンからタクシー代わりに使える自家用車を探して予約する「Uber(ウーバー)」を提供するウーバー・テクノロジーズがピッツバーグ市に研究拠点を置く代わり、市側がウーバーを全面解禁したというストーリーを聞いたことがあります。真偽の確認はできない話ではありますが、もし本当であれば地域の活性化を念頭に置いた駆け引きですよね。
斎藤:日本だと、補助金よりも規制緩和のほうが効きますよね。あとは世界の研究者は集まってきているので、日本の若くて優秀な人をどう集めるか。産業との接点をどうつくるかです。研究施設があるだけでは、ベンチャー企業をつくっても結局、お金が入ってこない仕組みになってしまいますから。
これまで、ベンチャー企業のゴールはIPO(新規株式公開)かM&A(合併・買収)のどちらか。日本はIPO一辺倒で、景気が悪くなると起業ブームが縮小してしまう傾向にありました。今、僕らがやっている試みが浸透して、大企業がベンチャー企業に投資して育て、買収し、さらに新しいものをつくるというサイクルができれば、ベンチャー企業は出口の選択肢が増える。景気に左右されない起業文化を創り出せると思っています。入山先生はどうお考えですか?
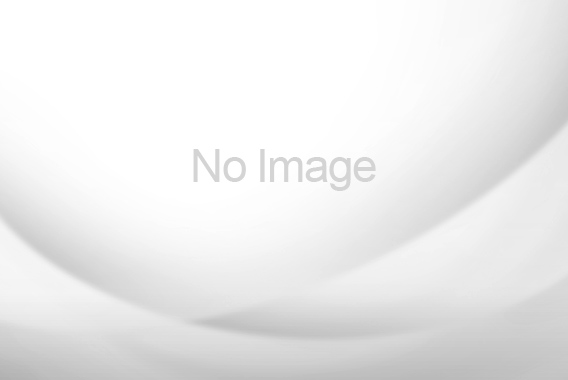 入山:自社の事業戦略の一環として投資するコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)が地方の技術力のあるベンチャー企業と組むと、投資と成長のいいサイクルが実現できるのではないでしょうか。普通のVCはリターンまでの目算が短い。スマートフォンのアプリを開発するような、アイデアとスピード勝負のベンチャー企業ならいいのかもしれません。でも、技術力で勝負したいベンチャーにとっては、もう少し長い目で投資してくれるCVCのほうが現実的なビジネスパートナーといえます。
入山:自社の事業戦略の一環として投資するコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)が地方の技術力のあるベンチャー企業と組むと、投資と成長のいいサイクルが実現できるのではないでしょうか。普通のVCはリターンまでの目算が短い。スマートフォンのアプリを開発するような、アイデアとスピード勝負のベンチャー企業ならいいのかもしれません。でも、技術力で勝負したいベンチャーにとっては、もう少し長い目で投資してくれるCVCのほうが現実的なビジネスパートナーといえます。
斎藤:マーケットの構造的な変化も起きていると思います。今まで、大企業は「いいもの」を自社でつくれば売れる時代でした。でも、経済がグローバル化するようになって、「新しいもの」を世界中から集めて売れる人が勝つ時代になりました。トレンドの移り変わりがすごく早くなっていますよね。
入山:経営学において、ビジネスにおける競争には「産業構造や経済の規模で優位なポジションを取って勝つ」「技術や人材などオペレーション力で差異化する」など複数の型があるとされています。でも、これは両方とも事業環境が変化しないという前提があるからこそ立てられる戦略です。悠長に「まずはポジションを確保して」などとやっていると、今の時代はあっという間にトレンドが変わって負けてしまう。競争の構造が本質的に変わってきているので、変化に対応できる“足の速い”ベンチャー企業でないと勝ち抜けない。今後、起業が活性化せざるを得ない状況になり、もっと増えてくるのは間違いないでしょう。
日経トップリーダー/名嘉裕美
※掲載している情報は、記事執筆時点(2016年6月)のものです
執筆=斎藤 祐馬
※トーマツ ベンチャーサポートは、2017年9月1日より「デロイト トーマツ ベンチャーサポート」に社名変更しました。
【T】
注目を集める地方発のベンチャー