
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
食料品をはじめ、物価高が消費者を直撃していると感じる読者も多いだろう。原材料価格の高騰や電気料金の値上げなどが、その一因と考えられている。特に、電気料金の高騰は消費者だけでなく、企業活動にも大きな影響を与える。多くの企業が省エネや節電を実施しているが、単に電力消費を抑えるだけでなく、従業員の働き方を見直す必要もある。今回は、オフィスの電力消費削減のポイントについて考えていきたい。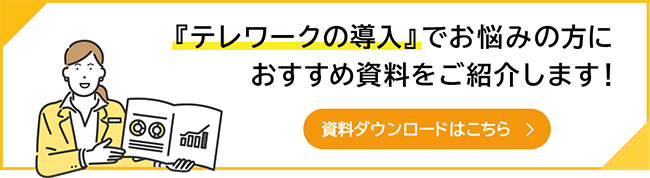
電気料金高騰の要因としては、例えば、火力発電に必要な原油・石炭・LNG(液化天然ガス)などの化石燃料の高騰や、円安の長期化、コロナ禍を経て経済が回復し電力需要が拡大していることなどが考えられる。地域の電力会社によって電気料金はまちまちだが、この環境の中で、電力消費の削減は企業の大きな課題となる。
オフィスで電力を消費する主なものには「照明、空調、OA機器」がある。これらで電力消費のおよそ85%を占めるとされる。資源エネルギー庁「夏季の省エネ 節電メニュー(令和5年6月)」によれば、一般的なオフィスビルにおける電力消費比率(17時時点)は空調48.6%、照明23.1%、パソコン6.6%、複合機7.3%、エレベーター等7.3%、その他7.0%となっている。
夏の暑いときには従業員の熱中症対策や働きやすさを考慮しながら、オフィスの冷房の効かせ過ぎに注意し、無理のない範囲で室内の温度を上げることにより、省エネになる。オフィスフロア面積やそこで仕事をしている従業員数によっても異なるが、室内温度を26度から28度に上げた場合、約3%の省エネ効果が見込めるという。
空調機の節電機能を利用する、フィルターの清掃など定期的なメンテナンスを行う、窓への日射を遮るためにブラインドやカーテン、遮熱フィルムを利用するといった対策も効果的だ。また、照明の節電もポイントだ。使用していない会議室などの消灯はもちろん、昼休みにオフィスの照明を抑えるなどこまめな消灯による節電や従来の蛍光灯をLED照明に交換することで電力消費が削減できる。
ただ、勤務時間中にもオフィスの照明を間引きして節電に努めるケースも見受けられるが、あまり暗くなりすぎると業務に支障がでてくる。さらに、従業員の健康(照度不足による眼精疲労など)にも影響するので注意が必要だ。
この点、労働安全衛生規則では、照度について規定している。労働者が常時就業する部屋の作業面の照度基準について、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業(資料の封入など、文字を読んだり、資料を細かく識別したりする必要のない作業)は150ルクス以上としている。また、労働安全衛生基準では「採光および照明」も規定している。事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備につき、6カ月以内ごとに1回、定期的に点検しなければならない。照度を計測する照度計も市販されており、従業員の健康はもちろん、業務の効率化、生産性の向上を図るためにも、節電とともに適切な照明を考えたい。
オフィスの電力消費と大きく関係するのが、パソコンやサーバー、複合機などのOA機器、そしてネットワーク機器だ。まずはパソコンから考えていこう。
業務に欠かせないパソコンの節電には、ディスプレーの明るさ(輝度)を調整する方法がある。すでにノートパソコンの充電バッテリーを長時間持たせるために輝度を調整している人もいると思うが、電力消費の抑制につながる。ちょっと席を外すなど、一時的にパソコンを使わない時にはスリープモードにすることで節電になる。数時間以上パソコンを使わないのであればシャットダウンしたいところだ。こうすれば節電だけでなく、第三者による盗み見などのセキュリティ対策にもなる。
次に複合機などだ。複写機能やプリンター機能、スキャナー機能、FAX機能を統合した複合機の利用もオフィスでは一般的だ。複合機を一定時間使用しないときには自動で低電力・スリープモードになるように設定する方法もある。
また、1枚の用紙に複数ページを印刷する機能を使うことで紙やトナーなどのコスト削減だけでなく、複合機利用にかかわる電力消費の抑制にもつながる。印刷そのものの削減には、オフィスのペーパーレス化推進がポイントになる。パソコンが一人一台のオフィス環境であればWi-Fiなどのネットワークを介して資料なども印刷することなく会議が行える。資料の共有・保管は社内のファイルサーバーやクラウドストレージサービスを利用すればよい。
では、社内で運用するファイルサーバーやメールサーバー、アプリケーションサーバーなどの節電も検討していこう。サーバーやネットワーク機器を考えるうえでは、これらを設置する部屋を冷却する空調設備の節電対策も必要になる。ファイルやメール、アプリケーションなどのサーバーは、オンプレミスからクラウドサービスを利用することで運用管理コストのみならず、電力消費の削減も可能だ。オンプレミスのファイルサーバーからクラウドストレージに置き換えることで、サーバーやコンピューター室の節電が期待できるだけでなく、オフィスのペーパーレス化によって従業員の仕事の仕方も変えられる。
オフィスの省エネ、節電を進めるには、従業員の働き方も大きなポイントになる。テレワークやハイブリッドワークを採用すれば、オフィスの空調や照明、OA機器などの電力消費の削減も期待できる。
ただ、注意しなくてはいけないのが従業員のコミュニケーション環境や情報共有といった側面だ。オフィスでお互いに近くにいれば簡単に相談できるようなことでも、テレワークの中では難しい面も出てくる。ビジネスチャットなどを上手に活用した意思疎通・情報共有ができる環境構築を進めたい。
また、テレワーク、ハイブリッドワーク時の電話取り次ぎにも留意したい。従業員にスマートフォンを支給して社内・社外との通話を可能にしている会社は別にして、オフィスに顧客・取引先からかかってきた電話の取り次ぎが課題の企業は少なくないだろう。その解決策になるのがスマホの内線化だ。会社にかかってきた電話を自宅や外出先でも内線電話としてスマホに着信できるので、重要な顧客からの電話でも取り逃がすことなく、スムーズな対応が可能だ。そして、オフィスで仕事をする人が少なくなれば電力消費の削減も期待できる。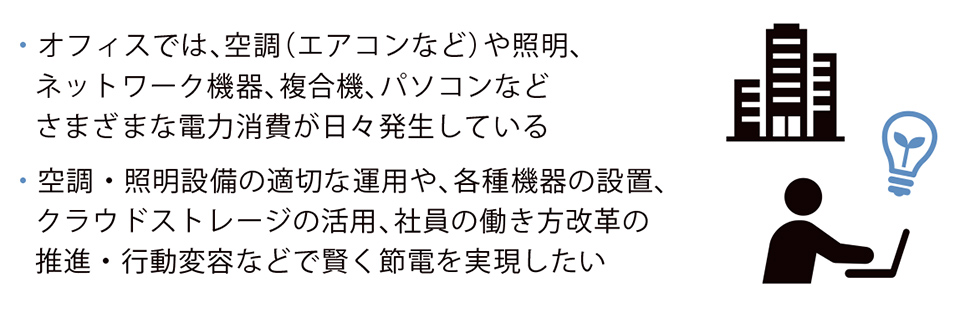
電気料金が今後も上がることはあっても、大幅に下がることは期待しにくい。省エネ、節電は企業の課題であるCO2削減にもつながる。空調や照明、OA機器などの節電対策とともに、どんなIT環境にすれば自社の業務効率化や働き方改革に効果的なのか検討したい。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=山崎 俊明
【MT】
ビジネスを加速させるワークスタイル