
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
事業環境が目まぐるしく変化する中で、迅速な意思決定が求められている。その際に重要になるのが、社内に蓄積されている情報だ。必要な情報を素早く引き出し、それを踏まえることで合理的な決定が可能になる。しかし、現実はそう簡単ではない。どこにどんな情報があり、それがどこまで正しいかわからないケースが多い。この状況を打破すべく注目されているのが「社内Wiki」の構築だ。どんなメリットがあり、他の情報共有ツールとどう違うのだろうか。
インターネットで調べ物をする際に「Wikipedia(ウィキペディア)」を参考資料として利用している人は多いだろう。無料で利用できる百科事典であり、豊富なコンテンツが提供され、知りたいことの概要が網羅的に記述されていて、必要に応じて掘り下げていくことも簡単だ。
実は、ここに収録されている内容は特定の専門家が書いたものではない。多くの不特定多数の参加者が執筆し、記事の自由な複製や改変が認められている。いわば世の中の人たちの知識が集積されたものだ。このWikipediaと同様のものを組織内で作成するのが通称「社内Wiki」という取り組みだ。組織内の情報を組織内で共有し、管理するためのシステムであり、目的は組織内の人たちの知識や経験、ノウハウを集約して蓄積し、組織内で活用できるようにすることにある。
対象としては業務マニュアルに始まって、社内規定や総務・人事などの関連情報、経費精算など各種申請方法といった全社共通のルール、さらには特殊なナレッジやプロジェクトの報告など個別の業務に関するものも含まれる。
社内Wikiにはいくつものメリットがある。業務のノウハウを共有することで、誰もが同じことができるようになり、属人化を防ぐことができる。新しく組織に加わった人にとっては業務マニュアル代わりになり、引き継ぎにかかる時間を短縮できる。必要な情報を探しやすくなることも大きなメリットだ。問題解決に必要な情報がすぐに探し出せるし、内容が古ければその場で更新して最新のものにすることもできる。こうした迅速性や柔軟性はWikipediaのようなシステムだからこそ可能になる。
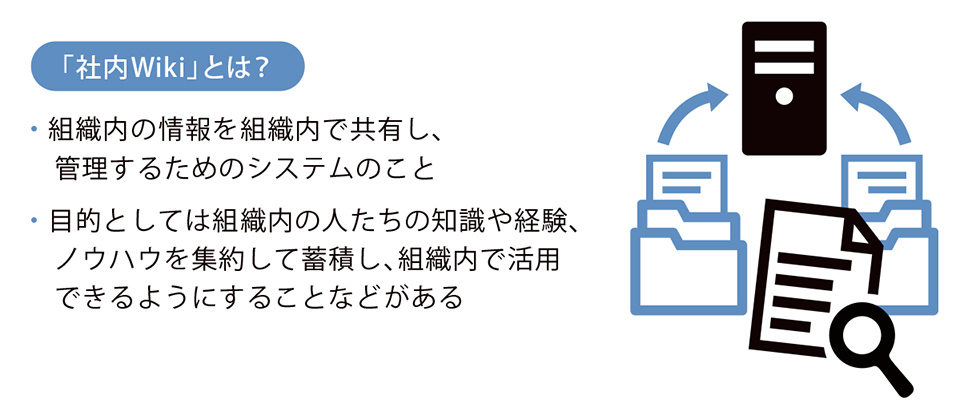
情報を共有するためのシステムは他にもさまざまなものがあるが、社内Wikiとは本質的に一線を画すものが多い。目的が違えば、提供される機能も違い、結果としてできることも違ってくる。
業務連絡などに使われるチャットは、瞬時にコミュニケーションするには便利なシステムだ。特定の相手やグループに確実にメッセージを届けることができ、リアルタイムで情報が共有できる。しかし、やり取りが多くなるほど過去の情報を探し出すのが難しくなる。情報を蓄積するには不向きなシステムだ。
プロジェクト管理システムは、プロジェクトメンバーと詳細な情報やスケジュール、進捗状況を共有するための便利な機能が豊富に提供され、さまざまな角度からプロジェクトの内容を確認することができる。しかし、あくまでもプロジェクトベースの情報共有になる。企業内の多種多様なファイルを格納してインターネットを介して参照できるようにするクラウドストレージも情報共有という面では威力を発揮する。大容量のファイルも扱えるし、どこからでもアクセスできる。アクセス権限ごとの制限を設けることも可能だ。
しかし、ストレージ内のファイルを探しやすくするための構造化ができていないために、ファイルの詳細な内容はファイルを開いてみないとわからない。目的に合ったファイルを探すには手間がかかることも多いのが現状だ。
Wikiのような機能を持ったシステムである社内Wikiとこれらの情報共有システムとの違いは歴然としている。専用のツールを使って社内Wikiを構築することが、詳細な情報を蓄積し、素早く引き出して活用する近道だと言えるだろう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆=高橋 秀典
【MT】
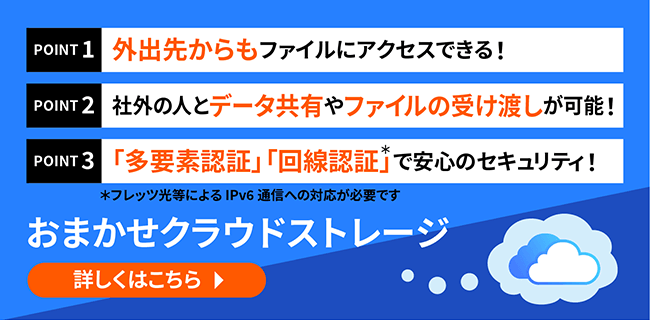
ビジネスを加速させるワークスタイル