
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
飲食店を複数経営しています。働き方改革でいろいろと法律が変わると聞きましたが、何か気を付けることはありますか?
A.働き方改革のポイントや支援施策を確認し、取り組むべき項目を整理しましょう
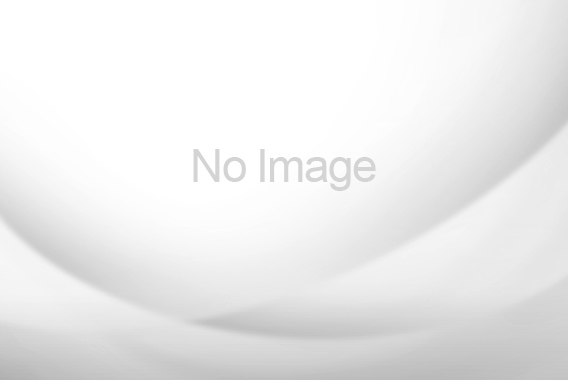
日本では長時間労働や、雇用形態による格差が深刻な社会問題となりました。少子高齢化の影響により、労働人口の減少に伴う深刻な人手不足も相まって、労働生産性(労働量に対する産出量・成果の割合のこと)の改善が大きな課題となっています。
「働き方改革関連法」は2018年6月29日に成立し、2019年4月1日から順次施行され、中小企業は2020年4月より適用開始となりました。
■働き方改革関連法(働き方改革一括法)
正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」
日本の法律における以下8つの労働法を一括し、取りまとめて改正する法律のこと
・労働基準法
・労働安全衛生法
・労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
・じん肺法
・雇用対策法
・労働契約
・短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
(略称:有期雇用労働法、パートタイム労働法、パート労働法など)
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(略称:労働者派遣法)
働き方改革関連法の推進のポイントは「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」です。
参考■厚生労働省「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて」(2019/4掲載)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
労働基準法において、「雇用から半年間の継続勤務(在籍期間)」「全労働日の8割以上を出勤していること」の2つの条件を満たしている場合、正規雇用労働者、非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイムやアルバイト労働者)など雇用形態にかかわらず、「労働者」に該当します。
次の項目については順守が義務づけられているため、現場での適切な情報管理と実態把握が必要になります。
■時間外労働の上限規制
原則として、時間外労働は月45時間・年間360時間が上限となる。
臨時的な特別事情によって労働者と雇用主双方が合意した場合でも、休日労働を含め、年720時間以内・複数月平均80時間以内、月100時間未満(1日当たり4時間程度)を時間外労働時間の上限とする。月45時間を超えることができるのは6カ月まで。
※違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑が適用される
■年次有給休暇の時季指定
雇用主は法定年次有給休暇の付与日数が10日以上あるすべての労働者に対して、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となる。
対象となる労働者には、管理監督者や有期雇用労働者も含まれる。
※違反した場合、30万円以下の罰金刑が適用される
■同一労働同一賃金
正規雇用労働者、非正規雇用労働者など、雇用形態の待遇格差の是正が必要となる。
研修勤続年数、成果、能力など職務内容や配置など労働条件が同一の場合は、基本給、賞与、各種手当は同一としなければならない。
・不合理な待遇差をなくすための規定の整備
・労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続き(行政ADR)の規定の整備
昨今ではフレックスタイム・テレワーク(※1)・短時間勤務制度など、社員一人ひとりが望む働き方について企業が柔軟に対応し、安定して仕事ができる環境づくりが求められています。
※1 Q. 従業員の育児や介護と仕事を両立させるために経営者ができることは?
また、働き方改革関連法により、管理監督者を含むすべての労働者に対してガイドラインにのっとった労働時間の正確な実績把握と、3年間の記録・保存が必要になります。違反した場合には罰則が適用されるため、2020年4月までに、情報管理の体制基盤やシステムの構築を整えておく必要があります。
参考■厚生労働省 働き方改革特設サイト(支援のご案内)
https://www.mhlw.go.jp/hatarakikata/index.html
2020年4月以降は、すべての中小企業に働き方改革関連法が適用されます。就業規則や社内規定によっては労働基準監督署への届け出が必要になる場合もあるため、雇用主はあらかじめ厚生労働省の定めるガイドラインに沿ったものかどうかポイントごとに見直し、社内の意識改善とシステムの導入を進めていきましょう。
※この記事は2019年11月8日現在の情報です
【T】
困りごと解決ビジネス専科