
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
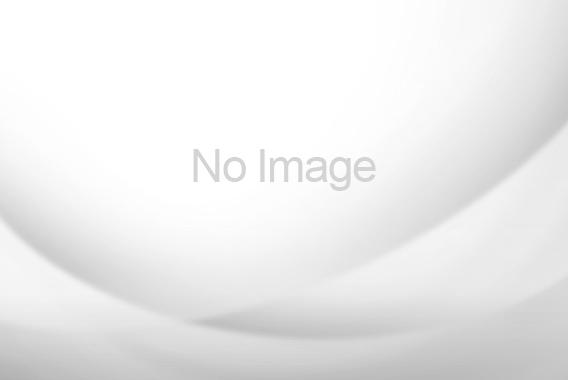 みなさんは、政治や経済に関する記事に、「〜する方向で検討に入った」とか、「〜の方針を固めた」といった表現が多用されていることにお気付きでしょうか。「〜に向けて最終調整している」という表現もよく出てきます。
みなさんは、政治や経済に関する記事に、「〜する方向で検討に入った」とか、「〜の方針を固めた」といった表現が多用されていることにお気付きでしょうか。「〜に向けて最終調整している」という表現もよく出てきます。
ほとんどの人は、いずれも「〜することがほぼ決まった」という意味だと、区別せずに受け取っているのではないでしょうか。
ところが、新聞記者はそれぞれの表現を使い分けています。明文化されているわけではないのですが、新聞記者の間では「こういう状況ではこの表現を使う」という一種のルールが共有されているのです。
<表現の例>
「〜の方向で検討に入った」=組織の一部で検討が始まっているが、計画が変更されたり中止されたりする可能性もかなりある
「〜の方針を固めた」=最終の手続きに向けて詳細が煮詰まっており、計画の一部が変更される可能性はあるものの実現性は極めて高い
「最終調整に入った」=「根回し」などを含む手続きは未了だが、あと一歩の段階に進んでいる
「〜することを決めた」=組織決定が終了した
こうした表現の意味を知っていれば「この話はまだ生煮えで、実現しない可能性も少なからずあるな」などと、報じられた内容の進捗状況や実現性を判断することができます。
しかし、こうした知識がなければ「大新聞が1面のトップで報じているのだから、明日にも実現するはずだ」と単純に考えてしまうでしょう。もし実現しなければ「誤報だ」「根拠もなく書いたな」と思ってしまうかもしれません。
実際、ネット上の書き込みを見ているとそう判断されている例が多いようです。しかし、同じ記事をプロが読むと、そもそも実現性が低いことが分かる表現が使われていたりするのです。
「見出し」の持つ意味も、一般の人にはあまり知られていません。実は、紙の新聞の見出しには、そのニュースの価値をどう判断しているかという情報が含まれています。こうした知識があれば、タテ見出しの長さや、文字の背景にある模様などを比べることで、特定のニュースについて「この新聞は他社に比べて重視しているな」といった判断ができます。複数のニュースを、ある新聞がどんな優先順位で報じているかも詳しく知ることができるのです。
ただし、見出しからニュース価値が分かるのは「紙」の場合だけです。同じ記事を転載したサイトで見ても、こうした情報はそぎ落とされています。つまり、「新聞社の価値観」を正確に知るには、ネットではなく「紙」で読み比べなければならないのです。
この手の「知られざる新聞表現のルール」はたくさんあります。こうした知識があるかどうかで、新聞から得られる情報の質はまったく違ってきます。当然、記事に書かれた情報を分析する際にも、その精度や深さに大きな差が生じるのです。
こうした情報格差が生じてしまった責任は、もちろん報道機関の側にあります。新聞記者だった私自身にも、「記事の表現にどんな意味を込めているのか」「どんな制約の下で書かれているのか」といった情報を、読者にきちんと伝えてこなかったという反省があります。
そこで、この連載を通じて、ニュースを正確に読むための基礎知識とノウハウをお伝えしていきます。
連載を一通り読めば、これまで紙の新聞を読んだことがなかった人はもちろん、長年、新聞を読んできた人でも、「以前よりニュースを深く理解できるようになった」という実感を持っていただけるはずです。
新聞記事を読み解く技術は、テレビやネットで流れる情報の分析はもちろん、ビジネスにも活用できます。例えば取引先が言外に発しているメッセージを正確に理解しようとするとき、相手の価値観や使う言葉の意味をあらかじめ知っておくことは不可欠でしょう。これは記者が使う独特の表現を踏まえて記事を解釈したり、見出しなどから新聞ごとの価値観の違いを読み取った上で報道を眺めたりするのと同じです。これからお話しする「新聞の正しい読み方」を通じて、ビジネスに必要な情報分析のスキルを磨いていただければと思います。
執筆=松林 薫
1973年、広島市生まれ。ジャーナリスト。京都大学経済学部、同大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。東京と大阪の経済部で、金融・証券、年金、少子化問題、エネルギー、財界などを担当。経済解説部で「経済教室」や「やさしい経済学」の編集も手がける。2014年に退社。11月に株式会社報道イノベーション研究所を設立。著書に『新聞の正しい読み方』(NTT出版)『迷わず書ける記者式文章術』(慶応義塾大学出版会)。
【T】
情報のプロはこう読む!新聞の正しい読み方