
オフィスあるある4コマ(第58回)
期待外れ⁉の光回線
メディアリテラシーで特に重要なのが「情報の信頼性を見極める力」です。しかし、報道に携わった経験でもない限り、メディア情報の信頼性を判断するのは至難の技です。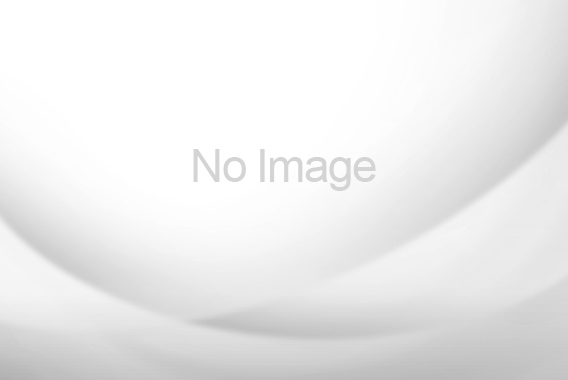
では、どうすれば一般の人でも情報の質を見分けることができるのでしょう。
最も簡単で有効性が高いのが、実は「誤字脱字」に注目する方法です。私は、自分の経験から、誤字脱字が多い記事は「情報としての質が低い可能性が高い」と判断してもいいと考えています。
この方法は、新聞記事はもちろん、ブログなどネット情報にも当てはまるので、ぜひ覚えておいてください。
あまりにも単純で、拍子抜けしたかもしれません。しかし、「記事が作られる過程」を考えると、これが重要である理由が理解できると思います。
新聞にしろブログにしろ、執筆や推敲(すいこう)の段階で誤字脱字に気付けば、必ず修正するでしょう。大した手間ではないのですから、あえて放置するということは考えにくいわけです。
にもかかわらず、そのまま掲載されたということは、原稿の段階で筆者も含め、誰もミスに気付かなかったということを意味します。つまり、筆者がきちんと読み返していない上に、「複数の人の精査をくぐっていない」という可能性が高いのです。
「情報の質」を考える上で、こうした「記事ができるまでの工程」は決定的に重要な意味を持ちます。
記事の正確性は一義的には書いた本人の能力や注意力などに左右されます。ただ、原稿が完成してメディアに掲載されるまでの工程に着目すると、
【チェックした人の数】×【チェック参加者の能力】×【チェックの回数】
で決まると言ってもいいでしょう。このとき、誤字脱字があるということは、3つの項目のいずれかのレベルが低い可能性を示唆しているのです。
ヤフーニュースのトップページに掲載されるような記事でも、ブログの場合は新聞記事の転載に比べ、かなりの確率で誤字脱字があります。これは筆者が書いたものをそのまま載せていたり、編集者がいてもほとんどチェックしていなかったりするからだと考えられます。
中には1つの記事に2〜3個も誤字脱字があって、本人すら読み返していないと思われるものもあります。そういう記事は、内容を検証していくと明らかな事実誤認や、根拠が不確かな記述が見つかるケースが少なくありません。
執筆=松林 薫
1973年、広島市生まれ。ジャーナリスト。京都大学経済学部、同大学院経済学研究科修了。1999年、日本経済新聞社入社。東京と大阪の経済部で、金融・証券、年金、少子化問題、エネルギー、財界などを担当。経済解説部で「経済教室」や「やさしい経済学」の編集も手がける。2014年に退社。11月に株式会社報道イノベーション研究所を設立。著書に『新聞の正しい読み方』(NTT出版)『迷わず書ける記者式文章術』(慶応義塾大学出版会)。
【T】
情報のプロはこう読む!新聞の正しい読み方