
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
2019年4月から施行される「働き方改革関連法」。この法律は長時間労働を是正し、多様な働き方の実現をめざしている。その大きな柱となっているのが「残業時間の上限規制」だ。
長時間労働は心身をむしばむ要因となり、会社側から見れば病欠や長期療養、はたまた退職で貴重な戦力を失うきっかけになりかねない。過労死に至ることさえある。「karoshi」という単語が英和辞典に載るほど、日本の長時間労働は問題になっている。働く側から見ても、長時間労働は、心身の健康を損なう原因になりかねない。
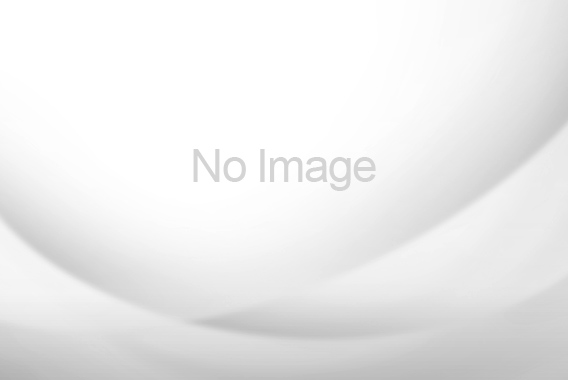 こうした問題を解決しようとするのが、働き方改革関連法の残業時間の上限規制だ。法律の内容を見ていこう。
こうした問題を解決しようとするのが、働き方改革関連法の残業時間の上限規制だ。法律の内容を見ていこう。
労働基準法(以下、労基法)では、1日8時間、1週40時間が法定労働時間とされる。それを超えて従業員を残業させるには、時間外労働として、労基法第36条を根拠とした、いわゆる「36協定」を従業員の過半数の代表と結び、行政官庁へ届け出なければならない。
この時間外労働の限度については、現行法の下でも基準が設けられている(限度基準告示)。ただ、会社がこれに違反した場合であっても、罰則はない。また、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない臨時的な特別の事情がある場合には、協定を結ぶことにより限度時間を超えて労働させることが許されている。長時間労働の抑止として不十分であった。
そこで、働き方改革関連法案では、現行の限度基準告示を法律(労基法)に格上げし、違反に対しては罰則の対象とするとともに、臨時的な特別の事情がある場合であっても、上回ることのできない上限を設定することとした。これが新しい点だ。
ポイントは、次の通り。
(1)原則的な限度時間は、1カ月45時間、かつ、1年360時間まで(休日労働を含まず)。
(2)特別の事情がある場合であっても、1年720時間まで(休日労働を含まず)。
(3)(2)の場合、以下のすべてを満たす必要がある。
a.単月で100時間未満(休日労働を含む)。
b.2~6カ月の平均で月80時間以内(休日労働を含む)。
c.月45時間を上回る回数は年6回まで。
(4)会社がこれらの規制に違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。
(3)b.に説明を加えると、例えば前月の残業時間が80時間、前々月の残業時間が90時間だった場合、(3)a.の要件は満たすが、過去2カ月の平均が85時間になり、違反だ。同じように、過去2~6カ月の平均も、80時間以上にできない。
(4)の通り、規定に違反した雇用主には罰則が科せられる。経営者には厳守が求められる。
残業時間の上限規制は一定の効果が期待できる。しかし、問題となるのがいったんタイムカードを押してから自席に戻って仕事を続けるといった「隠れ残業」だ。
隠れ残業は、タイムカードを見ただけでは実態を把握できない。しかしITを活用し、社内システムへのアクセスログや、メールの送受信ログといったデータをチェックすれば、実際の労働時間にかなり迫れる。隠れ残業も労働時間だ。労働基準監督署の臨検監督や残業代請求の裁判では、そこまで調べられる。規定に違反したとなれば、「半年以下の懲役か30万円以下の罰金」が科せられる可能性もある。
残業時間の上限規制に対応するには、労働時間の正確な把握が不可欠だ。在宅勤務などのテレワークを活用している企業は、より一層、労働時間管理に力を入れなければならないだろう。在宅勤務の場合、延々と仕事をしてしまう可能性がある。パソコンやタブレットから打刻できる勤怠管理システムを導入するとともに、システムへのアクセスログなどをチェックして、より正確な労働時間を把握する必要がある。
現在、管理職などの管理監督者は、36協定の除外対象だ。働き方改革関連法案の残業時間規制の対象からも管理職は外れる。しかし、2019年4月からは、企業が管理職の労働時間を把握するよう義務付けられることになった。一般の従業員に対してと同じく、企業はタイムカードやパソコンなどを使って、管理職の労働時間を記録し、3年間保存しなければならない。労働時間の把握で、管理職の長時間労働にも歯止めを利かせるのが狙いだ。
長時間残業を放置していると、ブラック企業とレッテルを張られてしまい、その情報がインターネットなどを通じて世の中に広まってしまうと、人材が集まらなくなる可能性もある。労働時間が長過ぎると生産性が低下するばかりでなく、離職率もグンと高まり、結果事業の継続さえ困難になることもあるだろう。
そういった事態を回避するためにも、ITツールを活用して隠れ残業やテレワークでの長時間労働を抑えつつ、働き方改革関連法の残業時間規制に対応する。法の順守が、結果的には事業の継続・発展につながるのはいうまでもない。
監修=上野真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)
1995年日本大学法学部卒業、1997年同大学院法学研究科博士前期課程修了。2003年10月、弁護士登録。2007年10月、中野通り法律事務所開設。現在に至る。
執筆=Biz Clip編集部
【MT】
急務!法対応