
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
正社員採用、終身雇用といった日本的経営の慣習が変化している。総務省が行った2017年の労働力調査によれば、今や有期契約社員、派遣社員、パートタイマーなどの非正規労働者が雇用者全体の4割近くに達するようになった。
しかし、こうした非正規労働者と正社員が同等の待遇を受けていないケースも珍しくない。2019年4月から順次施行される働き方改革関連法(2018年6月29日成立)では「同一労働同一賃金」を柱の1つとする。同一の労働を行えば、同一の賃金が支払われる原則を徹底する方針だ。不合理な待遇格差の解消を企業に義務付け、非正規労働者の待遇改善をめざす。
まず、簡単に「同一労働同一賃金」を実現する具体的な制度について見る。働き方改革関連法により、(1)から(3)の整備がなされた。
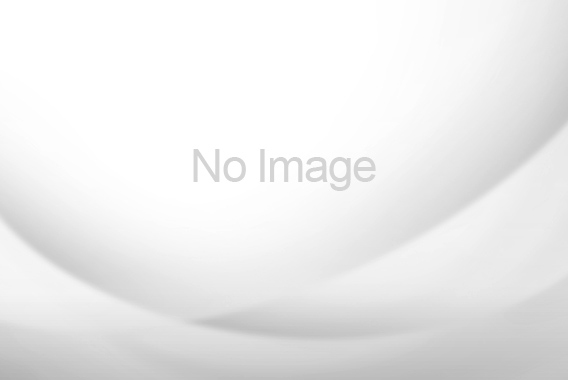 (1)不合理な待遇差をなくすための整備
(1)不合理な待遇差をなくすための整備
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、不合理な待遇差を設けることが禁止される。どのような待遇差が不合理に当たるかについては、ガイドラインを策定して、明確にする。
(2)労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」など、自身の待遇について説明を求めることができる。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければならない。
(3)行政による事業主への助言・指導などや裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行う。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となる。
これらの整備により、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を実現し、「『非正規』という言葉をこの国から一掃する」(2018年通常国会冒頭の安倍総理による施政方針演説)というのが、改正の狙いである。
以下では、(1)に関して、最高裁判決と「同一労働同一賃金ガイドライン案」について簡単に見ておく。
働き方改革関連法が成立する直前の2018年6月1日、同一労働同一賃金に関して最高裁が2つの判決を出した。振り返っておこう。
1件目は、60歳で定年退職して再雇用されたトラックドライバーの例だ。給与額減少を不服とし、同等の賃金を要求した。職務内容は退職前と同じだった。最高裁は、精勤手当と超過手当(時間外手当)に関して、不合理な待遇差を禁じた労働契約法第20条に違反しているとの判断を示した(長澤運輸事件)。
もう1件は、有期契約社員のドライバーが、正社員と同様の待遇を求めたもの。正社員との待遇格差が、労働契約法20条に違反するという理由だ。最高裁は無事故手当、作業手当、皆勤手当などで差をつけるのは違反と判断。原告側の主張を大幅に認めた(ハマキョウレックス事件)。
裁判になると、原告となる労働者だけでなく、会社側も多大な労力・時間・費用を費やす。働き方改革関連法では、同じ業務や成果には平等に賃金を支払うよう求めている。法に触れる待遇格差を設け、裁判になる事態は避けなければならない。
どのような待遇にすれば、同一労働同一賃金といえるのか。前述の2つの裁判でも一審と控訴審、最高裁判決の間に違いが出ている。判断は容易ではない。
厚生労働省は「同一労働同一賃金ガイドライン案」(2016年12月)を作成している。このガイドライン案に沿って、問題になる待遇と問題にならない待遇を見てみよう。ただし、今後の判決次第で判断基準が変わる可能性はある。
(1)労働者の職業経験・能力に応じて基本給を支給する会社の場合
〈問題にならない待遇〉
A社では、職業能力の向上のための特殊なキャリアコースを設定している。正社員のX氏は、このキャリアコースを選択して職業能力を習得した。これに対し、パートタイム労働者のY氏はその職業能力を習得していない。A社はその職業能力に応じた支給をX氏に行い、Y氏には行っていない。
〈問題になる待遇〉
B社において、派遣社員のY氏に比べて多くの職業経験を有することを理由に、X氏に対してY氏よりも多額の支給をしている。しかし、X氏のこれまでの職業経験は現在の業務に関連性がない。
正社員が豊富な職業経験を有しているだけの理由で多額の支給をしていれば、法律に反する可能性がある。明確な職業能力を習得しているかどうか、あるいはその職業経験が現在の業務に関連しているかどうか、棚卸しをしたほうがいい。
(2)労働者の業績・成果に応じて基本給を支給する会社の場合
〈問題にならない待遇〉
勤務時間が正社員の半分であるパートタイマーのX氏が、正社員に設定されている販売目標の、半分の数値に達した。このとき、A社は正社員が販売目標を達成した場合の半分の額を支給している。
〈問題になる待遇〉
B社は正社員が販売目標を達成した場合、基本給の一部を業績・成果に応じて支給している。パートタイマーであるY氏が正社の販売目標に届かない場合には支給を行っていない。
正社員とパートタイマーでは労働時間が異なる。基本給の一部を業績・成果に応じて支給する場合、正社員に設定している目標に達していない理由でパートタイマーに支給を行わないと、違法になり得る。
(3)労働者の勤続年数に応じて基本給を支給する会社の場合
〈問題とならない例〉
A社は、契約社員のX氏に対し、当初の雇用契約開始時から通算して勤続年数を評価し基本給を支給している。
〈問題となる例〉
B社は、契約社員のY氏に対して当初の雇用契約開始時から勤続年数を通算せずに、その時点の雇用契約期間だけで評価して基本給を支給している。
契約社員は、1年、2年といった期間で雇用契約を交わす。継続して勤務する場合は契約を更新する。勤続年数に応じて基本給を支給する場合、直近の契約のみを勤続年数にすると、アウトとなる可能性がある。契約を開始した時点からの年数で評価しなければならない。
こうした例のほか、ガイドラインでは賞与、各種手当てについても待遇を同等にするよう求めている。
日本企業の多くで行われている出向については、非正規と正規の格差解消をめざす働き方改革関連法には直接関係しない。ただ、今後、さまざまな事例が出てくる可能性もある。働き方改革関連法成立後も、裁判所の判断を注意深く見ておく必要があるだろう。
現在、人手不足が深刻な課題だ。有期契約社員、パートタイマーといった非正規社員の待遇改善は、人手不足の解消に有効だ。働き方改革関連法の施行をきっかけに、待遇格差の解消に努めたい。結果的に企業の利益にもつながるはずだ。
監修=上野真裕
中野通り法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)
1995年日本大学法学部卒業、1997年同大学院法学研究科博士前期課程修了。2003年10月、弁護士登録。2007年10月、中野通り法律事務所開設。現在に至る。
執筆=Biz Clip編集部
【MT】
急務!法対応