
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
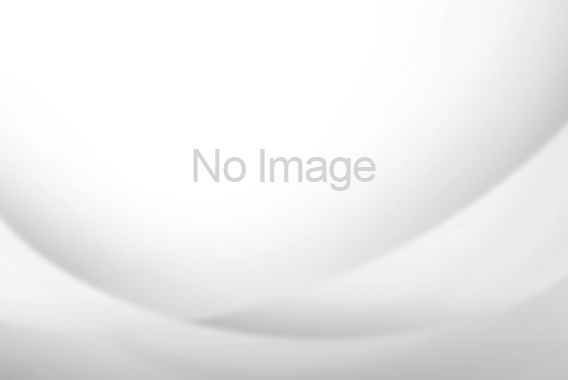
経営強化のためにコストを削減したいが、何から手を付けていいのか分からないと悩む企業経営者は多いかもしれません。まずは何からコストカットすべきなのでしょうか。本記事ではすぐにでも実行できる、コスト削減のアイデアについて紹介します。
目次
・企業におけるコストには「固定費」と「変動費」がある
・コスト削減の方法
・コスト削減の手順
・コスト削減のポイント
・まとめ
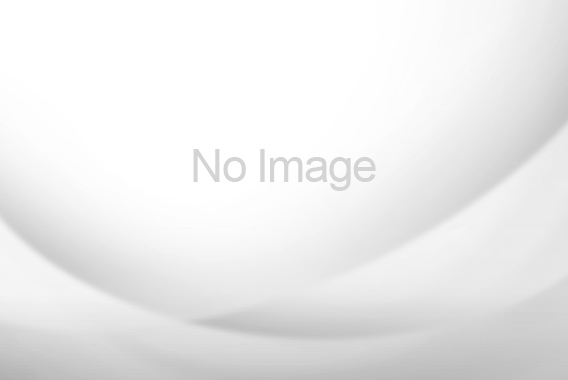
企業が経営を続け、成長する過程では、さまざまなコストが発生します。コストは大きく分けると、定期的に一定の支払いが発生する「固定費」と、支払額が都度変動する「変動費」があります。
コストの中にはどのようなものがあるのか、以下に列挙します。
人件費
企業が支払う固定費のうち、特に大きな割合を占めるのが人件費です。人件費は従業員の労働に対して支払う給与、各種手当、賞与、退職金などの一時金のほか、福利厚生にかかる費用なども含まれます。
コストを削減する目的で人件費をカットし過ぎると、さまざまな問題が発生します。例えば福利厚生などの制度が改悪され、従業員が働きに見合った給料や賞与を受け取れていないと判断すると、不満を募らせた従業員の士気が下がり、業績の悪化や、人材流出につながります。
採用コスト
事業で成果を残すためには、人的リソースの確保が不可欠です。そのため、企業活動では人材の採用にもコストがかかります。
採用コストには大きく「内部コスト」と「外部コスト」の2つに分かれます。内部コストは社内に発生するコストで、求職者や内定者に支払う交通費、社内研修や懇親会の費用などが含まれます。採用面接を行い、内定者向けに懇親会や研修を行ったにも関わらず、内定辞退者が出た場合、採用コストはかさむことになります。
外部コストは、社外に支払うコストです。求人広告や求人サイトへの掲載費、人材紹介サービスの利用料、会社説明会や面接を実施する会場費、企業PR映像やパンフレットなどの作成費、内定者研修費などが相当します。特に広告費や人材紹介サービスの利用料は額が大きくなりがちです。コストと成果が見合っているか、検証することも大切です。
オフィスコスト
オフィスを維持するためのコストも必要になります。自社ビルでない場合はオフィスの賃料が必要となるほか、空調設備や机などの費用、プリンターをはじめとしたOA機器の購入費・リース代、システムやアプリケーションの利用料、コピー用紙や筆記用具など消耗品費、事務所の電気代や水道代などの光熱費も発生します。従業員が増えるほど、オフィスコストも増加します。
ビジネスシーンにはさまざまなコストが存在しますが、そのほとんどはビジネスを継続するために必要なコストとなります。どのコストを削減するのが良いのか、実現しやすいコスト削減のアイデアを6つ紹介します。
オフィスの作業環境を見直す
内勤の従業員にとって、一日の大半を過ごす場所がオフィスです。そのオフィス環境を少し見直すことで、コストを抑えられる可能性が高まります。
例えば暖房や冷房が効きすぎている場合、空調システムを適正に設定するだけで電気代が節約できます。室温や湿度が適切に保たれて、作業環境が心地良いものになれば、生産性の向上も期待できるでしょう。
従業員の定着率を高める
従業員の採用と育成にかかるコストは、事業を円滑に回すためには必要なコストです。しかし、せっかく採用した従業員が仕事内容や職場環境、給与などに不満を募らせ退職してしまうと、さらに新たな従業員を確保したり、研修を行ったりする必要が生じ、コストがかさむことになります。つまり従業員の定着率を高めることは、結果的にコストを抑えることになるのです。
従業員の定着率を高めるためには、従業員がやりがいをもって仕事に取り組める環境・仕組みづくりが不可欠です。給与や賞与の根拠になる人事評価基準も、従業員が納得感を得られるような内容で策定しましょう。
オフィスコストを削減する
コロナ禍の影響で、テレワークを導入する企業は少なくありません。テレワークを一過性の措置ではなく、恒常的なスタイルとして制度化すれば、オフィスコストを長期的に削減できる可能性が生じます。オフィスへ出社する従業員を減らし、フロア面積を縮小すれば賃料や光熱費を抑えることができる他、賃料の安い地域にオフィスを移転するという選択肢も生まれます。さらに、筆記用具や事務用品など、消耗品の在庫数や発注数も抑えられる可能性があります。
エネルギーコストを削減する
コスト削減の基本は、固定費を下げることです。よって電気代や水道代などの光熱費や、電話回線代といった固定費を見直し、不要な支出をなくすのも良いアイデアです。照明を蛍光灯からLEDへの切り替えや、電気会社・通信会社の契約プラン見直しも、コスト削減につながる可能性があります。
通勤費・交通費・出張費を削減する
従業員に支払う通勤費・交通費・出張費がかさんでいる場合もあります。いずれも必要なコストではありますが、例えばテレワークを行っている従業員が、1時間程度の社内会議に出席するためだけに出社している場合、コスト削減という観点から検討する余地が生じるでしょう。
最近ではWeb会議ツールやビジネスチャットツールなどのコミュニケーションツールが次々と登場しています。これらのツールに置き換えれば、通勤費・交通費・出張費の削減に結びつくかもしれません。
ペーパーレス化する
いわゆるペーパーレス化も、コスト削減しやすいポイントです。紙に印刷して紙の資料を残すスタイルを廃止し、PDFなど電子データをメインに運用すれば、紙代やインク代が削減できるほか、紙書類を保管する倉庫の維持費用も不要になります。結果的に紙ごみも減ることになるため、環境に配慮した取り組みに積極的であるという企業姿勢がPRできるというメリットも生じます。

実際にコスト削減に取り組む際の作業フローについて、3つの手順に分けて解説します。
現状のコストを把握する
コストを削減しようとしても、どのコストがどの程度発生しているのかを把握していなければ、対策の施しようがありません。最初にすべき事柄は、あらゆるコストについて全体像を把握し、現状の課題確認を行うことです。複数の課題を洗い出し、どの課題から取り組んでいくべきか、市場の動向や経営方針をもとにして優先順位を付けていきます。
このとき大切なのは、額の多寡にかかわらず、すべてのコストを洗い出すことです。さほど重要でもなく、惰性で支払い続けているようなコストが見つかれば、有力な削減対象となります。
削減計画を共有し実行する
課題となるコストを把握したら、次はどのように削減を進めていくのか、具体的な計画を検討します。計画の策定後は、実際に削減に取り組む従業員に対して計画を共有し、実行のフェーズに入っていきます。
ここでの重要なポイントは、従業員に対し、コスト削減の明確な目的意識を共有することです。なぜ自社にとってコスト削減することが必要なのかという背景や理由から説明し、従業員へ理解を促します。コスト削減プロジェクトは一部の部門や部署だけではなく、全社を挙げて取り組むべきものです。現場の従業員がコスト削減の目的やビジョンを理解することで、実行するうちに目標が本来の意図から外れていくことが防げます。
実施した結果を分析・検証する
コスト削減は、一度実施したらそれで終わりではありません。施策を実施した効果はどの程度あったのか、定期的に分析し検証することが重要です。施策の成果を分かりやすく“見える化”すれば、次の改善点も見いだしやすくなるでしょう。加えて、施策に協力した従業員に成果を報告することで、次の段階でも従業員の協力を得やすくなります。
このようにコスト削減の施策、実施、検証、フィードバックを積み重ねていくことで、不要なコストを的確に減らしていくことができます。
企業がコスト削減を成功させるために、特に重要な3つのポイントについて解説します。
期待される効果が大きいものから取り組む
コスト削減は、より大きな効果を見込めるものから優先して実施することが重要です。例えば光熱費などエネルギー関連のコスト削減を実施した場合、年間で大きな成果をもたらす可能性があります。
不要なコストを見極める
すべてのコストをピックアップして、「不要なコスト」と「必要不可欠なコスト」を正しく見分けることも大切なポイントです。あらゆるコストを手当たり次第ターゲットにするのではなく、あくまで不要なコストを削減対象としなければなりません。
必要なコストまでカットしてしまうと、逆に仕事が非効率になり、時間や手間の浪費につながります。その結果、生産性の低下、売り上げ減少などのマイナスの影響が大きくなります。特に人件費を過剰に削減すると、現場で働く従業員に不満が生まれ、モチベーションやエンゲージメントの低下や離職、さらに企業イメージの低下につながることもあります。
定期的にコストの見直し・改善を行う
ひとたびコスト削減策を実施し、成功を収めたとしても、社内外の環境変化や市場動向によって、新たな課題が生まれることも多々あります。コストを適切に削減できているか、定期的に効果を計ることが大切です。コストの見直しを行うタイミングを決めて、業務のルーティンの一部として取り入れるべきでしょう。
企業経営においては何らかのコストが必ず発生しますが、日々支払っているコストの中には必要でないものも含まれている可能性があります。売り上げに占めるコストの割合が大きければ企業の利益は減ってしまいますが、不要なコストを削減できれば利益が拡大できるのです。積極的にすべてのコストを洗い出して不要なコストを見いだし、計画的に削減し検証していくことをおすすめします。固定費の見直しなど取り組みやすい内容から検討すれば、やがては収益も向上していくでしょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【MT】
覚えておきたいオフィス・ビジネス情報のキホン