
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
公開日:2023.03.03
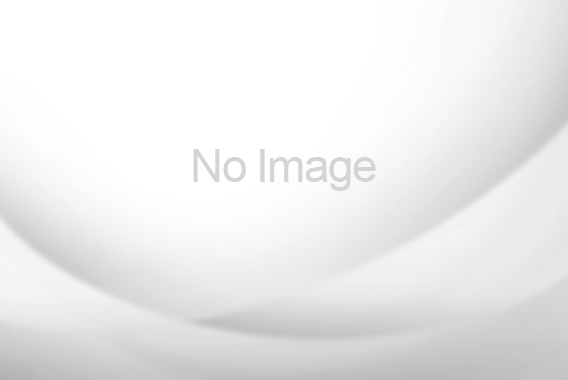
「DX」(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を耳にしたことがある人は多いでしょう。経済産業省の「デジタルガバナンス・コード2.0」では、DXは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義され、多くの企業が注目しています。DX化によって従来の企業が抱えていた課題を解決することが可能です。本記事では、その目的や導入の背景、メリットなどを解説します。さらに、すでにDX化を成功している企業の導入事例も併せて紹介します。
目次
・DX(デジタルトランスフォーメーション)とはデジタルによる変革のこと
・DX化の目的
・DX化が注目される背景
・DX化のメリット
・DX化のステップ
・【産業別】日本企業のDX化事例
・まとめ
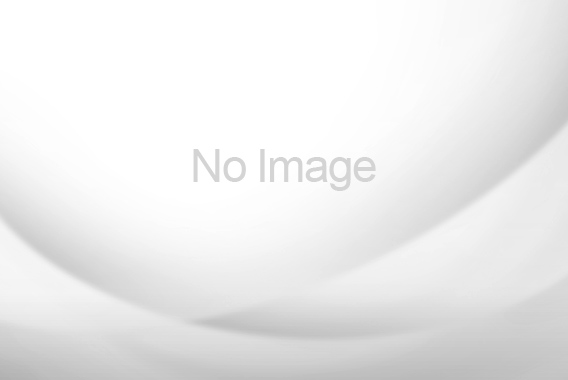
「DX」は「Digital Transformation」の略で、直訳すると「デジタルによる変革」という意味になります。つまりDXを推進することは、従来型のビジネスからデジタル技術を活用したビジネスへと変革し、競争力があり価値ある企業をつくり出す活動ということになります。
IT化・IoT化・ICT化との違い
「DX化」に似た言葉として「IT化」「IoT化」「ICT化」があります。これらはいずれもDX化とは意味が異なります。
まずITとは「Information Technology」の略で、コンピューターやソフトウエア、インターネット通信などのデジタル技術全体のことで、IT化とは環境をアナログからデジタルに変換することを示します。
次にICTは「Information and Communication Technology」の略で、インターネットやコンピューター関連など、人と人がつながるデジタル情報を通信する技術のことで、ITに近い意味合いをもちます。そしてICT化とは、通信環境を含めたデジタル化を進めることを意味します。
そしてIoTは「Internet Of Things」の略で、直訳すると「モノのインターネット」を意味します。IoTはモノをインターネットにつなげる技術、あるいはインターネットに接続する各種機器のことで、具体的にはスマートスピーカーやIoT家電、工場内の機械装置などが挙げられます。
まとめますと、「DX化」はデジタルによる変革という幅広い意味を有しますが、「IT化」「IoT化」「ICT化」は、より狭義の意味を有する言葉ということになります。
BX・CX・UXとの違い
DXに似ている言葉としては、この他にも「BX」「CX」「UX」があります。いずれも、主にデジタルマーケティングの文脈で使用される言葉です。
BXは「Business Transformation(ビジネストランスフォーメーション)」の略で、デジタル化によりビジネスシステムの改革、業務改善を行うことです。
またUXは「User Experience(ユーザーエクスペリエンス)」の略で、ユーザー体験を意味します。ユーザーが商品・サービスを使用した際の体験や使用する際の価値などを示します。
CXについては「Customer Experience(カスタマーエクスペリエンス)」の略です。顧客体験という意味で、顧客が企業の商品を購入・使用したり、Webサイトや営業担当者、カスタマーサポートなどのサービスを受けて体感したすべての経験を示します。UXとよく似ていますが、CXは商品・サービスの利用前後まで含む、より幅広い体験を表します。
DX化を推進する場合、何のためにDXを実行するのか、具体的な目的を立てておくことが重要になります。例えば、重要なデータを取り扱う人事・経理向けのDXでは、データのデジタル化とテレワークの推進といった手法が存在しますが、これらはいずれもITの活用による業務効率化を目的に行うものとなります。
顧客との関係性が重要な営業・マーケティングのDX化では、顧客とのコミュニケーションを円滑化し、顧客満足度を向上させるなどの目的を設定することが可能です。DX化を進めることで、管理システムの導入による顧客情報の一元管理や、チャットボットの導入による顧客対応の負担軽減といった目的が達成できます。
企業・組織全体としてのDX化の目的としては、「企業の競争力を高めて、市場での優位性を確立すること」などを挙げるべきでしょう。その上で、業務効率化や生産性向上、作業負担の軽減、効率的な顧客データの活用といった目標を具体的に設定することで、DX化にたどり着くことが可能になります。
日本でDX化が注目されるようになった大きなきっかけとしては、2018年9月に経済産業省が発表した「DXレポート」があります。このDXレポートでは、後述する「2025年の崖」に備えるためにはDXの実現が不可欠として、DX化に取り組まなかった場合のリスクやDX実現に向けたシナリオがまとめられています。
2025年の崖とは、2025年に主流システムのサポート終了や、ハードウエアの老朽化の進行、IT人材不足の拡大などで、IT関係のトラブルが集中し、最大で年間12兆円の経済損失が生じる悲観的な予測のことです。同レポートでは、既存システムを見直し、新しいデジタル技術への移行、新たなビジネスモデルの創出を行わないと、データを活用できずに市場競争の敗者となると予想しています。
つまりDX化は、この2025年の崖を乗り越えるために日本政府主導で行われている取り組みともいえます。
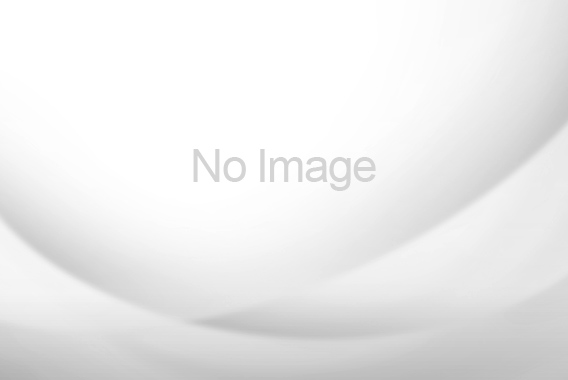
DX化には、生産性の向上、人材不足の解消、業界での優位性の獲得といったメリットが期待できます。
メリット1:生産性の向上
DX化により業務のIT化が進むと、業務効率化につながり、作業量の軽減さらにはヒューマンエラーの減少も期待できます。さらに、これまでは人の手で行われていた営業やマーケティング活動が自動化できます。デジタル化によってデータを有効活用できるようになる他、人的リソースをよりコアな業務に回せるため、生産性の向上にもつながります。
メリット2:人材不足の解消
生産性の向上により、残業時間の減少や従業員の負担軽減なども可能になります。例えば、デジタル化によりテレワーク・リモートワークで仕事を進められるようになれば、通勤時間を削減できます。働き方改革も進み、働きやすい環境を整えることで求職者の注目が集められれば、人材不足の解消にもつながるでしょう。
メリット3:業界での優位性を獲得
DX化を推進することで、事業や業務で使われる資料の多くがデータで管理されることになります。このデータを分析することで、市場の変化や顧客活動の変化を把握し、より確度の高いマーケティング活動を行うことも可能になります。効果的なマーケティング活動が実現できれば、市場や業界で優位性の獲得も期待できます。
DX化を進める方法はさまざまですが、大きく以下の流れになります。
ステップ1:自社の課題の洗い出し
DX化を進めるにあたり、まず自社の現状を洗い出し、抱えている課題を明確にします。業務プロセスや製品・サービスなどから、自社の強みや弱みについて洗い出すことが大切です。自社の業務プロセス上、あるいは製品・サービス上で抱える課題を明確にすると、課題を解決するためのアプローチ方法が見つけられます。その後、具体的にどこへどのような施策を実施すべきかを検討します。
ステップ2:目的の明確化
DX化の目的を明確に定めることも重要です。「顧客情報を共有して営業やマーケティング、商品開発に生かす」など、DXでどのような課題を解決するのかを明示します。設定した目的は従業員やスタッフに伝え、全員が目的を理解し、DX化により業務がどのように改善されるかを把握することで、目的意識を共有して取り組めるようになります。
ステップ3:ツールの選定
DX化を進めるうえで、どのITツールを選定するのかも重要なポイントの1つです。ITツール選定時は、従業員の使いやすさを考慮しなければなりません。使いにくいITツールの場合、従業員から敬遠され、DX化が進まない要因となる恐れがあります。
ステップ4:PDCAを回す
DX導入後は、現状を評価してPDCAを回します。DX化は一度で完了するものではないため、評価、改善を繰り返して徐々に改善していくことが大切です。ビジネスは、市場や社会の変化にも柔軟対応する必要があります。社会の変化に取り残されないためにも、PDCAサイクルを定期的に繰り返して自社の状況を確認する必要があります。
運送業、サービス業など、さまざまな業界でDX化を行い、成功した企業があります。ここでは国内企業のDX化に関して、産業別に5つの事例を紹介します。
【運送業】RPAを用いて作業効率化
RPA(Robotic Process Automation)は、人が取り組んでいたルーティンワークなどの業務を、AIや機械学習などを活用して自動化するツールです。A社は表計算ツールにより作成された請求書関係のデータをRPAで自動転記する仕組みの導入により、作業時間を数時間から数十分へと大幅に短縮。従業員の作業負担も軽減しました。
【サービス業】顧客データの分析でCX向上
B社は、自社ECサイトを中心としたマーケティングにDXを活用しました。ビッグデータとAIを活用して顧客データを分析し、マーケティングに活用することで、顧客のニーズをつかむことに成功。CXの向上も実現しました。
【金融業】キャッシュレス決済の導入
C銀行は、口座を有する顧客向けにDX化の一環としてキャッシュレス決済サービスを導入しました。同決済アプリは、利便性の高さから商業施設などで多くの人が利用するようになり、利用可能店舗数も右肩上がりが続いています。
【教育業】時間や場所にとらわれない授業
D社は、DX化の一環として中学生・高校生向けにオンライン映像授業サービスを構築しました。数千本の映像事業を用意することで、利用者は希望する授業を好きな時間に受けられるようになり、学習効率も向上。利用者も増加しているといいます。
【建設業】深層学習を活用した生産性の向上
E社は、過去に設計した図面データとAI技術を組み合わせて深層学習に使用し、自動設計やAI設計が行えるシステムを構築しました。これまでの画一化された設計ではなく、多様化するユーザーニーズに対応できるような、より高度な設計や建設手法の研究に活用しています。
DX化とは、デジタル技術を活用して人々の生活やビジネスを良い方向へ変革させることです。デジタル技術を取り入れ、活用できる人材の育成や組織の構築を行うことにより、業務の効率化、マーケティング活動の効率化、製品・サービスの改善が期待できます。
日本政府は、2025年の崖への対応としてDX化の促進を提唱しています。DX化を進めることで、企業は将来発生する恐れのあるリスクに備えるだけでなく、ITを活用した新しいビジネスモデルの創出にもつなげられるでしょう。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【MT】
覚えておきたいオフィス・ビジネス情報のキホン