
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
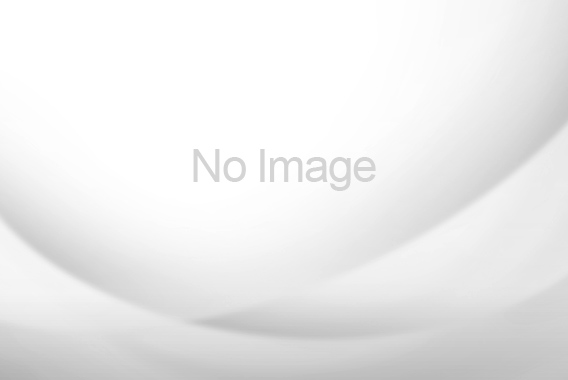
2023年10月から開始が予定されているインボイス制度は、特にBtoBビジネスを行う企業や事業者にとって、仕事の進め方が大きく変わる可能性があります。この記事では、インボイス制度の内容や申請方法の手順、インボイス制度に登録しないことによるデメリットについて紹介します。
目次
・インボイス制度とは消費税の仕入税額控除の新たな仕組み
・インボイス制度によって変わること
・なぜインボイス制度がスタートしたのか
・インボイスの登録申請の手順
・インボイスの申請に必要なもの
・インボイスを登録しなかったら?
・インボイス制度の注意点
・まとめ
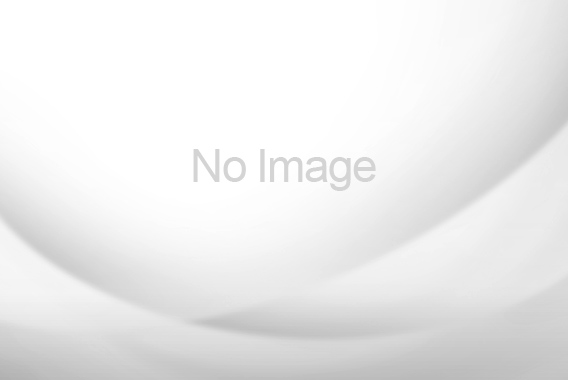
インボイス制度とは、インボイス(適格請求書)という請求書・領収書を使って取引をすることにより、消費税の仕入税額控除を受けられる制度で、2023年10月1日から施行されます。この制度は売り手、買い手の両方に適用されます。売り手側は、買い手側から求められればインボイスを交付しなければならず、その書類の写しを保存しておく必要があります。
売り手側がインボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。適格請求書発行事業者とは、インボイスの発行が認められた課税事業者のことです。ここでいう課税事業者とは、課税売上高が1000万円を超える、消費税を納付する義務がある法人・個人事業主のことです。
一方で、課税売上高が1000万円以下の法人・個人事業主は、国に消費税を納める義務がない「免税事業者」となり、適格請求書発行事業者の対象外となります。インボイス制度の施行後は、企業がインボイスを発行できない非適格請求書発行事業者から商品を購入した場合、消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。つまり、企業が課税事業者と取引する場合は、インボイスを発行することで取引時に発生する消費税は控除されますが、免税事業者と取引をする場合、消費税は控除されません。
関連記事:インボイス対策(1)免税事業者は関係ない?
https://www.bizclip.ntt-west.co.jp/articles/bcl00179-002.html
関連記事:インボイス対策(2)適格請求書発行事業者への道
https://www.bizclip.ntt-west.co.jp/articles/bcl00179-003.html
インボイス制度の認知度は6割越え
インボイス制度は商品の取引形態を大きく変える制度ということもあり、インボイスの対象となる事業者間では広く認知されているようです。
日経BPコンサルティングが2022年9月にモニター2251人を対象として実施した調査では、「具体的内容を理解している」「概要を理解している」「導入されることは理解している」の合計が61.0%を占めており、6割を超える事業者がインボイス制度を理解していると回答しました。その一方で、「ほとんど理解できていない」「本アンケートで初めて知った」の合計は39.0%となり、制度をよく知らない事業者も一定数存在します。
インボイス登録企業は全体で2割ほど
インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者として登録し、インボイスに記載する「発行事業者の登録番号」を取得する必要があります。
適格請求書発行事業者になるための申請手続きは、すでに受付が始まっています。前述の調査 では、「すでに対応済みである」が全体の21.4%、「具体的な準備を進めている」が35.2%で、合計では全体の56.6%がインボイス制度に積極的に対応していると回答しています。「対応していないし予定もない」という回答は、全体の11.9%と、全体的には少数派となっています。
ただし、事業者の規模別で見ると様相が変わります。従業員1万人以上の企業では、46.3%がインボイス制度に対応済みと回答しているのに対し、99人以下の企業では、対応済みの回答は11.8%にとどまり、27.2%が対応を予定していないと回答しています。このことから、小規模の企業では対応に苦慮している姿が見て取れます。
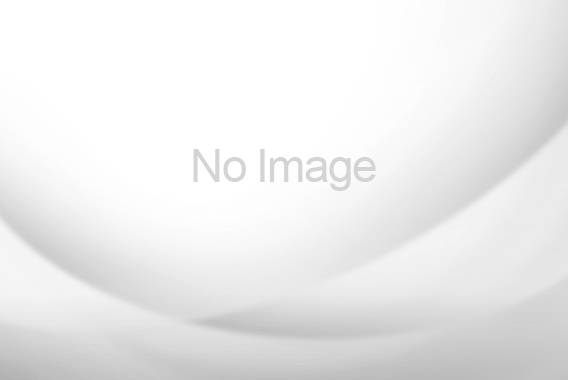
インボイス制度の施行により、新たに発生する経理事務があります。最も大きな変更点は、追加で請求書に記載すべき内容が発生する点です。インボイスとして認められる請求書には「登録番号」「適用税率」「税率ごとの消費税額」の記載が義務付けられています。自社でインボイスを発行する場合は、これらの項目が請求書に記載されていなければなりません。
課税事業者として取引先から請求書を受領する場合はさらに複雑になり、課税事業者と免税事業者を分けて経理処理する必要があります。また、取引相手がインボイスを発行できる課税事業者の場合は、相手から受け取る請求書に、先に述べた3項目が明記されているかどうか確認を行います。
一方、取引相手がインボイスを発行できない免税事業者の場合は、相手に支払う消費税が「仕入税額控除対象」にならないような経理処理が別途必要になります。これは、免税事業者に支払った金額は仕入税額控除として認められないためです。
つまり、インボイス制度の施行後は、新たに2通りに分けて別々の計算方法で経理処理を行うことになるので、手作業ではかなりの時間を要することが予想されます。状況によっては経理作業にかかる時間や人的リソースを削減し、業務効率化を図るため、会計システムの導入を検討する必要があります。
インボイス制度が定められた背景には、2019年10月に軽減税率が導入されたことが関係しています。軽減税率の導入により、10%と8%という異なる消費税率が混在し、適用される税率によって税込みの対価は異なります。
現行の請求書では、消費税について記載する義務がないため、どの商品にどの消費税率が適用されているのかは分かりません。そのため、8%の消費税を計上すべき部分で10%の消費税を計上し、差額分で不当に控除を受けることが可能になってしまいます。
この仕入れ額控除を正しく算出することを目的に、取引においてどちらの消費税率が適用されているのか正確に把握すべく、インボイス制度が導入されました。繰り返しになりますが、2023年10月のインボイス制度施行後は、インボイスがないと仕入税額控除を受けられなくなります。
インボイス制度を利用するには、自社を課税事業者として申請し、適格請求書発行事業者として認められ、登録番号を取得する必要があります。以下に、登録申請に必要な手順を解説します。
手順1:国税庁が発行する登録申請書を記入
自社を課税事業者として申請するためには、まず国税庁が発行する登録申請書に必要事項を記入します。登録申請書は国税庁のWebサイトからダウンロード可能です。申請書には国内用と海外用があります。
登録申請書による申請のほか、「e-Taxソフト(Web版)」、スマートフォン・タブレット用の「e-Taxソフト(SP版)」でも申請ができます。「e-Taxソフト(Web版)」「e-Taxソフト(SP版)」であれば、画面に表示される質問に回答するだけで申請できます。なお、「e-Taxソフト(SP版)」は個人事業主のみが対象です。
手順2:郵送・窓口持参・電子申請
申請書に記入したら、居住する地域の所轄税務署、またはインボイス登録センターに申請書を郵送します。所轄税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイトで郵便番号、住所、地図、税務署の一覧から検索できます。e-Taxソフトを使って電子申請する場合、紙の申請書を郵送する必要はありません。
手順3:税務署による審査
申請書を郵送またはe-Taxで電子申請したあとは、税務署によって審査が行われます。入力漏れや誤記などがあった場合は、差し戻しを受けたり、審査に通らなかったりする場合があります。審査を通過すれば、登録番号が発行されます。審査には相応の時間がかかるため、インボイス制度に早期に適応するためには、早めの申請が求められます。
手順4:適格請求書発行事業者公表サイトで確認
税務署で発行された登録番号を受け取ったら、適格請求書発行事業者公表サイトに自社の登録番号が掲載されます。登録番号を入力して検索し、検索結果で自社が確認できれば登録は完了です。
「e-Taxソフト(Web版)」と「e-Taxソフト(SP版)」でインボイス登録申請を行うには、電子証明書と利用者識別番号が必要です。
電子証明書として使えるものには、公的個人認証サービスであるマイナンバーカードの他、商業登記認証局や電子委任状取扱事業者である各事業者、地方公共団体組織認証基盤(LGPKI)や、政府共用認証局(官職認証局)などが発行する証明書があります。
利用者識別番号とはe-Taxを利用するために使う16桁の識別番号です。書面申請などのほか、「e-Taxソフト(Web版)」や「e-Taxソフト(SP版)」でも取得できます。なお、利用者識別番号はインボイス制度における適格請求書発行事業者の登録番号とは異なります。
免税事業者の場合、課税事業者としてインボイス制度に登録するか、インボイスに登録せずに免税事業者として続けるか選択を迫られることになります。課税事業者となることを避け、免税事業者として続けた場合、商品を購入した取引先が仕入税額控除を受けられないデメリットが発生します。
仕入税額控除とは、課税事業者が消費税を納税する際に、売り上げにかけられた消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いて、差額分を収める制度のことです。仕入税額控除には、二重課税を防ぐ効果があります。
しかし、インボイス制度の施行後に仕入税額控除を受けるためには、インボイスが必須となります。インボイスを発行できない事業者から商品を仕入れると仕入税額控除が受けられず、納税額が増えてしまうことになります。
こうした背景もあり、課税事業者は、適格請求書発行事業者ではない小規模の免税事業者との取引を避けるケースが増えると予想されます。免税事業者は、これまで取引をしていた企業に敬遠され、取引が停止される可能性もあります。
最後に、インボイス制度における注意点を3つ紹介します。
注意点1:2023年10月1日から利用したい場合は2023年3月31日までに申請する
インボイス制度が施行されるのは2023年10月1日で、すでに登録申請の受付は始まっています。国税庁では、2023年10月1日の施行から適格請求書発行事業者の登録を受けて制度を利用したい場合は、2023年3月31日までに申請を提出する必要があるとしています。登録完了までに、書類の場合は約1カ月、電子申請の場合は約2週間かかりますが、2023年3月31日前後は登録申請が集中して、通常よりも審査に時間がかかることが予想されます。早めの申請が望まれます。
注意点2:申請書に漏れや誤記が無いかを確認する、もしくはe-Taxで申請する
申請書に記入ミスや漏れがあった場合、審査に通らなかったり、申請書が差し戻しになったりすることもあります。その場合、修正や再申請を行わねばならず、登録までに時間がかかることになります。
e-Taxを利用した電子申請では、質問に回答するだけで申請登録が完了するため、記入漏れや間違いなどのリスクを低減できます。記入漏れが不安な場合は、e-Taxを使って申請することをおすすめします。
注意点3:免税事業者はインボイス登録ができない
適格請求書発行事業者としてインボイス制度を利用できるのは課税事業者のみで、免税事業者は対象外です。インボイス制度を利用したい場合は、免税事業者から課税事業者に切り替える必要があります。インボイス制度施行後も6年間の経過措置期間が設けられており、経過措置期間中に課税事業者に切り替えることも可能です。
インボイス制度は、消費税が正しく納付されることを目的にして導入された制度となります。特に、企業を相手にBtoBビジネスを行う事業者は、インボイス制度の内容を理解し、適格請求書発行事業者に登録するかどうか、十分に検討する必要があるといえます。
※掲載している情報は、記事執筆時点のものです
執筆= NTT西日本
【MT】
覚えておきたいオフィス・ビジネス情報のキホン