
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
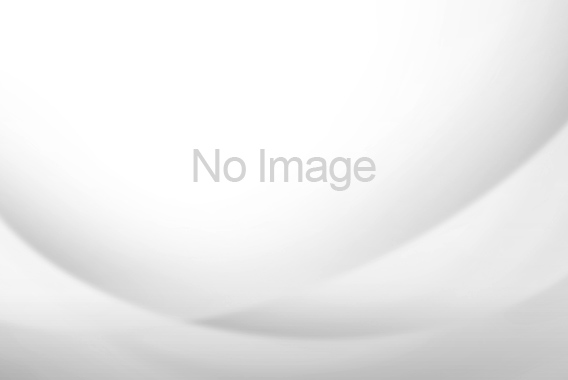
前回は免税事業者への影響を解説し、できるだけ早く準備を進めることが重要と説明しました。今回はその準備の具体策として、課税事業者を選択して「適格請求書発行事業者」になると決意された皆さんに、税務当局に対する手続きなどについて解説します。
前回もご説明しましたが、いわゆるインボイス制度は2023年10月1日から実施されます。そして、インボイスを発行するためには、その前に適格請求書発行事業者となっておく必要があります。当時、あまりニュースなどで取り上げられなかったので、ご承知の方は少ないかもしれませんが、実は昨年の10月1日から適格請求書発行事業者になるための登録申請は始まっています。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)は、法律上は納税地を所轄する税務署に提出することとされています。ただし、全国の各国税局ごとに「インボイス登録センター」が設置されており、郵送で提出する場合は所轄税務署ではなく、こちらに送付します。
適格請求書発行事業者は課税事業者でなければなりませんが、免税事業者が2023年10月1日から課税事業者になりたい場合には、原則として、6カ月前の2023年3月31日までに、この登録申請書を提出する必要があります。つまり対応の期限は9月末ではなく3月末となるため要注意です。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件(消費税法に違反して重い刑罰を受けた場合などで、通常関係ありません)に該当しないことなどの審査を行い、適格請求書発行事業者登録簿に登録を行い、登録された旨を申請者に通知することとなっています。この通知を受けるまでの期間として、登録申請書を郵送した場合で約2カ月かかる点にも注意する必要があります。
また、登録されますと、適格請求書発行事業者の「登録番号」「氏名または名称」「登録年月日」などが国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。これにより、受領した適格請求書などが真実の適格請求書発行事業者が交付したものかを確認できるようになり、そうでない請求書などでは仕入税額控除が受けられなくなります。
ここでひとつアドバイスですが、個人事業者の方は氏名が公表されるだけでなく、「主たる屋号」や「主たる事務所の所在地」なども公表された方が、交付先の事業者が確認しやすいと思いませんか。公表したい場合には、登録申請書と併せて、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出してください。決して登録申請書の「氏名または名称」欄に屋号を記載しないよう注意してください。
そして、登録された通知を受けたら、ご自身で「適格請求書発行事業者公表サイト」を確認して誤りがないか確認を行い、登録までの手続きは完了です。
次に、売り上げなどの取引先に自分が適格請求書発行事業者の登録を受けたと周知してください。買い手側として、取引先が課税事業者であれば、2023年10月1日以降も今までと同様の条件で取引ができると分かりますので安心してもらえると思います。
逆の立場で考えると、皆さんが簡易課税制度を選択しないのであれば、仕入れなどの取引先に対しては、適格請求書発行事業者になるよう仕向けないと100%の仕入税額控除が可能になりません。そうしたいのであれば、早期に仕入れ相手の対応確認が必要になってきます。
ところで、課税事業者を選択した場合、2023年10月1日から課税事業者として申告・納税する義務が課されます。その際、初めての方は「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると税額計算が簡素化されるとともに、交付を受ける適格請求書などの保存義務がありません。顧問税理士や税務当局によく相談した上で届出をするか否かを検討してください。
2回にわたってインボイス制度対策について説明をしてきました。今回の改正では何より早期の準備が大変であることをご理解ください。そして、現在免税事業者になっている個人事業主や小さな会社こそ、早期にこの件について取引先とのコミュニケーションを取っておかないと、2023年10月1日近くになってトラブルになりかねないので、ご注意ください。
執筆・編集協力=宮口 貴志
一般社団法人租税調査研究会事務局長
執筆=名取和彦
税理士・一般社団法人租税調査研究会主任研究員 国税局消費税課審理担当、国税不服審判所副審判官、税務大学校教授、国税局主任税務相談官、複数の税務署長を歴任。2021年7月退職。同年8月税理士登録。
【TP】
個人事業主・小さな会社の納税入門