
ビジネスWi-Fiで会社改造(第50回)
5GとビジネスWi-Fiの使い分け ~速度・コスト・利便性で比較
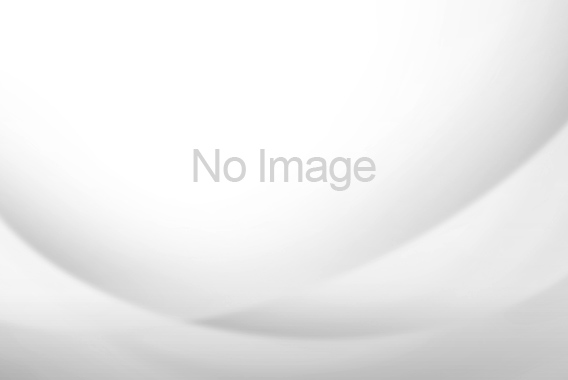
金融商品への投資で税金のかからない「NISA(ニーサ)制度」を理解して活用しましょう。2023年度税制改正により、2024年以降のNISA制度の非課税投資枠の大幅な拡大と制度の恒久化などが示されました。そもそも政府は、家計資産の貯蓄から投資へのシフトを目指しています。家計で保有している2000兆円ともいわれる資産の半分以上を現金預金が占めているとされていますが、この資産を投資に回せば企業が成長し、家計においても金融資産を増やせるという好循環を期待してのものです。
これを実現するための方策として2014年1月にスタートしたNISA制度を、今回大きく改正しました。前編では現在のNISA制度の内容を知っていただき、次回の後編では改正によってどのように変更するのかを詳しく解説していきます。
通常ですと、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらの商品を売却して受けた利益や受け取った配当金などに対しては、約20%の税金がかかります。NISA制度は、NISA口座(非課税口座)内において、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られた利益について税金がかからない(非課税)制度です。
そもそもNISAとは、イギリスのISA(Individual Savings Account(個人貯蓄口座))をモデルとして、日本版ISA(Nippon Individual Savings Account)を「ニーサ」と呼称しているものです。NISAには、18歳以上の成年が利用できる「一般NISA」「つみたてNISA」と、17歳未満の未成年が利用できる「ジュニアNISA」の3種類があります。なお、「ジュニアNISA」は、2020年度の制度改正において新規の口座開設は2023年までとされ、2024年以降は新規購入ができないとされていますので、詳細は省略します。ここからは、「一般NISA」と「つみたてNISA」について解説し、その後に各NISAの注意点を説明します。まずは一般NISAです。
「一般NISA」は2014年1月にスタートしました。少額から投資を行う方のための非課税制度で、投資信託に投資した場合の普通分配金と売却時の譲渡益が非課税になります。毎年120万円(2015年以前は100万円)分の金融商品(株式・投資信託など)が購入可能です。こうした年間の非課税限度額を「年間非課税枠」といいます。
各年に購入した金融商品を保有している間に受けた配当金や、値上がりした後に売却して受けた利益(譲渡益)について、購入した年から数えて5年間は課税されません。非課税で保有できる投資総額は、最大で600万円となります。
非課税である5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の「年間非課税枠」に移すことができるほか、「一般NISA」口座以外の一般口座や特定口座に移す(移管する)こともできます。現在、「一般NISA」は2023年までの制度とされていますので、この口座において金融商品の購入ができるのは2023年までです。当然ながら、2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有できます。
次に「つみたてNISA」ですが、こちらは特に少額からの長期・積み立て・分散投資を支援するための非課税制度で、2018年1月にスタートしました。購入できる金額は年間40万円までで、購入方法は累積投資契約に基づく買い付けに限られており、非課税期間は20年間です。
対象商品は手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積み立て・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資の初心者をはじめ幅広い年代の方が利用しやすい仕組みとなっています。各年に購入した投資信託を保有している間に受けた分配金と値上がりした後に売却して受けた利益(譲渡益)について、購入した年から数えて20年間課税されません。
非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の一般口座や特定口座に払い出されます。現在、「つみたてNISA」は2023年までの制度とされていますので、投資信託の購入ができるのは2023年までですが、2023年中に購入した投資信託についても20年間(2042年まで)は非課税で保有できます。
最後に両NISAの注意点を説明します。NISA口座は、1人1口座に限り開設できます。ですから、開設したNISA口座内では、一般NISAとつみたてNISAを併用できず、どちらか一方を選択する必要があります。その年の年間非課税枠の未使用分(限度額に達していない分)があっても、翌年以降に繰り越しできません。
NISA口座で保有している金融商品が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合は、他の一般口座や特定口座で保有している金融商品の配当金や分配金あるいは売却によって得た利益との相殺(損益通算)ができません。
現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移す(移管)ことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。以上が現在のNISA制度の解説となります。後編では、2024年1月から始まる新NISA制度の改正のポイントと、2023年で終了する現行制度との比較について解説します。
執筆=笹崎浩孝
税理士・一般社団法人租税調査研究会主任研究員
国税局課税一部資料調査課主査、国税局個人課税課課長補佐、国税局査察部統括査察官、国税局調査部統括国税調査官をはじめ、複数の税務署長を経て、2021年7月退職。同年8月税理士登録。
編集協力=宮口貴志
一般社団法人租税調査研究会専務理事・事務局長
株式会社ZEIKENメディアプラス代表取締役。元税金の専門紙および税理士業界紙の編集長、税理士・公認会計士などの人材紹介会社を経て、TAXジャーナリスト、会計事務所業界ウオッチャーとしても活動。
一般社団法人租税調査研究会(ホームページ https://zeimusoudan.biz/)
専門性の高い税務知識と経験をかねそなえた国税出身の税理士が研究員・主任研究員となり、会員の会計事務所向けに税務判断および適切納税を実現するアドバイス、サポートを手がける。決して反国税という立ち位置ではなく、適正納税を実現していくために活動を展開。
【T】
個人事業主・小さな会社の納税入門