
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
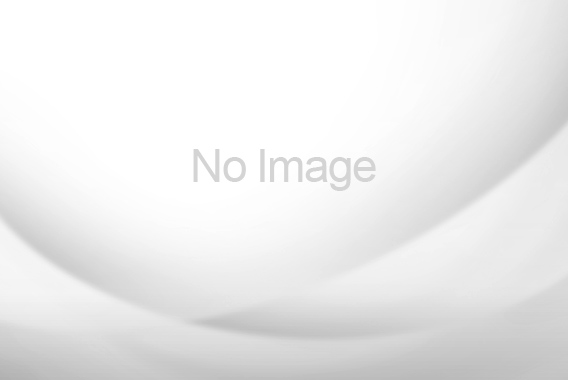
顧問先2200社を抱える会計事務所を率いる公認会計士、古田土満氏が語る小さな企業の経営のコツ。前回の第23回は、経営者がクレームの大きな原因である「報・連・相不足」を改善するコツを紹介しました。今回は、挨拶・掃除・朝礼の効果について解説します。どれも社員には面倒に感じられることもある挨拶・掃除・朝礼ですが、それぞれが社員のためになると古田土氏は力説します。
社員をしつけるのではなく、会社をしつける。そのための方法として、古田土会計は挨拶・掃除・朝礼を大切にしてきました。実は開業して20年くらいは、「挨拶と掃除ばかり強制して、税法や会計を教えてくれない。こんな会社には勤められない」と言って、多くの社員が辞めていきました。
代わって入ってくるのは、会計の資格も経験もない社員たちです。残っている社員からは「もっと経験者や資格者を入れてください」と言われ続けました。しかし、古田土会計の経営理念や駅前清掃、小中学校でのトイレ清掃、挨拶の話をすると、多くの経験者・資格所有者に入社を断られました。
結果、古田土会計には会計のプロや税法のプロは少ないのですが、営業活動をしなくても口コミでお客さまは増え続け、売り上げは伸び続けてきました。2016年12月期の決算では売上高15億8000万円、社員は181人、2017年の4月には190人になります。
他の会計事務所では、有資格者をたくさんそろえ、勉強会をしっかりやっているところが多いように思います。ただし、1人当たりの粗利益額や1人当たりの経常利益、1人当たりの給与は古田土会計のほうが高いのが現実です。
一般的には、全社員が互いに元気な挨拶をする時間、30分かける朝礼、社内と社外の清掃にかける30分間は、いずれも仕事をしていないのですから、生産性は低くなるはずです。しかし現実は、挨拶・掃除・朝礼をしっかりやっている我が社のほうが生産性は高いのです。
『データの見えざる手』(矢野和男著、草思社)という書籍があります。センサーを用いた、100万人以上の人間行動の研究の成果をまとめたものです。人間は、よくも悪くも、自分の周りの環境要因の変化に慣れてしまいます。この環境要因には、職場の人間関係、人事評価、給与、健康など全てが含まれます。しかし、これらの環境要因を全て合わせても、当人の幸せに対する影響は、全体の10%にすぎないのだそうです。50%は遺伝的に決まっていて、残りの40%は、日々の行動のちょっとした習慣や行動の選択の仕方、特に自分から積極的に行動を起こしたかどうかが重要になります。
自ら意図を持って何かを行うことで、人は幸福感を得ます。例えば人に感謝を表す、困っている人を助けてあげる、という簡単なことでも、幸せは格段に高まるのです。行動を起こすこと自体が、人の幸せなのです。
研究の結論の1つとして、「活発な現場」では「社員の生産性が高まる」「活発でない現場」では「社員の生産性が低くなる」このことは普遍的、一般的な傾向である、としています。いくら優秀な社員がいても自己中心的な人間の集団では職場の活発度が低くなり、生産性は低いのです。反対に、会社が社員を幸せにする経営理念を持って、お客さまに喜ばれたり、感謝されたりする仕事をしていけば、社員は幸福感が高まり、結果として生産性が高まることがデータとして証明されました。
会社の活発度を上げる具体的な繰り返しの行動が挨拶、掃除、朝礼です。挨拶は相手より先に元気よく明るく、大きな声でするものです。目線を合わせ、笑顔ですることによりお互いのモチベーションは上がり、お互いが幸せになります。
反対に、お互いに無視・無関心で挨拶もしない集団で、社員は幸せを感じることができるでしょうか?
・朝礼でスピーチをする。
・うなずきながら聞く。
・よいことがあると、大きな拍手を笑顔でする。
・お互いに相手をほめる。
・ハッピー体操(古田土会計が朝礼時にしている体操)をして、相手の方に心地よくなってもらう。
・お互いに「ありがとう」「感謝します」を連発して幸せな気持ちになる。
こうした行動によって目の前のお客さまにどうしたら喜ばれるかを考え、実行して、お客さまから「ありがとう」「感謝します」と言われ続ければ、会社は成功します。会社は社員に幸せになってもらうために、繰り返しの力である挨拶・掃除・朝礼を形にして実行しましょう。
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=古田土 満
法政大学を卒業後、公認会計士試験に合格。監査法人にて会計監査を経験して、1983年に古田土公認会計士・税理士事務所を設立。財務分析、市場分析、資金繰りに至るまで、徹底した分析ツールによって企業の体質改善を実現。中小企業経営者の信頼を得る。
【T】
人気会計士が語る、小さな会社の経営“これだけ”