
ビジネスWi-Fiで会社改造(第49回)
テレワークでの通信障害対策を考えよう
顧問先2200社を抱える会計事務所を率いる公認会計士、古田土満氏が語る小さな企業の経営のコツ。その第7回での最後で、「膨張拡大」ではなく「安定成長」をめざすことをお勧めしました。今回は、古田土氏が考える「成長」と「膨張」の違いを紹介します。それに当てはめると、あなたの会社は「成長」でしょうか。それとも「膨張」でしょうか。
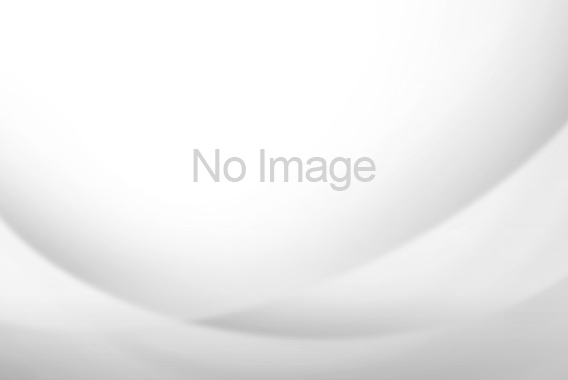 経営に現状維持はありません。拡大しているか、縮小しているかです。その拡大について、膨張しているだけなのに成長していると勘違いしている経営者の方が多くいます。では、「成長」と「膨張」の違いがどこにあるのか私見を書きます。
経営に現状維持はありません。拡大しているか、縮小しているかです。その拡大について、膨張しているだけなのに成長していると勘違いしている経営者の方が多くいます。では、「成長」と「膨張」の違いがどこにあるのか私見を書きます。
売上高は大幅に増加しているが、それに伴い仕入れ、人件費、経費も大幅に増え、税引き後利益が増えない。しかも、この状態が継続している。まずこういうケースは、膨張していると思った方がよいと思います。
会社は設備投資をすると、売り上げに先行して、人件費、広告費などがかかりますから、利益額が大幅に減少することがあります。過去にもこのようなことがあり、内部蓄積の厚い会社は、先行経費がなくなれば利益はすぐに出ますから、心配はいりません。
問題は、内部蓄積のない会社が設備投資や新規事業を行う場合です。会社に資本の蓄積がないということは、過去に売り上げは拡大したがもうからなかったということです。そして資本の蓄積がない会社は、自己資金がないから設備投資資金を借入金により調達します。
借入金は返済しなければなりません。借入金の返済原資は、原則として利益です。利益の蓄積がない、つまりもうからないということは、返済できないということです。設備は使って摩耗していても、借入金が減っていかないと、借金を返済するために借金をしているという状態になります。そして、借金を返済するために売り上げを拡大しようとします。
売り上げが拡大すると、売掛金や在庫が増えます。その結果、在庫資金、売上仕入資金が必要となり、さらに借金が増えます。このような状態が続くと、銀行はお金を貸ししぶるようになります。このように利益の出ないまま売り上げが増加し、資産の拡大と借入金の増加する状態を「膨張する」といいます。
「成長」は、売り上げの拡大は当然ですが、長期借入金の返済を利益で賄えている状態です。キャッシュフロー計算書の営業キャッシュフローの額で、借入金の返済ができていることです。理想は、設備投資額を引いたフリーキャッシュフローの額で借入金の返済ができることです。
分かっていただきたいのは、設備投資などにより会社が拡大するときには、事前にその投資は十分に採算が合うのか、何年で回収できるのかを計算し、借入金の返済額は利益で賄うことを前提に、安全な返済額を銀行にお願いすることです。返済期間は、長ければ長いほどよいと思います。この返済額を返済できなくなったら、この投資は「成長」ではなく、「膨張」だったと考えるわけです。
「成長」と「膨張」についてお金のことだけ書きましたが、その他にも大事な人材の問題があります。人が成長していないのに、規模のみ拡大して会社が潰れるケースは世の中にたくさんあるからです。
人材のケースでは、実は社長という人間が成長していなくて膨張していただけなのだと考えると、経営は分かりやすいと思います。私たち古田土会計は、どちらかというと会社の成長に人の成長がついていっていないのが現実です。10%以上成長しない方針ですが、これも膨張と思い質の教育に重点を置いています。
※本記事は、2017年に書籍として発刊されたものです
執筆=古田土 満
法政大学を卒業後、公認会計士試験に合格。監査法人にて会計監査を経験して、1983年に古田土公認会計士・税理士事務所を設立。財務分析、市場分析、資金繰りに至るまで、徹底した分析ツールによって企業の体質改善を実現。中小企業経営者の信頼を得る。
【T】
人気会計士が語る、小さな会社の経営“これだけ”